インタビュー・講演録
-

福島第二原発の危機対応から学べるもの
2011年3月11日の東日本大震災で、福島第一原子力発電所と同様に地震・津波の被害を受けながらも、炉心損傷に至ることなく全号機の冷温停止を達成した福島第二原子力発電所。現場指揮にあたったのが当時所長だった増田尚宏氏だ(現日本原燃株式会社 社長)。危機的な状況の中でも落ち着いて的確に現場をまとめあげたリーダーシップは海外でも評価され、ハーバード・ビジネス・スクールの授業でも取り上げられているという。その増田氏が当時を振り返った
2019/03/27
-

福島第二原発の危機対応から学べるもの
2011年3月11日の東日本大震災で、福島第一原子力発電所と同様に地震・津波の被害を受けながらも、炉心損傷に至ることなく全号機の冷温停止を達成した福島第二原子力発電所。現場指揮にあたったのが当時所長だった増田尚宏氏だ(現日本原燃株式会社 社長)。危機的な状況の中でも落ち着いて的確に現場をまとめあげたリーダーシップは海外でも評価され、ハーバード・ビジネス・スクールの授業でも取り上げられているという。その増田氏が当時を振り返った
2019/03/19
-

災害対応にはゴールと施策明確な戦略を
リスク対策.comは12日、東京都千代田区の明治薬科大学剛堂会館ビルで第3回危機管理塾を開催。システム開発などを手がけるクレオの内部統制室リスクマネジメントグループマネージャーの永井勝氏が「BCP(事業継続計画)は本当に回せるのか!? Bousai Continuity Planでいいじゃないか」をテーマに講演した。
2019/03/14
-

BCPは有効に機能するか〜定着のポイントとメリット~
2006年から国際標準化機構(ISO)でBCP(事業継続計画)に関する規格の策定が始まり、私もその委員を務めています。その関係でBCP導入企業がどのくらいBCPを定着させているのか、非常に関心があります。現実には、BCPの定着に悩んでいる企業が少なくないようです。
2019/03/13
-

福島第二原発の危機対応から学べるもの
2011年3月11日の東日本大震災で、福島第一原子力発電所と同様に地震・津波の被害を受けながらも、炉心損傷に至ることなく全号機の冷温停止を達成した福島第二原子力発電所。現場指揮にあたったのが当時所長だった増田尚宏氏だ(現日本原燃株式会社 社長)。危機的な状況の中でも落ち着いて的確に現場をまとめあげたリーダーシップは海外でも評価され、ハーバード・ビジネス・スクールの授業でも取り上げられているという。その増田氏が当時を振り返った
2019/03/13
-

次なる広域複合災害に向けた3.11の教訓とは
当社は大正元年(1912年)4月の創業、今年で108年目を迎える魚肉練製品製造販売業を行う会社です。商品は現在42品目ほどを製造販売しており、宮城名産の笹蒲鉾をはじめ、揚げ蒲鉾、手作り商品も作っています。工場拠点はすべて宮城県石巻市にあり、この工場すべてが被災するというかたちになりました。
2019/03/12
-

東日本大震災で実践できたBCP〜被災しても継続できる体制作り〜
当社の創業は昭和32年(1957年)、法人化が63年(1988年)。エンジンオイルなどを集めてきて、再生重油に加工処理して販売しています。そのほか、特殊なものでは、酸やアルカリを集めてきてブレンドし、セメント工場で使える加工用水にリサイクルしています。
2019/03/11
-

熊本地震での対応~社員を守れずして、真の復興はない~
2016年の熊本地震では、震度7の地震が2回ありました。50人の命を奪い、前震と本震の2回の揺れで建物はかなり壊れました。震度5以上の揺れは20回以上、車中泊も含めて20万人以上の方が避難しました。
2019/03/08
-

熊本地震から早期災害復旧のポイント
弊社は富士フイルムの100%出資の生産子会社として、2005年4月、熊本県菊陽町に設立されました。社員が当時で300名程、平均年齢32歳という若い会社です。主力製品である液晶用タックフィルムは、世界の総需要の約40%を私どもの工場で生産しています。
2019/03/07
-

獺祭のブランド守り抜く、西日本豪雨での対応
私どもが作る「獺祭」というお酒は、全て「山田錦」を使い、全て純米大吟醸、それを年間通して醸造することが特徴です。年間通して新鮮なものを作れますし、稼働率も非常によくなります。
2019/03/06
-

福島第二原発の危機対応から学べるもの
2011年3月11日の東日本大震災で、福島第一原子力発電所と同様に地震・津波の被害を受けながらも、炉心損傷に至ることなく全号機の冷温停止を達成した福島第二原子力発電所。現場指揮にあたったのが当時所長だった増田尚宏氏だ(現日本原燃株式会社 社長)。危機的な状況の中でも落ち着いて的確に現場をまとめあげたリーダーシップは海外でも評価され、ハーバード・ビジネス・スクールの授業でも取り上げられているという。その増田氏が当時を振り返った
2019/03/06
-

被災しても成長する企業に学ぶ
東京都中小企業振興公社は1月24日、「被災しても成長する企業に学ぶ〜強い企業の秘訣と組織を活性化させるBCPの構築方法〜」をテーマとするBCP策定推進フォーラムを都内で開催した(企画:リスク対策.com)。
2019/03/05
-

サイバー対策、サプライチェーン全体に必要
経済のグローバル化により、サプライチェーンが世界各地に広がる中で、日本企業においても、海外の指標と整合性のとれたサイバーセキュリティ対策が求められている。日本企業のサイバーセキュリティ対策の現状や今後の展望について、デル・テクノロジーズグループでサイバーセキュリティ事業を担うRSAのアジア太平洋・日本担当チーフサイバーセキュリティアドバイザー、レナード・クレインマン氏に聞いた。
2019/01/17
-

アカマイ、買収でセキュリティ事業強化
主に金融や観光、航空、Eコマースなど、オンラインサービスが本業に大きなインパクトを与える企業向けに、常に高速・安定・安全を提供するCDN(コンテンツ・デリバリ・ネットワーク)サービスを手掛ける世界最大手、アカマイ・テクノロジーズ(以下、アカマイ)が企業向けのセキュリティ事業の強化を加速させている。きっかけの1つとなったのは2017年11月、DNSサーバー周辺のソリューション事業を手掛けるノミナム社を買収したこと。2社の技術とノウハウを融合させることで着々と相乗効果が生まれているという。キャリアビジネス戦略開発部ヴァイスプレジデント(VP)であるジョン・ワトソン氏に最新動向を聞いた。
2019/01/09
-

膨張する企業データに新管理手法
IoT(モノのインターネット)やAI(人工知能)によるビッグデータ活用、4K・8K映像の編集など、企業が扱う業務データは近年急激に増加し、企業のデータ管理手法が根本的な変更が求められている。こうしたなか従来の自社内で構築・運用するオンプレミス型データストレージを活用しながら、新たなクラウド型ストレージを融合させ、両者の強みを生かして大量のデータを安価、安全に管理ができる「オブジェクト・ストレージ」というデータ管理サービスが注目されている。データストレージ企業の米ネットアップでオブジェクト・ストレージ部門を統括するダンカン・ムーア氏と、同社日本法人のシステム技術本部でソリューションアーキテクトを務める箱根美紀代氏に聞いた。
2019/01/08
-

耐震化へ行政は住民寄り添い悩み解決を
3月29日、旧耐震基準の建築物の診断結果を東京都が公表。延床面積1万m2以上の不特定多数が利用する大規模施設と特定緊急輸送道路沿道建築物が対象だったが、港区のニュー新橋ビルなど著名な施設が震度6強以上で倒壊の可能性が高いことがわかった。また、調査対象の約3割が6強以上で倒壊可能性あり、約2割は倒壊可能性大という結果は大きな波紋を呼んだ。この前日の同28日には都の「特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化促進に向けた検討委員会」が未耐震化建築物の公表を含めたふみこんだ内容の報告書のとりまとめを行っていた。同委員会の委員長を務めた東京大学生産技術研究所准教授の加藤孝明氏が今年の災害も含め振り返った。
2018/12/28
-

中小企業の海外進出に安全・安心を
世界最大級の保険グループであるアクサグループ。そのアクサグループの中でアシスタンスビジネスを提供するアクサ・パートナーズの日本法人であるアクサ・アシスタンス・ジャパン株式会社では、日本商工会議所と提携して、会員中小企業向けに「商工会議所の海外危機対策プラン」を提供している。香港から来日したアクサ・パートナーズ・アジアCEOのジェローム・イッティ氏に話を聞いた。
2018/12/28
-

集中・効率化に歯止め、災害備え変革を
11日、内閣府を中心とした政府の中央防災会議は南海トラフ沿いで地震など最初の異常が起こった場合の対応について報告書のとりまとめを行った。M(マグニチュード)8.0以上の地震が起こった際は、被害がなかったエリアでも続く地震に備えて津波の危険のあるエリアから1週間避難することなど、最初の異常があった際の大まかな方針をまとめた。このとりまとめを行ったワーキンググループ(WG)の主査である名古屋大学教授・減災連携研究センター長の福和伸夫氏が今年の災害を振り返った。
2018/12/21
-

大災害は国が積極関与、水害情報改善へ
山本順三・防災担当大臣は23日、内閣府で報道陣のグループインタビューに応じ、災害対応について地方自治体を国が支援するなど積極的に関与し、自治体と一体であたる方針を示した。また台風や大雨の際、避難につながるような情報伝達に努めていくほか、ハード面も充実させる国土強靭化にも意欲を示した。
2018/10/24
-

つながり支援や企業連携で災害対策強化
災害やテロなど有事に友人に無事を知らせるほか、支援の提供を申し出たり受けたりできるフェイスブックの機能である「災害支援ハブ」。安否確認については世界で1400回以上起動し、2017年11月時点で累計約30億人が利用した。日本でもここ2年で19回発動しているという。この機能ができたきっかけは2011年の東日本大震災だった。フェイスブック ジャパン代表取締役の長谷川晋氏に災害への取り組みを聞いた。
2018/10/19
-

第3回【港区】700棟の高層マンションを守れ!(上)
東京都23区内の各自治体は、災害への対策に対して各地域に即した体制で過去の経験を活かしながら取り組まれています。地形、災害経験などハード・ソフト面の特性は一つとして同じ地域はありません。それぞれの地域で予測されていること、予防計画、また、今後の取り組みなど現在の状況を各行政区の方々、地域で防災に関する活動をされている方々に伺い、お伝えしていきます。ご自身が住んでいるまちのことはもちろん隣町や連携する可能性があるまちのことを改めて知っていただける機会となるよう取材を続けてまいります。
2018/09/06
-

地方データセンターで災害対策と省エネ
ICTの進展により、年々重要性が増し続けるデータセンター。集中する企業の所在同様、63%は首都圏に置かれている。株式会社データドックの宇佐美浩一社長はBCP(事業継続計画)の面からも現状を疑問視。災害対策と省エネの観点から新潟県長岡市でデータセンター事業を展開する。
2018/08/31
-

災害リスクに対抗、クラウドで事業継続
企業で導入が広がるクラウド。利便性の向上やサイバーセキュリティのほか、近年は災害時に有効なバックアップとしても注目をされている。国内約1500社のデータをバックアップする、ねこじゃらし代表取締役・川村ミサキ氏に話を聞いた。
2018/08/17
-

LINE、乗っ取りは改良や啓発で対策
2011年の東日本大震災を契機に開発されたチャット・通話アプリ「LINE」。もはや生活に欠かせない通信手段となっている。高い利便性が特長の同アプリのセキュリティに関する取り組みについて取材した。
2018/07/25
-

水害に脆弱な東京、企業はBCP策定を
東京都が3月30日に策定した「想定し得る最大規模の高潮による浸水想定区域図」。1000~5000年に1度の台風と高潮、さらには河川での洪水や堤防決壊による被害を見込んだものではあるが、23区の約3分の1にあたる約212km2が浸水すると想定。東部を中心に浸水域は17区に広がり、墨田区や江東区では最大浸水深さ10m以上となるという衝撃のものだった。浸水被害にどう備えるべきか。元東京都および江戸川区職員で公益財団法人リバーフロント研究所の技術参与・土屋信行氏に話を聞いた。
2018/06/22


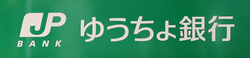
















![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)





