BCP事例
-

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入
日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。
2025/04/15
-

生コン・アスファルト工場の早期再稼働を支援
能登半島地震では、初動や支援における道路の重要性が再認識されました。寸断箇所の啓開にあたる建設業者の尽力はもちろんですが、その後の応急復旧には補修資材が欠かせません。大手プラントメーカーの日工は2025年度、取引先の生コン・アスファルト工場が資材供給を継続するための支援強化に乗り出します。
2025/04/14
-
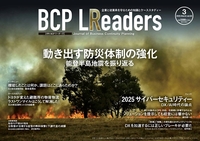
リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ
リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。
2025/04/05
-
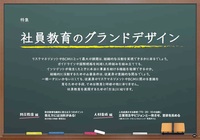
効果的な「学び」を組み立てる
人が大きく入れ替わり新たな制度や仕組みがスタートする新年度、あらためて社員教育について考えてみませんか。リスクマネジメントやBCMの活動で重要なのは、従業員の意識の醸成。効果的な「学び」を組み立てるための方法論をお届けします。事例紹介も、既存の防災・BCP活動を拡充して新しいプロジェクトを開始する企業を取り上げました。
2025/04/05
-
災害救助法等の大型改正を考える被災者支援の充実を中心に
本セミナーは、日本災害福祉研究会の企画協力により、パネルディスカッション形式で、災害関連法大型改正の意義とポイントを紹介。特に被災者支援の充実に関して、何がどう変わるのかを整理するとともに、運用上の課題とこれからの展望を現場の実態をふまえて掘り下げました。2025年3月31日開催。
2025/04/03
-
BCPの実効性を高める5つのポイント~能登半島地震の16社の分析結果を解説~
本セミナーでは、能登半島地震において、どのような対応、対策が速やかな復旧を実現したのかを、製造業、サプライチェーン上の主要な企業16社に対して経済産業省中部経済産業局が行ったインタビューをもとに整理した内容をご報告いただきました。2025年3月28日開催。
2025/04/01
-

リスクマネジメントを組織文化として醸成するための取り組みエイブルホールディングス
2025年3月の危機管理塾は4月21日16時から行います。今回の発表者はエイブルホールディングスでリスクマネジメント室室長を務める樋口達巳さんです。
2025/03/28
-

全社員が「リスクオーナー」リーダーに実践教育
エイブルホールディングス(東京都港区、平田竜史代表取締役社長)は、組織的なリスクマネジメント文化を育むために、土台となる組織風土の構築を進める。全役職員をリスクオーナーに位置づけてリスクマネジメントの自覚を高め、多彩な研修で役職に合致したレベルアップを目指す。
2025/03/18
-

阪神・淡路大震災から30年 あのときを振りかえる消火、救助活動の現実
日本の災害対策と防災活動の立脚点となった阪神・淡路大震災の当時の状況について一般社団法人・兵庫県消防設備保守協会の長畑武司さんにお話しいただきました。2025年2月17日開催。
2025/03/12
-

BCPの実効性を高める5つのポイント~能登半島地震の16社の分析結果を解説~
※2025年3月28日(金曜日)に会場にて開催します。お間違えのないようお申し込み下さい。なお、アーカイブを含め配信はございません。リスク対策.comでは、3月28日に、「リスク対策.PRO会員」限定のセミナーを開催します(1社2名までご参加可能です)。
2025/03/05
-

復旧時間の短縮を目指す、ADEKAのBCM
2025年3月の危機管理塾は3月19日16時から行います。今回の発表者はADEKAの環境・安全対策本部で課長を務める平野 富也さんです。
2025/02/21
-

現場対応を起点に従業員の自主性促すBCP
神戸から京都まで、2府1県で主要都市を結ぶ路線バスを運行する阪急バス。阪神・淡路大震災では、兵庫県芦屋市にある芦屋浜営業所で液状化が発生し、建物や車両も被害を受けた。路面状況が悪化している中、迂回しながら神戸市と西宮市を結ぶ路線を6日後の23日から再開。鉄道網が寸断し、地上輸送を担える交通機関はバスだけだった。それから30年を経て、運転手が自立した対応ができるように努めている。
2025/02/20
-

2度の大震災を乗り越えて生まれた防災文化
「ダンロップ」ブランドでタイヤ製造を手がける住友ゴム工業の本社と神戸工場は、兵庫県南部地震で経験のない揺れに襲われた。勤務中だった150人の従業員は全員無事に避難できたが、神戸工場が閉鎖に追い込まれる壊滅的な被害を受けた。30年の節目にあたる今年1月23日、同社は5年ぶりに阪神・淡路大震災の関連社内イベントを開催。次世代に経験と教訓を伝えた。
2025/02/19
-

阪神・淡路大震災から30年 あのときを振りかえる消火、救助活動の現実
2025年2月の危機管理塾は2月17日16時から行います。一般社団法人 兵庫県消防設備保守協会の長畑 武司氏です。
2025/02/07
-
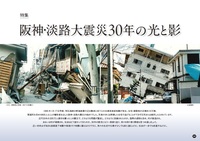
阪神・淡路大震災30年の光と影
阪神・淡路大震災から30年。今号では、発災直後の被災地で奔走した元消防署長、被災地を見つめ多くの災害支援に関わってきた専門家、被災の経験を継承し防災・BCP活動に取り込む企業の声を取り上げました。30年の節目にもう一度この震災を振り返り、我々を取り巻く環境を見つめ直せるように、日々の仕事や生活が一歩でも前進するように。
2025/02/05
-
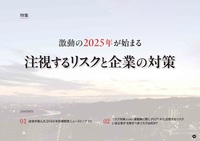
激動の2025年が始まる
激動の予感をはらんで2025年がスタート。今号はリスク対策.com の連載陣から、2025年に注視するリスクと企業が取り組むべき対策についてメッセージをいただきました。恒例の事例紹介は、降りかかる危機を教訓に課題の検証と改善を続ける企業を取り上げています。今年もリスク対策.comをよろしくお願いします。
2025/01/05
-

能登半島地震はBCPをどう変えたか市立輪島病院の経験
2025年1月の危機管理塾は17日(金)16時から行います。発表者は、市立輪島病院事務部長の河﨑国幸氏です。1年前、住民の命に直結する医療・福祉の現場で何が起き、どのような対応が求められたのか。業務継続計画の何が機能し、何が機能しなかったのか。新たに必要な視点は何か。能登半島地震発生から1年が経ったいま、当時を振り返っていただき、得られた教訓を発表いただきます。
2024/12/24
-

水害BCPタイムライン研修講座【リスク対策.PRO限定】
※2025年1月28日(火曜日)に会場にて開催します。お間違えのないようお申し込み下さい。なお、アーカイブを含め配信はございません。当日はPCを使って実際にタイムラインを作成していただきます。必ずお持ちください。
2024/12/20
-

製品供給は継続もたった1つの部品が再開を左右危機に備えたリソースの見直し
2022年3月、素材メーカーのADEKAの福島・相馬工場が震度6強の福島県沖地震で製品の生産が停止した。2009年からBCMに取り組んできた同工場にとって、東日本大震災以来の被害。復旧までの期間を左右したのは、たった1つの部品だ。BCPによる備えで製品の供給は滞りなく続けられたが、新たな課題も明らかになった。
2024/12/20
-
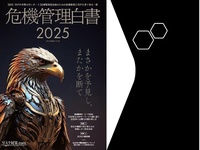
危機管理白書2025年版
A4サイズ、100ページ(本文96ページ)、カラー12月17日からECサイト「BASE(ベイス)」より発売。※2024年12月23日から順次発送いたします(12月28日~2025年1月6日は年末年始休業となります)。
2024/12/17
-

女性が本当に求める災害対策 コニカミノルタのアプローチ
2024年12月の危機管理塾は12月18日16時から行います。コニカミノルタ株式会社の林 佳津子氏です。
2024/12/05
-
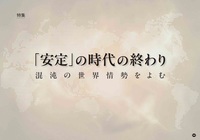
「安定」の時代が終わる
冷戦が終わって30余年。グローバル経済のもとで築き上げられてきた「安定」が崩れつつあります。安全保障上の対立、国家間のイデオロギー争い、パワーバランスの多極化、地政学リスクの高まり――。この混沌を企業はどう生きるのか。2024年の世界情勢を振り返り、来る2025年を展望します。また、今年二重被災に見舞われた能登半島が日本の防災に投げかける問題を考えます。
2024/12/05
-

ランサム攻撃訓練の高度化でBCPを磨き上げる
大手生命保険会社の明治安田生命保険は、全社的サイバー訓練を強化・定期実施しています。ランサムウェア攻撃で引き起こされるシチュエーションを想定して課題を洗い出し、継続的な改善を行ってセキュリティー対策とBCPをブラッシュアップ。システムとネットワークが止まっても重要業務を継続できる態勢と仕組みの構築を目指します。
2024/11/17
-

セキュリティーを労働安全のごとく組織に根付かせる
エネルギープラント建設の日揮グループは、サイバーセキュリティーを組織文化に根付かせようと取り組んでいます。持ち株会社の日揮ホールディングスがITの運用ルールやセキュリティー活動を統括し、グループ全体にガバナンスを効かせる体制。守るべき情報と共有すべき情報が重なる建設業の特性を念頭に置き、人の意識に焦点をあてた対策を推し進めます。
2024/11/08
-
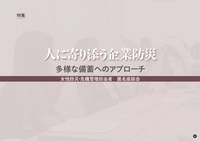
人に寄り添う企業防災
災害時に受ける影響は、個人ごとに異なります。多様な個人へのきめ細かな寄り添いが求められる時代、企業防災にも人間視点の見直しが求められるようになりました。本紙はその切り口を探るべく、さまざまな業種で防災・危機管理に携わる女性の匿名座談会を実施。災害備蓄の課題と改善点を中心に語り合った内容を、人への寄り添いの第一歩としてお届けします。
2024/11/05




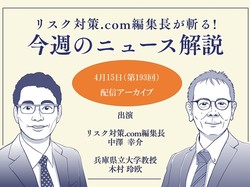












![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)





