2021/07/08
レジリエントな街づくりを支えるデジタル活用
今回の熱海市の土石流災害では、仮に住民の住所情報(ハザードマップ上の危険エリア)に基づくパーソナライズ情報が実現していたとしても、避難が必要な全ての人に情報を届けることについては課題も浮かび上がりました。その背景として、私たちは、必ずしも住民基本台帳に登録された住所に住んでいるとは限らない、という実態があります。別荘利用や多拠点生活などで、住民票が熱海市の当該地域に登録されていなかったとしても、住んでいる人がいる可能性があるということです。この逆もしかりです。
今回の土石流災害では、行方不明者の特定が極めて困難となっています。行方不明者の特定が困難なのは今回の災害に限ったことではありませんが、通常であれば避難所で避難者名簿が作られて、その名簿を起点に自治体による安否確認が進みます。今回は事前避難がほぼ行われていなかったことから、熱海市では安否不明者の氏名を公開して、家族・親戚・友人・近隣の人々からの情報提供を広く呼び掛けることにしました。このような個人情報(氏名)の公開は、2011年の東日本大震災の際にも避難所単位で行われていました。
各自治体では個人情報保護条例に基づき、災害などの有事の際には本人の同意なく個人情報の取り扱いを決めることができます(このような条例は自治体ごとに決められているため、今後全国で統一化される方向です)。今回の熱海市での氏名公開の結果として、「自分は無事である」「公開されている氏名の中に名前がないが、友人の〇〇さんと連絡がとれない」といった情報提供があり、安否不明者の特定につながっています。今回は土石流の範囲が限定的だったため、このような措置が可能だったと考えられますが、被害が広範囲にわたり、対象者が数百人、数千人となった場合には非現実的な方法となるため、やはり何らかの形でデジタル活用の模索が求められるところです。
個々人の住所情報に基づかない形でパーソナライズされた災害情報を実現しようとすると、考えられる選択肢は個人の位置情報の活用です。しかしながら、第3回でご紹介したように、現在のところデジタルサービスの提供における位置情報の活用には抵抗感を感じる人が多いのが実情です。やはり抵抗感の少ない住所や年齢情報からサービスの提供を始めていくほかないだろうと思います。
次回は、前回までの連載の流れに戻り、パーソナライズサービスへのニーズに影響を及ぼす「近隣住民とのつながりやコミュニティーづくり、助け合いによる充実感」について深堀りしたいと思います。
最後に少し宣伝をさせてください。以前本サイトで連載させていただいた「ロックフェラー財団100RCに見る街づくりのポイント」の内容を盛り込んだ書籍「世界のSDGs都市戦略: デジタル活用による価値創造」が2021年7月25日に刊行されます(https://www.amazon.co.jp/dp/4761527838?tag=hanmotocom-22&linkCode=ogi&th=1&psc=1&language=ja_JP)。レジリエンスの観点からSDGsを捉え、システム思考、デザインサイエンス、デジタル活用のキーワードから、今後の街づくりや社会デザインを考察しています。本連載でご紹介している「文脈化」の考え方、災害対応との関連についても整理していますので、ご関心のある方はお手に取ってご覧いただければ幸いです。
レジリエントな街づくりを支えるデジタル活用の他の記事
- いざというときに備えた日ごろの意識改革
- 突然の災害に備えるためには日ごろの意識と行動改革が大切
- デジタルガバメントに関する住民ニーズ調査の結果
- 近隣コミュニティーとのつながり、暮らしの満足感がパーソナライズへのニーズを高める
- リアルタイム情報と緊急時に自分や家族に必要な情報提供に高いニーズ
おすすめ記事
-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2025/04/01
-

-

-

-

-

全社員が「リスクオーナー」リーダーに実践教育
エイブルホールディングス(東京都港区、平田竜史代表取締役社長)は、組織的なリスクマネジメント文化を育むために、土台となる組織風土の構築を進める。全役職員をリスクオーナーに位置づけてリスクマネジメントの自覚を高め、多彩な研修で役職に合致したレベルアップを目指す。
2025/03/18
-

ソリューションを提示しても経営には響かない
企業を取り巻くデジタルリスクはますます多様化。サイバー攻撃や内部からの情報漏えいのような従来型リスクが進展の様相を見せる一方で、生成 AI のような最新テクノロジーの登場や、国際政治の再編による世界的なパワーバランスの変動への対応が求められている。2025 年のデジタルリスク管理における重要ポイントはどこか。ガートナージャパンでセキュリティーとプライバシー領域の調査、分析を担当する礒田優一氏に聞いた。
2025/03/17
-

-

-

なぜ下請法の勧告が急増しているのか?公取委が注視する金型の無料保管と下請代金の減額
2024年度は下請法の勧告件数が17件と、直近10年で最多を昨年に続き更新している。急増しているのが金型の保管に関する勧告だ。大手ポンプメーカーの荏原製作所、自動車メーカーのトヨタや日産の子会社などへの勧告が相次いだ。また、家電量販店のビックカメラは支払代金の不当な減額で、出版ではKADOKAWAが買いたたきで勧告を受けた。なぜ、下請法による勧告が増えているのか。独占禁止法と下請法に詳しい日比谷総合法律事務所の多田敏明弁護士に聞いた。
2025/03/14
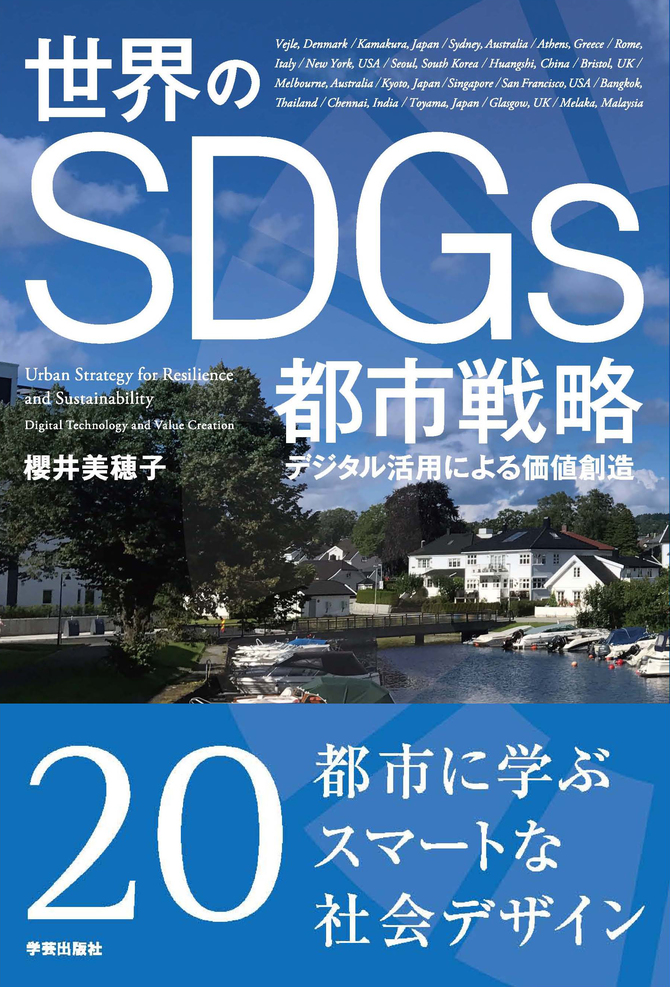






















![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)






※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方