2019/07/22
安心、それが最大の敵だ
内務技師青山士の改修計画

大正15年、鬼怒川改修計画が策定された。ここで内務省(国土交通省前身)主任技師青山士(あきら)が手掛けた鬼怒川改修工事計画の概要を見てみる。上流から下流までの総合的治水策である。
(1) <上流対策>堰堤(ダム)建設:最上流の栃木県塩谷郡三依村(みよりむら、現日光市)関門(地名)にロックフィル・ダムを建設する。(今の五十里ダム、ロックフィル・ダムは岩石を積上げて構築するダム)。
(2)<流域対策>河道改修:蛇行が甚だしく洪水の流下に支障のある宗道河岸付近については、これを解消するため新たに直線河道を開削することにする。この時、内務省土木局が鬼怒川改修工事の一環として計画したのが鎌庭捷水路(しょうすいろ、ショートカット)掘削工事である。鬼怒川右岸大形村(現下妻市千代川)大字鎌庭地先から下流に向かって短絡する直線コース・延長2050メートルの新しい河道を掘削し、従来の湾曲部の河道を2350メートルも短縮させる計画であった。ほぼ半分の距離に短縮させる一大工事で、上流や下流の流れに大きな影響をもたらす工事でもあった。
(3)<下流対策>遊水地築造:洪水調節のため、利根川本川沿いの千葉県田中村(現我孫子市)から我孫子町(同)にかけて田中遊水地を、また茨城県北相馬郡の菅生沼に遊水地をそれぞれ築造するものとする。
◇
政府の利根川改修計画に基づいた大事業が利根川本流の全流域に渡って進められていた。明治33年(1900)は、利根川近代改修史の出発点となった記念の年である。明治期の公共事業の中では最大級と言える利根川改修工事は、この年から開始される。欧米の最新機材や工法を導入した大規模工事は、利根川下流部からさかのぼる形で展開され、第一期は河口から千葉県佐原町(現香取市)まで、第二期は佐原町から茨城県取手町(現取手市)まで、第三期は取手町から群馬県芝根村(現玉村町)までであった。一大工事は、第一期改修工事着手以来、30年の歳月をかけて昭和5年(1930)に終了した。その間も利根川流域は大洪水に繰り返し見舞われた。
青山の直属の部下だった安芸晈一(あきこういち、内務技師、1902~85)は東京帝大土木工学科を卒業後、鬼怒川改修工事に配属された。安芸は追想する。
「その当時(大正末期)の鬼怒川改修工事の主任技師は青山士さんであった。青山さんは当時荒川上流の改修工事を担当し、鬼怒川は兼務ということで、月に十日ほどしかこちらに来られなかったのであるが、学校(帝大)を出たばかりの私には、川治(栃木県北部)での、それから鎌庭(茨城県下妻市千代川)、川島(現同県筑西市)での青山さんとの接触は何よりのものであった。青山さんは、私たちの本当の異色の先輩であった」。
「私はお会いする機会のあるごとに、パナマ運河のお話を伺った。せっかく渡米されたのではあるが、事情でパナマ運河の再開がしばらく遅れ、その間には鉄道会社に勤められて、測量に従事されたという。アメリカ人のポール持ちで、自分は測量器械をかついで後を追うのが大変だったとのこと。アメリカでは測量する人が自分で器械をかつぎ、自分で据付け、自分で読み取り、助手にノートさせるというのであった。パナマ運河の開削が再開されてからはそちらに移られ、初めのうちは測量班の班長としてしばらく天幕生活をされたそうであるが、班長は班員がとってきた野帳(やちょう)を夜通し整理して、これを翌朝班員に渡し、自分はそれから寝たのだと言われた。青山さんはその後、ただ一人の外国人技師としてガツン人造湖の築造には副技師長を勤めておられた。
そしてパナマから帰国されたのが明治の終わり頃であって、それから内務省に勤められることになり、荒川の放水路の開削に従事されてから、荒川上流改修工事の主任技師となられたのであった」。
「ある時、青山さんから鎌庭の捷水路のことで注意を受けたことがあった。青山さんの言われるのは、『川は上から下へ流れるのだ、途中に上下流との関係のない形の川がはいったのでは、いろいろな段階の流量が円滑に流れるとは思われない、掘削土量が少しくらいは増えてもよいから、そのところをもう少し考えたらどうだ』と言われたのであった。そこで私は、捷水路の上下流それぞれおよそ5キロの間からいくつかの断面をとり、これを重ね合わせて、その中から適当な断面の形を決め、これを計算でチェックして青山さんの承認を得たことがあった。私には、このわずかではあったが、親しく接触する機会を持つことができたのは何よりのことであった」(安芸晈一「わが師・わが友」の「川は流れている」)。
青山の鬼怒川治水策は戦後になってほぼ計画通り実現された。
- keyword
- 安心、それが最大の敵だ
- 鬼怒川
- 青山士
- 常総市
- 水害
安心、それが最大の敵だの他の記事
おすすめ記事
-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2025/04/01
-

-

-

-

-

全社員が「リスクオーナー」リーダーに実践教育
エイブルホールディングス(東京都港区、平田竜史代表取締役社長)は、組織的なリスクマネジメント文化を育むために、土台となる組織風土の構築を進める。全役職員をリスクオーナーに位置づけてリスクマネジメントの自覚を高め、多彩な研修で役職に合致したレベルアップを目指す。
2025/03/18
-

ソリューションを提示しても経営には響かない
企業を取り巻くデジタルリスクはますます多様化。サイバー攻撃や内部からの情報漏えいのような従来型リスクが進展の様相を見せる一方で、生成 AI のような最新テクノロジーの登場や、国際政治の再編による世界的なパワーバランスの変動への対応が求められている。2025 年のデジタルリスク管理における重要ポイントはどこか。ガートナージャパンでセキュリティーとプライバシー領域の調査、分析を担当する礒田優一氏に聞いた。
2025/03/17
-

-

-

なぜ下請法の勧告が急増しているのか?公取委が注視する金型の無料保管と下請代金の減額
2024年度は下請法の勧告件数が17件と、直近10年で最多を昨年に続き更新している。急増しているのが金型の保管に関する勧告だ。大手ポンプメーカーの荏原製作所、自動車メーカーのトヨタや日産の子会社などへの勧告が相次いだ。また、家電量販店のビックカメラは支払代金の不当な減額で、出版ではKADOKAWAが買いたたきで勧告を受けた。なぜ、下請法による勧告が増えているのか。独占禁止法と下請法に詳しい日比谷総合法律事務所の多田敏明弁護士に聞いた。
2025/03/14










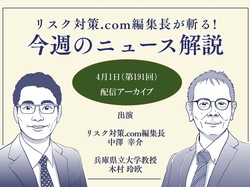













![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)






※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方