教育・ハウツー
-

テレワークで使用するパソコンなどのサイバーセキュリティーに注意!(2)
前回に引き続き、テレワークで勤務する際のサイバーセキュリティ対策上の注意点を記します。
2020/04/08
-

生きる――新型コロナウイルスとの戦い
統計によると、日本時間の2020年4月1日夜時点で世界の新型コロナウイルス感染者は累計88万人超で、死者は約4万4000人と報道され(時事通信社)、さらに増え続けている。こうした感染症は歴史始まって以来初めてのことではない。過去にもさまざまな感染症を経験し、先人は幾多の悲しみを乗り越えてきた。
2020/04/06
-

3日間の「巣篭り生活」を実験してみたよ
「3日間の巣篭もり生活」を実験してみました。今ある食材だけで1日3食、普段通りの食事をどれだけ準備できるかという実験です。前々から備蓄の課題を確認したいと思っていましたし、もし「ロックダウン(都市封鎖)」になったらどう過ごすのかを考えることもできると思ったからです。パニックを起こさず、買い込みをせず、過ごしましょう。
2020/04/03
-

第27回:必要な人員の確保をはばむ要因と対策その2
BCPに規定していても、想定外の人員不足に悩まされるのが災害対応の現実だ。これに備えた代替要員の確保も、事前対応プランの一つにほかならない。人員不足にはパターンがあるが、とくに問題となるのは実際に現場の最前線で活動にあたる従業員の欠員。この実働・支援部隊をいかに現実的な線で確保するかは、スタッフ一人ひとりの顔と力量が見える配備体制をいかに実現するかにかかっている。
2020/04/02
-

高野豆腐とさば缶の簡単コクうま煮
今回も、常温で長持ちできる上に栄養価も高い「乾物」に注目してみたいと思います。乾物は手間のかかるイメージですが、実は簡単に食べられるんです! 今回注目する乾物は「高野豆腐」。最近はいろいろな形にカットされたものや小分けタイプもあり、より使いやすくなっていますので、ぜひつくってみてください。
2020/04/02
-

情報漏えい事故を再発させないために
顧客情報をはじめとした機密情報の漏えいは、多くの企業にとって重要なリスクであることから、ほとんどの企業では既に何がしかの対策は行っているはずです。しかしながら情報漏えいは全国で毎日のように発生しています。
2020/04/02
-

動き標章の「ピクトグラムアート」
ピクトグラムアートとは、時間の経過に伴う標章の変化の状態を示す2つ以上並べたピクトグラムからなる動き標章。動き商標と商標をベースにしたデジタルアート作品です。ピクトグラムアーティストの藤代洋行が絵コンテを作成し、デザイナーの石倉京氏が図形を組み合わせて作ったオリジナルのピクトグラムやJISなどのピクトグラムで静止画や動画の作品にしています。
2020/04/01
-

第16回:建物・設備などに関する被害の確認
前回は、大きな地震に見舞われた際、どのように従業員の被害、つまり安否確認を進めていくかについて説明しました。今回は、従業員と並んで企業にとって重要な経営資源である建物・設備などに関する被害の確認と、その後の対応について考えます。
2020/04/01
-

テレワークで使用するパソコンなどのサイバーセキュリティーに注意!(1)
テレワークでの勤務は、オフィスのサイバーセキュリティの環境とは異なり、勤務先のシステム等へ外部からアクセスしますので、マルウェア(ウイルス)への感染リスクが高まります。今回と次回の2回にわたり、テレワークで勤務する際のサイバーセキュリティ対策上の注意点を記します。
2020/03/31
-

複合災害があなたを狙っている
あなたは今、新型コロナウイルスという「生物災害」と必死に戦っていますが、地震や津波にも狙われていることをお忘れなく。例えば超大物の南海トラフ巨大地震、それに首都直下地震などです。2011年3月11日に体験した東日本大震災のような地震と津波の2つではなく、これからは新型コロナウイルスを加えた三つどもえの戦いになります。一刻も早く新型コロナウイルスへの対応を含めた防災・減災対策が求められます。
2020/03/30
-

世界に広がる新型コロナウイルス感染(2)
新型コロナウイルス感染では、発病した人がいったん回復した後に再発するケースが起きています。ウイルスの再感染か、あるいは完全に消滅し切らず体内に残っていたウイルスが再増殖する持続感染か。いずれの可能性も考えられますが、今回は後者について、前回同様、鳥類のコロナウイルス感染病の実験結果から考察します。
2020/03/25
-

第3回 海外子会社のリスク管理に本社が関与しない問題点とは?
事業リスクは国境をまたいで存在します。日本国内の保険手配をきちんと行っていても、海外子会社の保険手配は現地任せで本社がリスク管理に全く関与していない状況であれば、それは大きな問題につながりかねません。
2020/03/25
-

第26回:必要な人員の確保をはばむ要因と対策その1
「BCPはプラン通りには機能しない」。そう考える担当者が多い理由の一つが「実際の現場で必要な人員を確保できない」という問題が起こるためだ。なぜ、そうした問題が起こるのか。非常事態だからと割り切ることもできるが、その原因を知っているかいないかで対策のリアリティーは変わる。人員の招集がスムーズに進まない原因と解決のヒントを考えてみたい。
2020/03/19
-

コロナ会見にはいたわりや励ましの言葉が必要
新型コロナウイルスは、WHO(世界保健機関)にパンデミックとして認識され、世界的規模での危機に発展しました。社会全体の危機には、どのようなメッセージを心掛ける必要があるのか考えます。
2020/03/18
-

第15回:従業員の安否確認
首都直下地震や南海トラフ巨大地震で想定されている激しい揺れに見舞われた場合、最も重要なことは、自らの命を守ること。そしてその後は、従業員の安否確認や建物・設備の安全確認など、自社の被害状況を把握し、速やかな事業復旧につなげていくことが重要です。今回から、地震などの災害で重大な被害を被ったとき、どのように確認を進めていくべきかを説明します。
2020/03/18
-

新型コロナ対応としてもつながった日本と世界のマンガの絆
COVID-19がパンデミックに当たるというWHOの声明も発表され、今後やるべきことの数々に気が抜けない日々が続いています。私は災害時の乳幼児の栄養の在り方や支援について、OG-IFEという国際基準に基づいたマンガを作成して防災研修で配布したり、無料で公開していたのですが、このたび、このOG-IFEの作成団体であるENN(Emergency Nutrition Network)という国際機関のホームページで、私と仲間が作成したマンガが公式に掲載されることとなりました!
2020/03/13
-

人が受ける情報の8割は視覚
ピクトグラムは、背景と図に明度差のある2色を用いて、表したい概念を単純な図として表現する技法が用いられています。全盲(完全にものが見えない)、弱視(ものがはっきり見えない)に該当する視覚障害者や色覚異常、夜盲症、羞明、複視などの障害者手帳の交付対象ではありませんが、ものの見え方はさまざまあり、その見え方によってピクトグラムに限らず、日常生活も困っている方はいます。まずは「バリアフリー」と「ユニバーサルデザイン」の違いを知っていただく必要があります。
2020/03/13
-
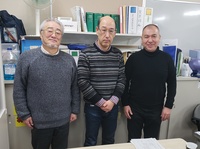
東日本大震災後の福祉支援
東日本大震災の発生から9年。今回は震災後の被災者支援について、宮城県気仙沼市保健福祉部高齢介護課の高橋義宏課長にヒアリングをさせていただいた内容を報告する。先進的に取り組んできた被災自治体の取り組みから学ぶべきことは多い。これまでの取り組みをパッケージ化、標準化し、次の災害での支援に活用できるようにすることが重要だ。
2020/03/11
-

「災害復興法学」のすすめ
「防災・減災を自分ごと」にしてほしいという願いからはじまった本連載も、今回が最終回となりました。被災者を支援する法律はあるのに、知られていない、利用しにくいなどの理由から十分な支援ができないケースは多々あります。ならば既存の法律や制度の改善が必要で、連載のベースとなった「災害復興法学」はそのための学問です。防災や復興においても「法律」「政策」が重要なファクターになることに興味を持っていただけたら本望です。
2020/03/11
-

【オンライン講座】企業の新型コロナウイルス対策
このオンライン講座では、2月中旬に実施した企業の新型コロナウイルス対策のアンケート結果を解説するとともに、そこから見えてきた課題と、今後考えておくべき対策のポイントについて解説します。
2020/03/11
-
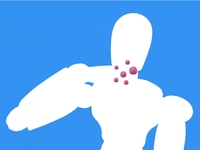
溶連菌感染症への備え
新型コロナウイルス(COVID-19)による感染症は毎日新しい情報が報告され、まだ確定した所見が多くないため、今回はあえて溶連菌感染症を取り上げます。症状として、冬から春は咽頭・扁桃炎が多くなるので注意が必要。適切な予防を心がけましょう。溶連菌には消毒剤が有効です。
2020/03/10
-

新型コロナ、片付け、トイペ騒動、そして備蓄
新型コロナウィルスの影響で、出演予定だったライブやイベントが中止になっています! ということで、こんな時でないとなかなかできない片付けをしているのですが、友人宅の片付けに訪れたら、やっぱりトイレットペーパー騒動に巻き込まれていました! なるほど、こんな時だから、常日頃の備蓄についてちょっくら再考するのもいいかもです!
2020/03/09
-

世界に広がる新型コロナウイルス感染
鳥インフルエンザの予定を変更し、新型コロナウイルスについての考察をお届けします。コロナウイルスは動物から人への感染が成立してから時間を経ていないため、人に感染したウイルスの動態が詳しく分かっていません。筆者は1970年代初めから鳥類のコロナウイルス感染による「鶏伝染性気管支炎(IB)」の研究に取り組んできました。COVID-19とは近縁ではありませんが、同じコロナウイルスであることから、興味深い共通点が見つかるはずです。
2020/03/06
-

新型コロナウイルス騒動で中国もBCPに着目!?
上海市では、日本からの入国者に14日間の経過観察を求める方針を日本総領事館に通知しました。感染の「拡大」抑制から「逆流」防止へ新たな対策がとられ始めたといえますが、旅行業や交通業などへの経済的影響は大きく、事業継続に関わる事態も。単なる騒動では済まされない状況に至り、中国でもBCP(事業継続計画)への関心が高まりそうです。
2020/03/06
-

第25回:災害時の帰宅または移動の留意点
大災害の発生時には、公共交通機関の停止や道路の寸断などにより大量の「帰宅困難者」が発生する。とくに大都市の企業においては、こうした帰宅困難者に対する備えは必須だ。内勤、外勤それぞれの社員に対する備え、訪問客に対する備え、そしてどうしても帰らなければならない場合への備えは、十分だろうか。
2020/03/05



















![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)





