2016/05/24
講演録
TIEMS日本支部第11回パブリックカンファレンス

化学工場事故等に備えた地域住民との
リスクコミュニケーション
横浜国立大学大学院環境情報研究院客員准教授
(独)製品評価技術基盤機構化学物質管理センター調査官 竹田宜人氏
本日は工場の化学物質管理におけるリスクコミュニケーション(以下、リスコミ)の現状について話したいと思います。まず、化学物質管理におけるリスクの構造を見てみますと、対象は工場などで使用している化学物質で、通常の操業で排出されるものと、災害による環境への化学物質の急激な排出、放出、漏えいです。リスクをこうむる人は周辺住民や環境。ステークホルダーは住民や行政(国、地方自治体、警察、消防、自衛隊など)と、事業者自身です。
さまざまな業界のリスコミも見てみたいと思います。化学物質のほかに食品安全、災害対策、土壌汚染、放射線対策などでリスコミが重視されています。化学物質のリスコミの目的を見ると、経済産業省は住民に対して「不安を小さくするため」としています。埼玉県庁は事業者に対して「事業活動を円滑に展開するために、地域と良好な関係を築き、共存していく」ためとし、それぞれの立場で異なることがわかります。食品安全では、「国民が、物事の決定に関係者として関わる公民権や民主主義の哲学・思想を反映したものである」としており、リスコミが民主主義に基づくものとされています。いろいろな視点でリスコミを語る方がいますが、対象が何のリスクなのか、目的を明確化しないと、やろうとしていることと、根拠とするリスコミの定義がミスマッチになります。例えば災害時には「公助、自助、共助を可能とするため、(中略)現実の災害時における被害低減を図る」としています。これは非常に分かりやすくて明確なリスコミの目的と言えます。
ここで注意してほしいのは、「リスコミは説得の技術ではない」ということです。以前に、私のところにとある会社の方が来られまして、リスコミついて教えてほしいというので繊維関係の化学工場にお連れしたところ、非常にがっかりされました。なぜかというと、リスコミは住民の方をあっという間に説得できる手法だと思っていたらしいのですが、そうではないということが分かったからです。見学した会社は明治時代から操業しており、設立当初からこれまで地域住民と長いコミュニケーションを続けている会社でした。事故の情報も全て出して話し合っているから、住民とうまくコミュニケーションがとれているのです。「来月までに何とかできるというものではありません」というお話をさせてもらったので、根気強く続けることの重要性に気が付かれたのだと思います。リスコミは説得の手段と勘違いされている方は多いですが、そうではないのです。
私たちが調査してきたリスコミの形態では、実にさまざまなものがありました。夏祭りやオープンファクトリーという形で地域に工場を開放する取り組みや、工場周辺の掃除や環境美化活動、防災訓練の地域との共同開催など、日常的にさまざまなコミュニケ―ションを工場は行っています。その際に、自社の環境対応に関する説明を同時行い、PRTR制度における化学物質の排出の話や省エネ対策の話をしている事業所が多く、このような場所でリスコミは成り立つのです。話題は、何でもいいと思います。環境保全の話でもいいし、防災の話でもいい。意外に話題に上るのが、社員のマナーの問題です。従業員が近くのコンビニエンスストアにたむろしていてマナーが悪いなどの苦情も住民の方から指摘され、カイゼンに役立てている企業も増えています。
最近では、工場を学校教育の場として活用するケースもあります。このようにいろいろなステークホルダーとさまざまなコミュニケーションをとっていることは、日本企業の良い事例なのです。リスコミと言うと、特別なことをしなくてはいけないと考えておられる方が多いのですが、日本企業は昔から周辺地域とのコミュニケーションについて、経験豊富なのです。そのなかに防災や環境保全などリスクへの対応に関する話を入れるだけで十分だと考えています。
講演録の他の記事
おすすめ記事
-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2025/04/22
-

帰宅困難者へ寄り添い安心を提供する
BCPを「非常時だけの取り組み」ととらえると、対策もコストも必要最小限になりがち。しかし「企業価値向上の取り組み」ととらえると、可能性は大きく広がります。西武鉄道は2025年度、災害直後に帰宅困難者・滞留者に駅のスペースを開放。立ち寄りサービスや一時待機場所を提供する「駅まちレジリエンス」プロジェクトを本格化します。
2025/04/21
-

-

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視
4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。
2025/04/15
-

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入
日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。
2025/04/15
-

-

生コン・アスファルト工場の早期再稼働を支援
能登半島地震では、初動や支援における道路の重要性が再認識されました。寸断箇所の啓開にあたる建設業者の尽力はもちろんですが、その後の応急復旧には補修資材が欠かせません。大手プラントメーカーの日工は2025年度、取引先の生コン・アスファルト工場が資材供給を継続するための支援強化に乗り出します。
2025/04/14
-

新任担当者でもすぐに対応できる「アクション・カード」の作り方
4月は人事異動が多く、新たにBCPや防災を担当する人が増える時期である。いざというときの初動を、新任担当者であっても、少しでも早く、そして正確に進められるようにするために、有効なツールとして注目されているのが「アクション・カード」だ。アクション・カードは、災害や緊急事態が発生した際に「誰が・何を・どの順番で行うか」を一覧化した小さなカード形式のツールで、近年では医療機関や行政、企業など幅広い組織で採用されている。
2025/04/12
-

-









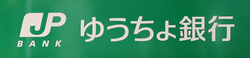














![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)






※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方