取引先からの厳しい要求は、企業間取引でのハラスメントに該当する可能性があります。法的には問題がありそうだとしても、重要な取引相手であればすぐに公的機関を頼るわけにもいきません。今回は、社内対応を含めた対策を紹介します。
■事例:下請けハラスメント
Aさんはある中小企業の営業担当として、長年にわたり大手企業X社との取引を担当しています。X社は業界でも有名な企業であり、Aさんの会社にとって売上の大部分を占める重要な取引先です。しかし、最近になってX社からの要求が次第にエスカレートし、Aさんは頭を抱えています。
ある時、X社の担当者より「この追加作業を無料で対応できないか?」と問い合わせがありました。Aさんは契約書を確認した上、「契約外の業務になりますので、追加費用が発生します」と伝えると、X社の担当者は露骨に顔をしかめて、こう言い放ちました。
「そんな細かいことを言わないでくださいよ。ウチは長年取引してきたんだから、少しぐらいサービスしてくれたっていいでしょう?」
本来であれば、契約外の業務を無償で引き受ける義務はありません。しかし、X社は暗に「対応しなければ今後の取引に影響する」と圧力をかけてきたようにも思えます。上司に相談すると、「とりあえずやれる範囲で対応しておけ」と言われるだけでした。
別のタイミングでは「納品スケジュールを前倒しできないだろうか? 他の取引先は柔軟に対応してくれてるんだけど」と取引条件の変更を一方的に押し付けてきました。Aさんは「申し訳ありませんが、生産ラインの都合上、急な前倒しは難しい」と答えたところ、X社の担当者は「そちらの事情は関係ない。ウチとしては必要なんだから、どうにかしてもらわないと困る」と言ってきました。
公正な取引関係が求められるはずの企業間取引で、一方的なスケジュール変更の強要は本来ありえません。しかし、X社は自社の影響力を背景に「他の企業なら受け入れるはず」と言わんばかりの態度を取ってきたのです。社内で協議したものの、「X社の要望には極力応えるしかない」という結論に着地しました。
以降も、X社の担当者は「何度言えば分かるんですか? 仕事が遅すぎるし、対応が悪すぎる!」と止まりません。
Aさんは毎回の打ち合わせが憂鬱になっていきました。ミスをしたわけでもないのに、何かと怒りの矛先を向けられるのです。これまでの要求を素直に受けなかったことが理由かもしれないとAさんは考えました。謝罪すると担当者から「やる気がないなら担当を代えてもらったほうがいいですね」とまで言われてしまいました。
ある日、Aさんはネットで「企業間ハラスメント」について検索すると、そこには、自分が今まさに直面している問題と同じような「取引先からの契約外業務の強要」「不当なスケジュール変更の強要」「パワハラ的な言動」の事例が並んでいました。
Aさんは深いため息をはきつつ、こう考えました。
「これはカスタマーハラスメントかもしれない。でも、上司は助けてくれないし、会社もX社との関係を何よりも優先している。公正取引委員会や行政機関に相談する手もあるかもしれないが、そんなことをしたら、取引を失う可能性が高い。仕事を続けるためには、X社の要求を飲むしかないのか。でも、それでは自分や会社の負担が増え続けるだけだ。どうしたらいいのだろう・・・」





















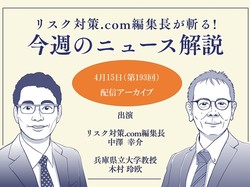













![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)






※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方