2019/03/11
安心、それが最大の敵だ
吉田茂の反軍思想
当事者である吉田茂の追想を聴こう。「回想十年 第一巻」吉田茂」から引用する(原文のママ)。
「<自由主義者の烙印>
戦前私は軍部から自由主義者、親英米派ということで睨まれたが、その折紙をいただいたのは、昭和11年(1936)、例の2・26事件直後に廣田内閣の出来る時である。私は本来政治向きのことは好きではなかったし、従って関係したこともなかったのだが、この時は、貴族院議長だった近衛文麿公に依頼され、後継総理の候補として廣田弘毅君の引出しの使者に立った。そして私は廣田君に出馬を勧めた行懸りから、組閣本部に入って閣僚銓衡(せんこう)の相談に参画することとなったが、その関係で私も外務大臣候補として挙げられていたようだ」。
「ところで閣僚候補の顔触れがやっと出揃った翌日、陸軍大臣の候補として軍部が推薦していた寺内寿一大将が山下奉文少将(後の大将)を始め陸軍省の幕僚数名を引き連れ、当時外相官邸だった組閣本部に乗り込んできて、『新聞に出ている閣僚候補の顔触れなるものを見ると、現時局に好ましくない人物の名前が見えるが、そのような人物の入閣には、陸軍は飽くまで反対する』と申し入れてきた。軍の反対する人物の一人が私であることは明らかだったので、私は組閣の手伝いから直ちに手を引いた。結局、司法大臣候補の小原直、文部大臣の下村宏、それに私との3人が、自由主義者とか親英米派とかいう理由で、軍部から忌避されていたことが後でわかった」。
「<駐英大使としてロンドンへ>
廣田内閣への入閣に落第した義理合いからであろう、廣田総理の推薦で同年4月私は駐英大使としてロンドンに赴任することとなった。当時の世界情勢は、ドイツではヒットラーの率いるナチの勢いが漸く最盛期に入らんとしており、欧州の勢力分野も、いわゆる独伊枢軸と英仏側の対立が漸く濃厚ならんとしていた。またわが国内情勢は例の2・26事件の直後であり、陸軍は粛軍とは名のみで、実際には社会不安や国民の恐怖的心理につけ込んで、極端な国家主義者や対外膨張論者を利用し、国際的には枢軸側に加担して、反英仏、ひいては反米的色彩をますます鮮明にしてきた時代であった」。
「<説得にきた駐在武官>
その頃わが国では独伊との防共協定に加盟することの可否が問題となり、政府も陸軍の勢力に押されて、協定締結に肚を決めていたようである。ところがそれについて一応在外大公使の意見を徴することとなったらしく、私のところへも賛否の意見を問い合わせてきた。そこで私は防共協定には反対だと返事してやった。その後も辰巳栄一駐英、大島浩駐独の両陸軍武官がやってきて私を説得にかかったが、私はどうしても自分の所信を枉げる気にはなれなかった。私が防共協定に反対したわけは、軍部の言い分では、これは単なる反共というイデオロギーの問題に過ぎないというのであるが、それは全く表向きの言葉で、肚のうちは、独伊と結んで英仏、ひいてはアメリカ側に対抗しようとしたものであることは明らかで、結局この枢軸側への加担は遠からず政治的、軍事的なものにまで発展するに決まっており、その勢いの赴くところ、わが国の将来にとってまことに憂うべきものとなることが、私には感得されたからである」。
「しかし、こうした私の心配や反対などにはお構いなく、ドイツとの防共協定は成立し、ついでイタリ―(イタリア)も加わり、更に協定が強化されて、後には軍事同盟にまで発展したことは、周知の通りである。それはともかくとして、そうした頑固な反対をしたため、私はいよいよ以て反軍思想の持主という烙印を軍部から捺されたらしい」。
安倍内閣の麻生太郎・財務相は、自由主義者・「ワンマン首相」吉田茂の孫である。
参考文献:「日本憲兵正史」(全国憲友会連合会本部刊行)、「回想十年 第一巻」(吉田茂、新潮社)、筑波大学附属図書館文献。
(つづく)
- keyword
- 安心、それが最大の敵だ
- 吉田茂
- 太平洋戦争
安心、それが最大の敵だの他の記事
おすすめ記事
-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2025/04/01
-

-

-

-

-

全社員が「リスクオーナー」リーダーに実践教育
エイブルホールディングス(東京都港区、平田竜史代表取締役社長)は、組織的なリスクマネジメント文化を育むために、土台となる組織風土の構築を進める。全役職員をリスクオーナーに位置づけてリスクマネジメントの自覚を高め、多彩な研修で役職に合致したレベルアップを目指す。
2025/03/18
-

ソリューションを提示しても経営には響かない
企業を取り巻くデジタルリスクはますます多様化。サイバー攻撃や内部からの情報漏えいのような従来型リスクが進展の様相を見せる一方で、生成 AI のような最新テクノロジーの登場や、国際政治の再編による世界的なパワーバランスの変動への対応が求められている。2025 年のデジタルリスク管理における重要ポイントはどこか。ガートナージャパンでセキュリティーとプライバシー領域の調査、分析を担当する礒田優一氏に聞いた。
2025/03/17
-

-

-

なぜ下請法の勧告が急増しているのか?公取委が注視する金型の無料保管と下請代金の減額
2024年度は下請法の勧告件数が17件と、直近10年で最多を昨年に続き更新している。急増しているのが金型の保管に関する勧告だ。大手ポンプメーカーの荏原製作所、自動車メーカーのトヨタや日産の子会社などへの勧告が相次いだ。また、家電量販店のビックカメラは支払代金の不当な減額で、出版ではKADOKAWAが買いたたきで勧告を受けた。なぜ、下請法による勧告が増えているのか。独占禁止法と下請法に詳しい日比谷総合法律事務所の多田敏明弁護士に聞いた。
2025/03/14









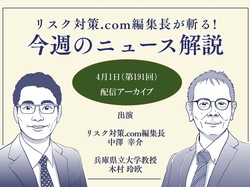













![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)






※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方