2025/03/04
防災・危機管理ニュース
発生7日目も延焼が続き、平成以降最大規模となった岩手県大船渡市の山林火災。専門家は、断続的に吹き続けた風や険しい地形、乾燥した腐葉土が拡大の一因とみている。
同市では火災が発生した2月26日に最大瞬間風速18.1メートルを観測し、その後も強風が吹き続けた。山林火災に詳しい東北大流体科学研究所のサミュエル・マンチェロ客員教授は「強風下では数キロ先の建物や森林に飛び火するため、消火を難しくしている」と説明。乾燥した山の腐葉土も延焼の一因とみており、「枝や葉が細かく積み重なり、着火しやすい」と分析する。
三陸地方沿岸は急斜面が続く地形になっている。森林総合研究所(茨城県つくば市)の玉井幸治研究ディレクターは「風や地形が延焼速度に与える影響は大きい」と指摘。シミュレーションでは風速2メートルの時に比べ、延焼速度が風速6メートルで約10倍、8メートルで約20倍になった。また、平たんな森林に比べ、傾斜30度の森林では約1.5倍、40度では約2倍になったという。
〔写真説明〕山林火災現場に放水する陸上自衛隊のヘリ=2月28日、岩手県大船渡市(防衛省提供・AFP時事)
(ニュース提供元:時事通信社)

防災・危機管理ニュースの他の記事
おすすめ記事
-

-

-

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2025/03/25
-

-

全社員が「リスクオーナー」リーダーに実践教育
エイブルホールディングス(東京都港区、平田竜史代表取締役社長)は、組織的なリスクマネジメント文化を育むために、土台となる組織風土の構築を進める。全役職員をリスクオーナーに位置づけてリスクマネジメントの自覚を高め、多彩な研修で役職に合致したレベルアップを目指す。
2025/03/18
-

ソリューションを提示しても経営には響かない
企業を取り巻くデジタルリスクはますます多様化。サイバー攻撃や内部からの情報漏えいのような従来型リスクが進展の様相を見せる一方で、生成 AI のような最新テクノロジーの登場や、国際政治の再編による世界的なパワーバランスの変動への対応が求められている。2025 年のデジタルリスク管理における重要ポイントはどこか。ガートナージャパンでセキュリティーとプライバシー領域の調査、分析を担当する礒田優一氏に聞いた。
2025/03/17
-

-

-

なぜ下請法の勧告が急増しているのか?公取委が注視する金型の無料保管と下請代金の減額
2024年度は下請法の勧告件数が17件と、直近10年で最多を昨年に続き更新している。急増しているのが金型の保管に関する勧告だ。大手ポンプメーカーの荏原製作所、自動車メーカーのトヨタや日産の子会社などへの勧告が相次いだ。また、家電量販店のビックカメラは支払代金の不当な減額で、出版ではKADOKAWAが買いたたきで勧告を受けた。なぜ、下請法による勧告が増えているのか。独占禁止法と下請法に詳しい日比谷総合法律事務所の多田敏明弁護士に聞いた。
2025/03/14













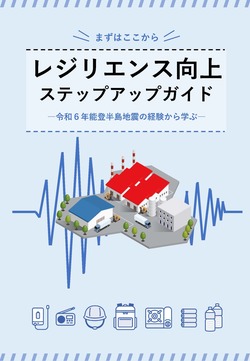










![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)






※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方