BCP事例
-

「買い物客」守る初動マニュアル 訓練で実効性担保
東北地方を代表する老舗百貨店の藤崎(仙台市青葉区、藤﨑三郎助社長)は3.11を機にBCPを策定。災害時の基本方針とワークフローを明確化するとともに以前から行っていた防災訓練を充実、各地の小規模店舗も網羅しながら初動にかかる従業員の練度を高めている。また、早期復旧と地域支援を事業継続方針に掲げ、百貨店が地域に果たす役割を問い直しつつ、取引先や顧客との新しいつながりを模索する。
2021/03/07
-

改良を積み重ねたサプライチェーン管理手法
東日本大震災では、部品供給網の寸断が大きな課題となった。その後も、災害がある度にサプライチェーン問題が顕在化している。製品に使われる部品そのものが複雑になっていることに加え、気候変動などに伴う異常気象が追い打ちをかける。日産自動車では、東日本大震災前からの継続的なBCPの取り組みと、過去の災害検証を生かしたサプライチェーン管理の仕組みにより、災害対策に手ごたえを感じ始めている。コーポレートサービス統括部担当部長の山梨慶太氏に聞いた。
2021/03/07
-
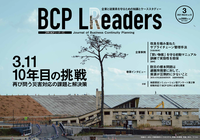
3.1110年目の挑戦
日本社会とそこに生きる企業にさまざまな課題を投げかけた東日本大震災。果たして、それらの課題は解決をみたのでしょうか、またその解決は時代の変化に耐え得るのでしょうか。奇しくもコロナ禍に見舞われている10年後のいま、企業は再び危機対応について考える機会を得ています。月刊BCPリーダーズ3月号は、企業や専門家への取材を通じ、災害対応の現在を切り取ります。
2021/03/01
-

行政としての新型コロナ対策~過疎地で実施した危機管理から学べること~
4月の危機管理塾は、「行政としての新型コロナ対策~過疎地で実施した危機管理から学べること~」をテーマに開催します。講師は、元航空自衛隊1佐で、現石川県奥能登広域圏事務組合の危機管理官の佐藤令氏です。
2021/02/24
-

福島沖地震×コロナ禍で組織はどう動いたか?
リモートワーク下での組織の危機管理、事業継続のあり方について、参加者同士の意見交換会を開催します。
2021/02/15
-

「組織と人を守る」活動をCSR視点で舵取り
危機管理やBCPは、不測の事態から組織と人を守るとともに、社会貢献を目指すものでもある。30社超の事業会社から成る物流サービスのSBSグループは、持株会社のSBSホールディングスを中心に、重点的に取り組む経営リスクとその対策をCSR 視点でコントロール。特色の違う企業の集団が一丸となってリスクマネジメントを推進し、業界全体の信頼向上に向かっていけるよう舵取りする。
2021/02/10
-

東日本大震災から10年 地域防災力は高まったか「医療と防災のヒトづくり・モノづくりプロジェクト」の実践から
今年3月11日は東日本大震災から10年の節目。3月の危機管理塾は、被災の教訓を胸に「災害に強い社会づくり」に全力で取り組む北良株式会社の笠井健社長を講師にお迎えし、同社の「医療と防災のヒトづくり・モノづくりプロジェクト」についてご講演をいただきます。
2021/02/08
-
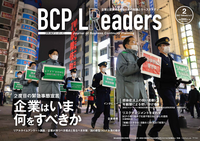
企業はいま何をすべきか
2度目の緊急事態宣言後も新型コロナの感染者数、重症者数は高い水準で推移。医療がひっ迫する一方で経済も疲弊、飲食業界を筆頭に影響が深刻化し、先の見えない状況に社会全体が不安を募らせています。いま企業はどう動いているのか、持つべき視点と取り組むべき対策は何か、国のコロナ対策は今後どうなるのか、アンケートとインタビューでひも解きます。
2021/02/01
-

BCPの取り組みで社員や取引先に安心を提供
マネジメントシステム(BCMS)の国際規格ISO22301の認証を取得した中小企業の白謙蒲鉾店。人命第一の防災を最優先に、地震災害だけでなく、ゲリラ豪雨、感染症、事故、テロなどさまざまな事象まで想定し、年間50回を超える演習を行い、危機管理力を高めている。食品製造会社である同社がなぜ、これほど危機管理にこだわり続けるのか、どのように社員のモチベーションを高めているのか。そこからは、BCPを組織に定着させるヒントを垣間見ることができる。同社のBCM推進責任者の白出雄太常務取締役に聞いた。
2021/02/01
-

地域支えるモノづくり、「災害弱者」へまなざし深く
東日本大震災の被災を教訓に「医療と防災のヒトづくり・モノづくりプロジェクト」を推進する北良株式会社(岩手県北上市、笠井健社長)は、人材開発と技術開発を両輪に「災害に強い社会づくり」を本気で目指すプロジェクトを推進。その取り組みは確実に成果を上げ、社内に防災文化を築くとともに、事業活動を通じて地域へ、全国へとその波紋を広げています。「技術開発」にスポットをあてて取材しました。
2021/01/25
-

津波による壊滅的被害から10年
宮城県名取市で、津波により工場が壊滅的な被害に遭いながらも、被災1週間後から事業を再開させた廃油リサイクル業者のオイルプラントナトリを訪ねた。同社は、東日本大震災の直前2011年1月にBCPを策定した。津波被害は想定していなかったものの、工場にいた武田洋一社長と星野豊常務の適切な指示により全員が即座に避難し、一人も犠牲者を出さなかった。震災から約1週間後には自社の復旧作業に取り掛かり、あらかじめ決めていたBCPに基づき優先業務を復旧させた。現在のBCPへの取り組みを星野常務に聞いた。
2021/01/21
-

新型コロナ対策の法的背景と企業に求められる対応~特措法の策定・改定の背景を振り返り、今後の対応を考える~
2月の危機管理塾は、「新型コロナ対策の法的背景と企業に求められる対応~特措法の策定・改定の背景を振り返り、今後の対応を考える~」をテーマに開催します。講師は、株式会社三菱総合研究所 ヘルスケア・ウェルネス本部 主任研究員(厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策本部参与、元・内閣官房新型インフルエンザ等対策室内閣参事官)の平川幸子氏です。
2021/01/20
-

風水害対応訓練シナリオづくり基礎講座
今回のレクチャーでは、風水害の訓練についてどのように行えばいいのか、何から考えていけば良いのか分からない担当者向けに説明します。
2021/01/05
-
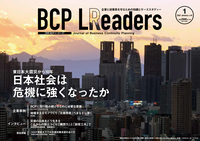
日本社会は危機に強くなったか
東日本大震災から10年経とうとしているいま、日本は再び新型コロナウイルスという危機にあえいでいます。この10年で、社会は強くなったのか。いつか必ず起きる大規模災害をめぐり、政治・行政システムや産業構造、技術環境、市民の生活や仕事は進歩したのでしょうか。インタビューや事例取材を通じ、現在の防災・危機管理の課題を考察します。
2021/01/04
-

今年のリスク対策~参加者同士の意見交換会~
「今年のリスク対策」をテーマに、参加者同士の意見交換会を開催します。
2020/12/16
-

ボランティアの可能性~被災地におけるボランティアの役割と現場で生じている課題~
1月の危機管理塾は、「ボランティアの可能性」をテーマに、 元トヨタ自動車株式会社トヨタボランティアセンター長・愛知県社会福祉協議会災害対応支援部会長の鈴木盈宏氏よりご講演をいただきます。
2020/12/16
-

水害リスクの高い土地 事業再開焦らずビジョン再考
幼稚園・保育園を中心に全国500カ所の施設で給食サービスを提供する株式会社ミールケア(長野県長野市)は、昨年10月の台風19号で本社を含む拠点施設が浸水、復興に向けて歩を進めていたところに新型コロナウイルスが襲いました。関幸博社長が2つの災害から受け止めたメッセージは「変化」。社会貢献の視点から企業ビジョンを再構築して被災施設の再生にあたるとともに、経営理念をさらに浸透させて実践につなげようと決意をあらたにします。
2020/12/15
-

理想の会社へ 社員一丸でまわすリスクマネジメント
印刷会社の株式会社マルワ(名古屋市天白区)は、事業継続にかかるリスクをISO、ISMS、BCPなどの指標と 手法を使って洗い出し、解決に向けた取り組みの一つ一つをSDGsのゴールに照らしてセルフチェック、自社の目指す姿を達成するために必要なESG活動として毎年の経営計画に落とし込んでいます。それをまわしているのは、社員全員の実践と協力にほかなりません。
2020/12/11
-
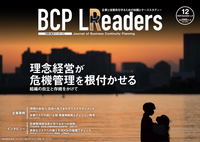
理念経営が危機管理を根付かせる
BCPの実効性を確保するには、日頃から経営基盤の可視化に努めなければなりません。ふと気が付くと必要な活動や連携ができない、そんな状況に追い込まれないように注意しましょう。そのためには、組織の自立に向けた太い価値軸を関係者全員が共有し、選択基準や行動規範として根付かせていくことが必要です。月刊BCPリーダーズ12月号は、自らの目指す姿に危機管理の取り組みを落とし込み、実践につなげている企業を紹介します。
2020/12/01
-

BCPの策定と、実効性を高めることの違い「組織におけるBCPの取り組みに関する調査」結果解説セミナー
12月9日(水)16時から、「組織におけるBCPの取り組み状況に関する調査」結果解説セミナーを開催します。参加費は無料です。是非ご参加ください。
2020/11/30
-

「組織における風水害対策調査」結果解説セミナー
11月17日(火)16時30分から、組織における風水害対策のアンケート調査結果に関する解説セミナーを開催します。参加費は無料です。是非ご参加ください。
2020/11/09
-

危機を検証し改善につなげる
いまだコロナ禍から脱し切れず、不安の影が先行きを覆う日本社会。しかし、環境変化を好機ととらえ、BCP体制やビジネス基盤の強化に乗り出す企業もあります。社員と危機意識を共有し、リスク対策を深化させながら、社会貢献と事業継続とを重ねていく。月刊BCPリーダーズ10月号は、そうした取り組みにスポットをあてました。
2020/11/02
-

過去の災害とコロナの教訓を未来の防災に生かす
今回の危機管理塾は、「過去の災害とコロナの教訓を未来の防災に生かす」をテーマに、熊本県益城町危機管理監の今石佳太様よりご講演をいただきます。
2020/11/02
-

オール ハザードアプローチが機能
「オールハザードアプローチ」――災害の種類や規模を問わず、あらゆるハザード(危険)に対して、柔軟に対応できるようにする考え方をこう呼ぶ。東急グループでは、東日本大震災以降、オールハザードに対応できるBCP構築を目指して活動している。事態への対応に必要となる人、物、金、そして情報を、状況に応じて活用し、主要事業を守り抜く。この手法により、ビル清掃や設備のメンテナンスなどビルの管理運営業務などを手がける東急ファシリティサービスでは、緊急事態宣言下でも、感染予防を徹底させながら従業員を安全に作業に当たらせ、顧客サービスの維持に努めている。同社のこれまでの取り組みを聞いた。
2020/10/31
-

新型インフルの教訓を生かし迅速に対応
2009年のH1N1新型インフルエンザ以降、徹底した感染症対策に取り組んできたことで、マスク不足や消毒液不足などの大きな課題もなく事業継続をしている企業がある。半導体加工装置を製造するディスコだ。5Gへの対応で例年より需要が高まっている半導体業界とあって、工場はコロナ禍でもフル稼働状態。従業員数は国内だけで4000人以上いるが、10月中旬時点でいまだ感染者はゼロ。広島事業所では公共交通機関を使わない通勤体制を実現するため、3月からそれまで工場間移動で使っていたマイクロバスを朝夕の社員の送迎に利用し、7月には東京〜広島間の移動手段として1800万円を投じて大型バスまで購入した。同社の感染症対策を取材した。
2020/10/31

















![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)





