2025/01/21
危機管理ポッドキャスト「日本における人道支援のリスク」
支援団体のBCP
ジョエル:企業は災害後の事業継続計画(BCP)を持っていますが、フードバンクや慈善団体、NGOのような小規模組織は、リソースや体制が不足していて同様の計画を実行できないことが多いのではないでしょうか?
チャールズ:そうですね、まさにその通りです。長年フードバンクを運営してきた私自身も、正式なBCPを持っていませんでした。しかし、献身的なチームがいて、私を含めて問題解決に積極的に取り組む姿勢がありました。スタッフやボランティアを迅速に呼び集め、東北へ向かったり、他の地域の状況を確認することができました。とはいえ、組織が行動を躊躇する理由として、何かにコミットする責任感を感じてしまう場合があります。しかし、状況を評価した結果、「これは赤十字や自衛隊が対応しているから必要ない」「自分たちの能力を超えている」と判断することも重要です。そのような判断を支持するための評価書が必要です。
ジョエル:「どうやって活動に参加するか」ではなく、「どの具体的なニーズに応えるのか」を考えるべきということですね。例えば、温かい食事を提供するのか、それとも主食を配布するのか。
チャールズ:その通りです。時には「何もしないよりは良い」という考えがあるかもしれませんが、私は「何もしない方が良い場合もある」と言いたいです。
ニーズと支援のミスマッチング
ジョエル:例えば、東北の災害時に、現地のニーズと提供された支援が一致しなかった事例はありますか?
チャールズ:あります。ある企業から、アメリカ産の缶詰の桃を詰めた40フィートコンテナ6個分を提供されたことがありました。それをコミュニティに提供しようとしましたが、断られました。結局、そのうち4つのコンテナをフィリピンに送ることになりました。当時は「なぜ桃が受け入れられないのか」と困惑しましたが、今では理解しています。災害発生から3か月も経つと、支援は「プル」フェーズに移行すべきでした。つまり、被災者が本当に必要としているものを提供するべきだったのです。
ジョエル:その経験が、資源管理についての考え方を変えるきっかけになったのでしょうか?
チャールズ:残念ながら、当時は狭い視点のままでした。その後、より効果的なシステムについて学び、自分の考えを改めました。被災者の声を聞くべきという考え方がありますが、問題は、その声が実際には地域の代表者やゲートキーパー(情報や資源の管理者)である場合があることです。ゲートキーパーが「必要ない」と言っても、実際の被災者、つまり家庭の人々は異なる意見を持つことがあります。
ジョエル:場合によっては、ゲートキーパーが地元の組織として独自の方法で災害対応を行っている中で、外部の組織が関与することに対して慎重になることもあるのでしょうか?ゲートキーピングの背後にある仕組みや、関係者の考え方を教えてください。
チャールズ:初期のフードバンク運営の中で、住宅を提供する支援団体と協力したときのことを思い出します。この団体は、住居を見つける支援を行っていました。そして、家電をリサイクルする別の団体と連携し、政府から支給される25,000円を使って基本的な家電セットを提供していました。素晴らしい協力体制でした。そこで私は、家電セットに加えて食料を詰めた箱を「新生活応援ギフト」として提供したいと提案しました。しかし、最終的にその団体から返ってきた答えは「そういう形の支援は信じていません」というものでした。ここで重要なのは、食料を拒否したのは個人ではなく、その団体が自分たちの理念に基づいて判断したということです。このようなゲートキーピングの事例は、実際には非常に多く見られます。
ジョエル:興味深いですね。
チャールズ:イデオロギーが背景にあることが多いのです。東北でも、桃の缶詰を断られた際、同じような状況だと感じ、苛立ちを覚えました。しかし、現在の「プル」モデルの考え方では、現地のコミュニティに直接意見を聞くことをスタッフに指示したでしょう。ゲートキーパーが「いらない」と言ったとしても、それを尊重しながらも、コミュニティそのものからのフィードバックを確認する必要があります。これは、良好な関係と信頼を築くことが重要だという意味でもあります。
ジョエル:桃の缶詰が拒否されたのは災害発生から約3か月後のことだったとおっしゃいましたが、時間の経過とともにニーズが進化していくということですね?
チャールズ:その通りです。
危機管理ポッドキャスト「日本における人道支援のリスク」の他の記事
- 必要な資源を必要なタイミングで必要な人々に届ける
- 東日本大震災での支援におけるリスク
おすすめ記事
-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2025/04/22
-

帰宅困難者へ寄り添い安心を提供する
BCPを「非常時だけの取り組み」ととらえると、対策もコストも必要最小限になりがち。しかし「企業価値向上の取り組み」ととらえると、可能性は大きく広がります。西武鉄道は2025年度、災害直後に帰宅困難者・滞留者に駅のスペースを開放。立ち寄りサービスや一時待機場所を提供する「駅まちレジリエンス」プロジェクトを本格化します。
2025/04/21
-

-

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視
4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。
2025/04/15
-

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入
日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。
2025/04/15
-

-

生コン・アスファルト工場の早期再稼働を支援
能登半島地震では、初動や支援における道路の重要性が再認識されました。寸断箇所の啓開にあたる建設業者の尽力はもちろんですが、その後の応急復旧には補修資材が欠かせません。大手プラントメーカーの日工は2025年度、取引先の生コン・アスファルト工場が資材供給を継続するための支援強化に乗り出します。
2025/04/14
-

新任担当者でもすぐに対応できる「アクション・カード」の作り方
4月は人事異動が多く、新たにBCPや防災を担当する人が増える時期である。いざというときの初動を、新任担当者であっても、少しでも早く、そして正確に進められるようにするために、有効なツールとして注目されているのが「アクション・カード」だ。アクション・カードは、災害や緊急事態が発生した際に「誰が・何を・どの順番で行うか」を一覧化した小さなカード形式のツールで、近年では医療機関や行政、企業など幅広い組織で採用されている。
2025/04/12
-

-









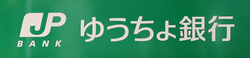














![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)






※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方