2017/12/18
安心、それが最大の敵だ

県令三島との巡り合い
三島は薩摩閥の雄・大久保利通の懐刀とも呼ばれた政治家である。東北地方の民権派を抑えて明治新政府の中央集権化を推進するという政府方針を受けて、まず酒田県令として赴任し、その後山形県令、福島県令、栃木県令兼任と東北各県の県令を歴任する間に、山形・福島・栃木の3県にまたがる新道開発や関連の架橋工事をはじめとする土木事業を休む間もなく行っていった。「山形・福島・栃木と帝都東京を道路で結べ!」と叫び、「土木県令」とあだ名されたが、必ずしも否定的な誇称ではなかった。福島県に着任早々、会津三方道路の建設を指示し、建設反対の地元政治家河野広中ら福島自由党を徹底的に弾圧した(福島事件)。
有無を言わさぬ公共事業の推進によって三島は「鬼県令」と非難され憎まれた。三島の評価は地元では今日も必ずしも芳しくない。だが、それこそが明日の東北をつくる社会基盤整備であると信じた三島は疑うことなく突き進み、同時に自ら指示する事業の成果を絵画に託して後世に残そうとしたのである。
◇
由一の東北風景画の代表作の一つに、新建築が立ち並ぶ山形市街のモダンな光景を描いた作品『山形市街図』がある。三島は自らが手がけた新しい地方都市の姿を由一に命じて描かせたのである。三島の発案で造られた主要な西洋建築(県庁、警察本部、師範学校など)が大通りの両側に肩を並べている。油絵による記録性が存分に発揮されている。
三島から再度東北地方の風景を描くように要請されたのは、明治17年(1884)のことである。福島・栃木両県の県令を兼ねていた三島は、東北全域にわたる新道開発の事業を記録し、記念に残すために由一を指名した。栃木・福島・山形・宮城の各県内に造られた道、橋、トンネル、建造物などをつぶさに取材して100図を石版画にして50部を政府に納めるとの一大計画であった。その後三島は内務省土木局長を経て警視総監に就任する。由一は新都東京をシリーズで描く「東京市街直写願」を三島に提案したが、受け入れられなかった。中央政界に返り咲いた三島には、洋画の政治的利用はもはや意味がなくなったのであろう。
警視総監・三島通庸は激務がたたって病に倒れ、栃木県塩原の別荘で保養しようと、景勝の温泉地で秋を観賞した。が、回復の兆しは見られず、東京の警視総監邸に戻って養生に努めた。治療もかなわず明治21年(1888)10月23日、不帰の人となった。享年52歳。「彼の熱心は凡人の及ばざる神力というてよし」(原文のママ)。高橋由一の「三島論」である。論じる高橋もまた「熱心」の人であった。言論界の重鎮徳富蘇峰は「三島通庸は6尺の身をもってよく明治の長城たり」とその業績を讃えた
由一の東北地方との関係はその後も続いた。明治20年(1887)から翌年にかけて再び山形を旅し、地元の富豪たちの肖像画を描いている。厳しい風雪に堪えて生きる東北人への愛情をにじませた作品も少なくないのである。明治27年(1894)7月6日、由一は67歳5カ月の生涯を閉じた。死因は胃癌であった。北豊島郡元金杉(現荒川区東日暮里)の自宅で、子どもたちに囲まれながらの最期だった。亡骸(なきがら)は東京・広尾の臨済宗祥雲寺内の香林院に葬られた。

由一の画業は、明治初期の未曾有の変革と動乱の中で苦節を強いられ、本格的な画業は慶応3年(1867)40歳頃からであり、実質的にはわずか25年ほどで極めて遅くそして短い。その間に多くの大作を残した。
由一に対する専門家・研究者の評価の一部を紹介したい。
「由一の絵画は、制作の過程が同時に世界認識の過程でもあったという、近代日本洋画史に類例のそう多くはない形而上学的な意味合いを、深い語調をもって今日なお私たちに語りかけてくるのである」。「まるで三島土木の得意の作はそのまま由一洋画の秀作でもあったというかのようである」。
○「日本の近代美術」(土方定一)より。
「幕末の下級武士=インテリゲンツィアの実学=自然科学的な精神が高橋由一のなかに激しく共有されていたことを想像させるし、その後の高橋由一は、この精神のなかで生き続けた幕末、明治初期の典型的な画家となっている。そういう意味で、由一は享保(江戸中期)にはじまる洋画家の最後の人であり、明治にはじまる洋画家の最初の人ということになる」。
○「絵かきが語る近代美術 高橋由一からフジタまで」(菊畑茂久馬)より。
「日本の近代化は明治になって一気に果たされ、江戸前近代を一掃したかのように言われた時代がありまして、その時代の転換期に、高橋由一の絵はキーポイントとして立ち現われるという重要な役割を背負わされていると私は思います。つまり由一の絵をどうみるかということで、自らが問われているということです」。「高橋由一が大事な絵かきということは、こういう歴史観の潮目の所になると、轟然と姿を現すというところを押えておかねばならないと私は思います」。
参考文献:古田亮「高橋由一」(中公新書)、「高橋由一と三島通庸」(西那須野町)、東京芸術大学・筑波大学所蔵関連文献など。
(つづく)
安心、それが最大の敵だの他の記事
おすすめ記事
-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2025/04/01
-

-

-

-

-

全社員が「リスクオーナー」リーダーに実践教育
エイブルホールディングス(東京都港区、平田竜史代表取締役社長)は、組織的なリスクマネジメント文化を育むために、土台となる組織風土の構築を進める。全役職員をリスクオーナーに位置づけてリスクマネジメントの自覚を高め、多彩な研修で役職に合致したレベルアップを目指す。
2025/03/18
-

ソリューションを提示しても経営には響かない
企業を取り巻くデジタルリスクはますます多様化。サイバー攻撃や内部からの情報漏えいのような従来型リスクが進展の様相を見せる一方で、生成 AI のような最新テクノロジーの登場や、国際政治の再編による世界的なパワーバランスの変動への対応が求められている。2025 年のデジタルリスク管理における重要ポイントはどこか。ガートナージャパンでセキュリティーとプライバシー領域の調査、分析を担当する礒田優一氏に聞いた。
2025/03/17
-

-

-

なぜ下請法の勧告が急増しているのか?公取委が注視する金型の無料保管と下請代金の減額
2024年度は下請法の勧告件数が17件と、直近10年で最多を昨年に続き更新している。急増しているのが金型の保管に関する勧告だ。大手ポンプメーカーの荏原製作所、自動車メーカーのトヨタや日産の子会社などへの勧告が相次いだ。また、家電量販店のビックカメラは支払代金の不当な減額で、出版ではKADOKAWAが買いたたきで勧告を受けた。なぜ、下請法による勧告が増えているのか。独占禁止法と下請法に詳しい日比谷総合法律事務所の多田敏明弁護士に聞いた。
2025/03/14









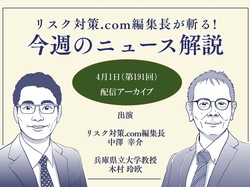













![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)






※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方