2019/12/19
昆正和のBCP研究室
■避難支援が必要な社員への対応
今日では、外国人労働者やハンディキャップを持つ社員を雇用している企業も少なくない。こうした社員が地震等の災害に遭遇した場合、一般の社員よりも不安や心細さ、あるいは戸惑いが大きいということに配慮して支援に当たらなければならない。
(1)外国人労働者の避難対応
東日本大震災が発生したとき、工場で働いていた3名の外国人労働者は直ちに作業の手を止めて工場の外に避難した。その後も余震が断続的に続いたため、3名のうち2名が「地震が怖いので帰国したい」と会社に申し出た。他に人材を確保する当てがなかったので、会社側は懸命に彼らを説得して帰国を思いとどまらせたという。これは外国人労働者が片言の日本語を話せて、日常業務の手順さえこなせればよいと考えていた会社側に落ち度がある。災害を想定した緊急時の基本的な行動ルールや手順について、(少なくとも基本的な英語を交えた)オリエンテーションと避難訓練をしていなかったことによる失敗例だ。適切に事前の対応がなされていれば、外国人労働者の不安は軽減され、会社に対する信頼も維持されて地震後も安心して働くことができたことだろう。
(2)高齢者・障がい者などの避難支援
災害発生時、訪問者のなかに高齢者や障がい者、妊婦など、避難支援が必要な人がいるかもしれない。こうした人たちへの対応については、各自治体で用意している「災害時要援護者マニュアル」などを参照して事前の情報収集と備えを済ませておきたい。例えば、1.車椅子を利用している場合はブレーキをかける。階段を経由して階下に避難する場合などは、複数の支援者が必要となる。2.視覚に障害がある場合、大声で周囲に自身が視覚障害者であることを告げ、避難を誘導してもらう。3.妊婦の場合、落下物や転倒物からお腹を守るとともに、援護者に頼んで避難を誘導してもらう。4.高齢者の場合、特に持病やハンディがない限りは一般の社員と同じ方法で避難する。介助が必要な高齢者の場合は、周囲の手を借りてともに避難する、といったことである。
緊急時に避難の支援が必要になる外国人労働者やハンディのある社員を雇用している職場では、緊急時の援護者を複数指名しておこう。緊急時に援護者が不在の場合は、被援護者のほうから周囲に援護を頼み、取り残されることがないようにする必要がある。
昆正和のBCP研究室の他の記事
おすすめ記事
-

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2025/04/08
-

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ
リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。
2025/04/05
-

-

-

-

-

全社員が「リスクオーナー」リーダーに実践教育
エイブルホールディングス(東京都港区、平田竜史代表取締役社長)は、組織的なリスクマネジメント文化を育むために、土台となる組織風土の構築を進める。全役職員をリスクオーナーに位置づけてリスクマネジメントの自覚を高め、多彩な研修で役職に合致したレベルアップを目指す。
2025/03/18
-

ソリューションを提示しても経営には響かない
企業を取り巻くデジタルリスクはますます多様化。サイバー攻撃や内部からの情報漏えいのような従来型リスクが進展の様相を見せる一方で、生成 AI のような最新テクノロジーの登場や、国際政治の再編による世界的なパワーバランスの変動への対応が求められている。2025 年のデジタルリスク管理における重要ポイントはどこか。ガートナージャパンでセキュリティーとプライバシー領域の調査、分析を担当する礒田優一氏に聞いた。
2025/03/17











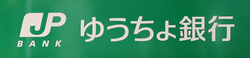












![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)






※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方