2019/05/08
ワールド ファイアーファイターズ:世界の消防新事情
1.STARTトリアージ法を応用し、乗務員を含む災害対応関係者全員
(可能な限りFRを含む)に教育・訓練する。
2.Lateral Trauma Position(右側を下にした外傷側臥位)をファーストレスポンダー全員に教育・訓練する。
3.メインの消防活動隊は、関係機関が現場指揮本部において、一目で全体の被災状況を把握できる ICS(Incident Command System)による集団災害指揮活動マニュアルを作成し、いつでも現場における役割や責任を明確にし、各隊の共通認識のもとに実働できるよう、教育・訓練を行っておく。
4.搬送員、搬送先病院は、傷病者の衣服に付着した航空機燃料による2次災害や傷病者の化学熱傷に配慮し、安全に脱衣を行う。
5.搬送先病院で治療待ちの傷病者をバックボードから下ろして病院側のストレッチャーに移して待機させる。
6.Brace Position、シートベルトなど外傷予防の研究&実施。
7.意識不明者と体重150キロ以上の乗客のシューター脱出が課題。
8.空港外墜落時の出動態勢と部隊フォーメーション&活動手順マニュアル。
9.メディアへの展示訓練の必要性。既存の内容では逆効果だと思う。
10.活動選択肢があっての臨機応変。なければ場当たり的活動で終わる。
など
航空機事故は、ひとたび起こると百名単位での死傷者を出す事が予測される、またICAOの安全レポートを読んでいると、大勢の死者を出した事故原因はさまざまだが、航空会社によっては、十分なメンテナンス体制を行っていなかったことやパイロットの若年化による経験不足、また、最新の機体においても、ソフトウェアの不具合による墜落事故なども発生していることから、予防という視点では、海外から日本国内に就航する航空会社の安全評価と許可などの選択基準の必要性も挙げられている。
また警防という視点からは、空港内外における航空機災害対策訓練が、実際に起こる可能性のあるさまざまなシナリオを想定して、関係機関が一体となって具体的に行われているか? と指摘している消防関係者も多い。
オリンピックなどスポーツイベントでは、その国を代表する国民的ヒーローの選手も大勢、航空機を使って来日する。また日本政府は2020年に訪日外国人旅行者数を2015年の約2倍の4000万人と目標を定めており、そのうちの3500万人が空路を利用するものと想定している。
当然、航空交通量も増加することから、羽田都心上空ルート、成田での管制機器 の高度化(広域マルチラテレーションの導入)など、首都圏空港を機能強化(約8万回発着枠増)することにより対応可能と航空関係者は語っている。
また、将来の増大する航空交通量に対応するための航空路空域の上下分離が2025年4月には完了するとのことで、航空管制の場も大きく変化していくなど、これからもますます外国人観光客の増加を目指しているが、安全面もしっかりと体制を備えて、空港施設内外の墜落事故対応訓練を行っておかなければ、国際的な問題につながるのは間違いない。大事故が起こる前に、航空機災害対策の具体的な強化が早急に行われる必要があると思われる。
(了)
一般社団法人 日本防災教育訓練センター
https://irescue.jp
info@irescue.jp
ワールド ファイアーファイターズ:世界の消防新事情の他の記事
おすすめ記事
-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2025/04/01
-

-

-

-

-

全社員が「リスクオーナー」リーダーに実践教育
エイブルホールディングス(東京都港区、平田竜史代表取締役社長)は、組織的なリスクマネジメント文化を育むために、土台となる組織風土の構築を進める。全役職員をリスクオーナーに位置づけてリスクマネジメントの自覚を高め、多彩な研修で役職に合致したレベルアップを目指す。
2025/03/18
-

ソリューションを提示しても経営には響かない
企業を取り巻くデジタルリスクはますます多様化。サイバー攻撃や内部からの情報漏えいのような従来型リスクが進展の様相を見せる一方で、生成 AI のような最新テクノロジーの登場や、国際政治の再編による世界的なパワーバランスの変動への対応が求められている。2025 年のデジタルリスク管理における重要ポイントはどこか。ガートナージャパンでセキュリティーとプライバシー領域の調査、分析を担当する礒田優一氏に聞いた。
2025/03/17
-

-

-

なぜ下請法の勧告が急増しているのか?公取委が注視する金型の無料保管と下請代金の減額
2024年度は下請法の勧告件数が17件と、直近10年で最多を昨年に続き更新している。急増しているのが金型の保管に関する勧告だ。大手ポンプメーカーの荏原製作所、自動車メーカーのトヨタや日産の子会社などへの勧告が相次いだ。また、家電量販店のビックカメラは支払代金の不当な減額で、出版ではKADOKAWAが買いたたきで勧告を受けた。なぜ、下請法による勧告が増えているのか。独占禁止法と下請法に詳しい日比谷総合法律事務所の多田敏明弁護士に聞いた。
2025/03/14
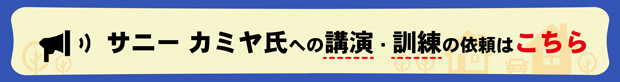























![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)






※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方