描けないバラ色の未来
私たちの結末は!?
最終回:”時間切れ”となった世界で

昆 正和
企業のBCP策定/気候リスク対応と対策に関するアドバイス、講演・執筆活動に従事。日本リスクコミュニケーション協会理事。著書に『今のままでは命と会社を守れない! あなたが作る等身大のBCP 』(日刊工業新聞社)、『リーダーのためのレジリエンス11の鉄則』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)、『山のリスクセンスを磨く本 遭難の最大の原因はアナタ自身 (ヤマケイ新書)』(山と渓谷社)など全14冊。趣味は登山と読書。・[筆者のnote] https://note.com/b76rmxiicg/・[連絡先] https://ssl.form-mailer.jp/fms/a74afc5f726983 (フォームメーラー)



















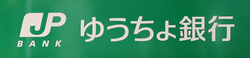













![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)






※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方