安全衛生
-

地上波メディアと専門家の相互依存関係
前回は専門家の発信について、正確性にこだわるあまり逆に分かりにくく誤解を招くケースを紹介しました。今回は、学術的に純粋な解説ではなく、別の目的・意図を持って発信されるケースを考えます。これはマスメディアの特性と絡んだ、ある意味、最も問題のある行為と思われ、我々はよほど注意して自己防衛する必要があります。
2022/06/24
-

第183回:激動の時代におけるリスクマネジメントはどうあるべきか【前編】
激動の時代におけるリスクマネジメントはどうあるべきか、世界有数の大企業でリスクマネジメントを主導する立場にいる人々への調査結果をまとめた報告書。感染症によるパンデミック、気候変動、ウクライナ侵攻といった3つの重大な事象が同時に発生している現状において、企業におけるリスクマネジメントや、リスクマネジメントのプロフェッショナルの仕事をどのように変えていくべきか、示唆に富む内容となっている。
2022/06/21
-

6月は外国人労働者問題啓発月間です
厚生労働省では、毎年6月1日からの1カ月間を「外国人労働者問題啓発月間」とし、外国人問題に関する周知・啓発活動を行なっています。今年は、「共生社会は魅力ある職場環境から〜外国人雇用はルールを守って適正に〜」を標語に、労働条件などルールに則った外国人の雇用や外国人労働者の雇用維持・再就職援助などについて、事業主や国民を対象とした啓発活動が行われています。
2022/06/21
-

第3回 職場が「曖昧な言葉」であふれてはいないか?
スタッフ一人ひとりの行動を変容させ職場でのミスや事故を防止するためには、職場全体の文化として、「安全行動を取る」という文化を、現場のリーダー、マネジャーが率先して築かなければならないのです。今回は「安全行動」について掘り下げます。
2022/06/15
-

現地報告!上海の街から人が消えた
4月1日、上海市内の都市封鎖が始まり、魔都と呼ばれる街から人が消えました。全面解除となったのが、ほんの数日前の6月1日。この間の動向は日本にいる方々もさまざまなメディアの情報を見聞きしてご存じと思いますが、この都市封鎖が日系企業の事業環境にどのような影響を与えたのか。実際に封鎖に遭遇した立場から報告します。
2022/06/10
-

安全・安心な観光は産業の課題であり地域の課題
知床観光船の遭難事故で、観光事業のリスク管理・危機管理上の問題が浮き彫りとなりました。杜撰な経営や不適切な契約の排除は不可欠ですが、それが一過性の対策で終わっては意味がありません。安全・安心な観光地づくりに向けて地域の産業・行政が危機を共有し、信頼回復とブランド構築の取り組みを進めていくためには何が必要か。立教大学観光学部の野田健太郎教授に聞きました。
2022/06/09
-

センセーショナルな言葉だけ切り取られる
専門家の発言にはいくつかのパターンがあり、それを前提とした思考がなされないと、すべて鵜呑みにしてしまいがちです。専門家の発言といえども鵜呑みにすることには危険がともなうと、これまで述べてきました。パターンは複数ありますが、今回は表現の正確性にこだわるがゆえに一般に分かりにくく、誤解を招くケースを紹介します。
2022/06/08
-

相談窓口と担当者を置くだけでは不十分
引き続き、2022年4月1日から中小企業においても義務化されたパワーハラスメント防止措置について考えます。今回は、企業がパワーハラスメントを防止するために講ずべき措置の中から「相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備」について考えます。「適切に対応する」とはどういうことか、具体的にみていきましょう。
2022/06/08
-

急務となっているカスタマーハラスメント対策
改正労働政策総合推進法第30条の2(通称、パワハラ防止法)が令和4年4月1日から中小企業にも適用されるようなり、パワハラ防止措置を講じることは、全ての事業主の義務となっています。最近は、ハラスメント防止措置の一環として、一般社員研修や管理職研修でハラスメント研修を実施する企業が増えており、私も講師を務める機会が増えていますが、パワハラ、セクハラなどの職場のハラスメントに加えて、「カスタマーハラスメント」に関する事項を研修内容に含めることを求められることが多くなっています。顧客等の著しい迷惑行為に悩む企業や労働者は少なくありません。そこで今回は、社会問題にもなっているカスタマーハラスメントについて解説します。
2022/06/07
-

危機をシェアする 志と技の共有
新型コロナウイルスの第6波にはじまった2022年。増大するリスクのなかで企業が重要な経営判断に迫られる場面は急増、同時に危機管理の位置付けもますます高まっています。この難局を乗り切るには、担当者が組織の垣根を越え、危機管理の意識・知見・ノウハウを共有することが必要。今号はそうした観点からの提言と取り組みを紹介します。
2022/06/01
-

第180回:英国の金融関係者のリスク認識がどのように変化しているか
今回紹介するのは、英国の中央銀行にあたるイングランド銀行が半年に1回行っている、英国内の銀行や外国の大手銀行、機関投資家などを対象とした「Systemic Risk Survey」というアンケート調査の2022年上半期版の結果。英国の金融システムの安定性に関するリスクを、市場参加者がどのように認識しているかを追跡調査するものだ。
2022/06/01
-
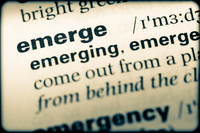
新たに出現するリスク
リスクマネジメントの新たな課題の一つとして、新興リスク(emerging risks:エマージングリスク)に対処することがある。増加する急速な環境変化、複雑化する環境に対応を迫られているからである。
2022/05/31
-

ワークショップ方式で振り返る「企業の新型コロナ対応における法的課題」
新型コロナウイルスによるパンデミックが始まってから2年半が過ぎようとしています。この間、企業では在宅勤務が一気に加速し、働き方は大きく変わりました。他方で、勤怠管理の在り方や、従業員や家族に感染者や農耕接触者が出た際の対応、ワクチン接種への対応、国内外への出張、さらに感染者が出た際の公表の在り方などについては対応に苦慮された企業も多かったように思います。そこで本セミナーでは、企業のコロナへの対応を法的側面から振り返り、次の大規模災害、あるいは新たな感染症の拡大時に向け、どのような対策が必要なのかを考えます。
2022/05/30
-
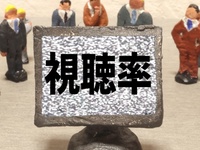
専門家の発言を鵜吞みにしてよいのか
昨今の報道は、専門家と称する人たちがあらゆる事案に解説を加えます。しかし、その言説はどこまで信用に値するでしょうか。コロナに関する感情的世論が醸成されたのは、メディアが視聴率を稼ぐために専門家を都合よく利用した結果といえます。そうした偏向情報から自己を防衛するには、専門家の解説であっても妄信しない姿勢が必要です。
2022/05/26
-

第179回:サプライチェーンにおけるリスクをどのように把握していくか
2022年5月に発表されたサプライチェーンのレジリエンシーに関する報告書。欧米のIT、ITセキュリティ、および調達・購買に関する意思決定者1500人を対象として行われたアンケート調査に基づくもので、大企業におけるサプライチェーンの状況が反映されている。回答者の86%が、サプライヤーが特定の地域に集中しすぎていることを懸念しているという。
2022/05/25
-

あらゆる手段で周知してこそのパワハラ防止
引き続き、4月1日から中小企業においても義務化されたパワーハラスメント防止措置について考えます。企業がパワハラを防止するためには、方針を明確にするだけでなく、それをあらゆる機会、あらゆる手段で従業員に周知しなければなりません。厚生労働省のガイドブックをもとに、そのポイントを説明します。
2022/05/11
-

成人年齢引き下げは未成年者雇用にどう影響するか
改正民法の施行により成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました。これにより、2022年4月1日からは、満18歳以上であれば、携帯電話の購入契約やアパートの賃貸借契約、クレジットカードの作成なども親の同意を得ることなく行うことができます。その一方で、喫煙、飲酒、競馬・競輪などの公営ギャンブルについては、これまで通り年齢制限が20歳に維持され、国民年金への加入義務が生じるのも20歳からです。では、成人年齢の引き下げは、労働契約の締結にどのような影響を及ぼすのでしょうか。今回は未成年者雇用の留意点について解説します。
2022/05/06
-

職場からハラスメントをなくす7ステップ
職場での社会的な環境整備にとって欠かせないのは、ハラスメントを生じさせないことである。セクハラ、パワハラなど多様なハラスメントは、職場での心理的な安心感を損なうものであり、ある調査によれば、多くの従業員はそうしたハラスメントの現場に遭遇していること、またリモートワークへ移行しても、そうした事態は決して減少するわけではないことも明らかになっている。しかも、ハラスメントが解消されないことで離職する者も決して少なくないという。
2022/05/06
-

飲酒運転をさせないための企業のリスク対策
2022年4月1日道路交通法施行規則の一部が改正され、安全運転管理者の業務に白ナンバーの車両を一定台数以上保有する事業所に対してアルコールチェックが義務化されました。そこで、今回の法改正に伴い企業が対応すべき事項について元警察官である社会保険労務士が解説します。
2022/05/04
-

いま目の前にある 富士山噴火という危機
噴火は自然のサイクルとして必ず起きますが、富士山は最後の噴火から300年以上沈黙。もし前回の宝永噴火と同規模で噴火したら降灰による首都圏への影響も甚大です。それはいつか、そのとき何が起きるのか。山梨県富士山科学研究所所長の藤井敏嗣氏に解説いただくとともに、企業の備えと取り組みを調査、取材しました。
2022/05/02
-

「GoTo=感染拡大」という意図的な誤誘導
感染者を特定、隔離して拡大を防ぐのは感染症対策の基本。しかし「だから行動規制が必要」とするのは論理の飛躍です。状況を客観的に見る限り、強力なロックダウンでなければ感染抑止の効果があるとはいえない。にもかかわらず「人流=感染拡大」の煽りはやまず、GoToトラベルなどは中断に追い込まれました。コロナ対策としての行動規制を考えます。
2022/04/25
-

モノの動きを可視化し、現場のトレーサビリティ確保とDX化
業務系ソフトウェア開発・販売のセールスワン(東京都港区、山本圭一社長)は、工具の持出・返却管理システム「工具ONE」を通じて企業のDX化を支援。社有資産の使用や保管、点検、棚卸しなどにかかる作業を自動化することで業務改善をあと押しするとともに、ヒト・モノの動きを可視化、データベース化して経営改善に役立てる。
2022/04/20
-

健康も害するパワハラ 全職場で防止措置
ハラスメントは人権侵害行為であるとともに、職場の雰囲気が悪くなる、仕事の生産性が落ちるなど、健康経営の観点からも重大な問題です。2020年6月1日に「改正労働施策総合推進法」が施行され、中小企業においても4月1日からパワーハラスメント防止措置が義務化されました。今回は、パワーハラスメント防止対策の内容を確認します。
2022/04/13
-

目的・効果論に立てば全員マスクはもう不要
マスクに対する議論が活発になってきました。3月に開催されたG7の映像を見て分かる通り、世界ではもうノーマスクが主流。岸田首相は現地ではマスクなし、帰国すればマスク着用という不可思議な構造です。これが日本国内で適切に議論した結論であればいいですが、実際は感情論に支配された結果に過ぎません。目的・効果論からマスクの問題を考えます。
2022/04/11
-

被災見舞金は福利厚生か給与か
職場の作業環境や清潔保持、休養のための措置については、事務所衛生基準規則等により基準が定められています。しかし、従来の基準が定められてからすでに50年近く経過し、社会状況も大きく変化していることから、令和3年12月1日に「事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令」が公布され、職場の照度、便所、救急用具等に関する労働安全衛生基準が見直されました。
2022/04/11

















![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)





