前回、前々回に続き、2022年4月1日から中小企業においても義務化されたパワーハラスメント防止措置について考えます。今回は、企業がパワーハラスメントを防止するために講ずべき措置の中から、「相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備」について考えます。
1.相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
(1)相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること
職場においてパワーハラスメントが起きないように対策を講じていても、実際には、パワーハラスメントが発生することが考えられます。そのようなとき、パワーハラスメントの被害を受けた従業員が相談できる窓口を設置しておくとともに、その存在を従業員に周知しておくことが求められています。
「窓口をあらかじめ定める」ということは、単に窓口があるという形式的なものではなく、従業員が利用しやすいものである必要があります。必ずしも、面談形式にこだわらず、電話やメールなど複数の方法で利用できる窓口が望ましいと言えます。
(2)相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるようにすること
相談の内容や状況に応じ、適切な対応がとれるような体制を構築しておくことが求められています。例えば、必要に応じて、人事担当者や相談者の上司と連携をとることなども検討してくことが大切です。
また、相談に来る従業員は、パワーハラスメントによる精神的・肉体的な被害を受けています。相談窓口担当者は、その心身の状況や、実際にパワーハラスメントを受けた際の気持ちなどを理解した上で、適切に対応できることが求められます。これについて、次ページで具体的にみていきます。






















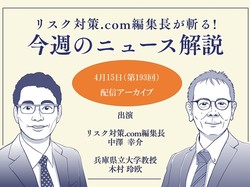













![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)






※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方