センセーショナルな言葉だけ切り取られる
第17回:情報活用の方法論(2)

多田 芳昭
一部上場企業でセキュリティー事業に従事、システム開発子会社代表、データ運用工場長職、セキュリティー管理本部長職、関連製造系調達部門長職を歴任し、2020年にLogINラボを設立しコンサル事業活動中。領域はDX、セキュリティー管理、個人情報管理、危機管理、バックオフィス運用管理、資材・設備調達改革、人材育成など広範囲。バイアスを排除した情報分析、戦略策定支援、人材開発支援が強み。
2022/06/08
再考・日本の危機管理-いま何が課題か

多田 芳昭
一部上場企業でセキュリティー事業に従事、システム開発子会社代表、データ運用工場長職、セキュリティー管理本部長職、関連製造系調達部門長職を歴任し、2020年にLogINラボを設立しコンサル事業活動中。領域はDX、セキュリティー管理、個人情報管理、危機管理、バックオフィス運用管理、資材・設備調達改革、人材育成など広範囲。バイアスを排除した情報分析、戦略策定支援、人材開発支援が強み。
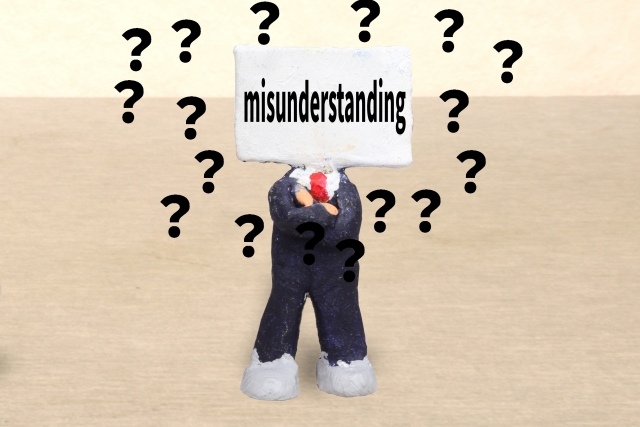
専門家の発言であろうとも、金科玉条のごとく鵜呑みにすることに危険がともなうことをこれまで語ってきた。それは専門家の発言にいくつかのパターンがあり、それを前提とした然るべき思考がなされていないことで生じる。パターンは複数あるので、パターン別にその注意点を含めて論ずる。
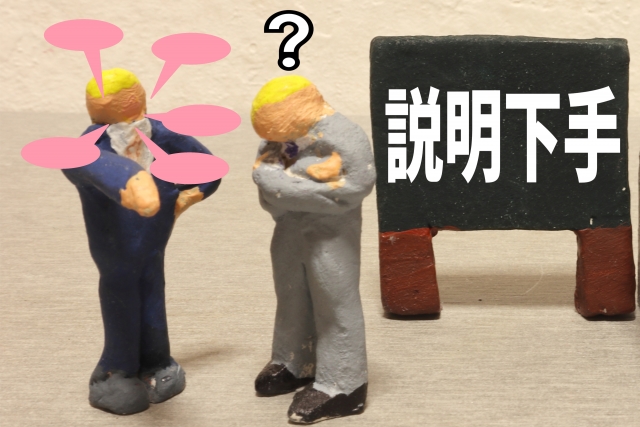
パターンの一つは、専門家ゆえに表現の正確性にこだわり、一般にはかえって分かりにくく、誤解を招くことだ。分かりやすく説明するための表現上の嘘にならない程度の比喩的表現が不十分で、どうしても強調したいことが先走り、ていねいに表現すればするほど、一般人には誤解をともなうケースであろう。
このパターンの場合、本来であれば伝えるべきメディアが適切に解釈し表現するべきなのだが、その能力がないのか、意図的に都合よくセンセーショナルに切り取り表現するのか、どちらにしても論旨が曲がって伝わることが多い。
具体的な例として「8割おじさん」と称される京都大学の西浦博教授(発言自体は北海道大学教授時代のもの)が挙げられる。
最初に西浦教授の名誉のためにも断っておくが、教授の研究成果は感染症の数理モデル化等最先端の成果を誇り、実績豊富で優秀な研究者であることは疑いようがない。そして、一度、筆者の疑問、確認したいこと、見解を質問させていただく機会があったが、筆者のようなド素人の質問にもていねいに、かつ紳士的にお答えいただくなど、人間的にも尊敬に値する方である。
結局、言葉を切り取り、センセーショナルな発言としてメディアが利用した構造であり、ある意味、西浦教授もメディアの被害者と感じている。

「42万人死ぬ」は非常にセンセーショナルな響きである。この発言を聞き、その根拠となる論理を確認したく、当時北海道大学のホームページを確認し、いくつかの論文も拝読させていただいた。内容的には医学系の論文というより数学・統計・データ分析系の内容であり、微積分程度の知識があれば読める内容であった。
結論からいうと極めて単純、ある条件を元に数学的に計算したものである。実効再生産数にもとづき感染は拡大し、致死率にもとづいて死者が発生する。この感染拡大は集団免疫を獲得するまで拡大し、集団免疫と共に収束する。当時筆者も、この論理を元に、より簡易な計算をしてみたら近しい値が出ている。
しかし、これは「何もしなければ」が前提なのだ。それは事実上あり得ない設定であり、だから対策が必要だと訴えているのだ。専門家としてリスクを最悪シナリオで提示するのは至極当然のことだろう。
現実世界では、この「何もしなければ」は実現しない。危機を感じた個々人の行動は心理的に抑制されるだろうし、マスクや飛沫飛散防止、強制換気、行動規制に加え、個々人の手洗い、うがい、検温・血中酸素濃度測定などの健康管理は「やれることはやる」に働くので、42万人が死ぬことは決してなかったのだ。加えて、時系列で、ウイルスの変異やワクチン、治療薬の投入などの要素が変化することを忘れてはならない。
再考・日本の危機管理-いま何が課題かの他の記事
おすすめ記事


中澤・木村が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2026/01/06

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ
リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。
2026/01/05
年末年始にサイバー攻撃は約2倍以上増加する
サイバー攻撃のリスクは、平日よりも休日に高まる傾向がある。デジタルデータソリューション株式会社(東京都港区)の調査によると、年末年始にはサイバー攻撃が約2倍以上に増加することが明らかになっているという。
2026/01/04

能登半島地震からまもなく2年
能登半島地震からまもなく2年。災害対応の検証も終盤に入っています。浮上した課題を反映し、災害関連法も変わりました。来年はこれらの内容をふまえた防災・BCPの見直しが加速しそうです。発災直後から被災地を調査し、石川県の初動対応を振り返る検証委員会の委員も務めた金沢大学准教授の青木賢人氏に防災・BCP強化の方向を聞きました。
2025/12/25





※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方