連載・コラム
-
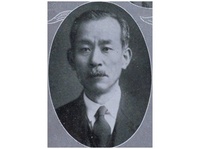
戦前・戦後の2人の知性派都市計画家~その苦悩と実践~
工学博士・直木倫太郎著「技術生活より」(東京堂)は、土木学会が選定した「戦前土木名著100著」の中でも異色の書である。奥付によると同書は大正7年(1918)3月3日発行とあり、約100年前の刊行である。この「激烈」な「名著」は、土木技師としての日ごろの鬱々(うつうつ)たる苦悩や怒りを歯に衣を着せずにぶちまけた私憤の思索集である。なぜ技術専門書とはおよそ内容を異にする「異端の書」が戦前の名著100著に選定されたのだろうか。同書の背後に一貫して流れる氏の祈りのような技術者倫理を感じとらなければならないが、まずは著者直木倫太郎(1876~1943)の人生を略記する。
2017/11/13
-

-

-

-

-

-

東北の復興現場を訪ねて~その2、山元町、岩沼市
前回に続き、東北の復興現場の報告である。宮城県南端の山元町(人口1万2462人)は大津波により死者700人、行方不明者18人を出した。県仙台市以南では名取市に次ぐ犠牲者数である。同町は復興を機に、「コンパクトで持続可能なまちづくり」を目指し、分散していた集落を3つの新市街地に集約するまちづくりを進めていた。昨年10月、被災者の集団移転先となる2つの新市街地(つばめの杜地区、新坂元駅周辺地区)が完成して「まちびらき」の式典が行われた。その後、遺跡の出土で完成が遅れていた宮城病院周辺地区も住宅の引き渡しが行われて、すべての移転が完了した。同町も人口減となっており、商業施設などを誘致して人口減に歯止めをかけたい考えだ。
2017/09/19
-

-

家庭の防災を推進するために必要なものは何か?
これまでの本連載においては、主に国、地域、あるいは企業を対象とした調査研究を紹介してきたが、今回は家庭の災害対策に関する研究例を紹介する。 2017 年 8 月に、リスク分析学会(The Society for Risk Analysis)の学会誌『Risk Analysis』に「保険、公的支援、および家計に対する洪水リスクの軽減:オーストリア、イングランド、およびルーマニアにおける比較研究」(原題は本稿サブタイトルのとおり)という論文が掲載された(以下「本論文」と略記)(注 1)。タイトルから想像される通り、家庭における洪水対策に保険や公的支援などがどのように影響を与えているかを調査した結果が報告されている。
2017/09/12
-

-

現代版・ダムをめぐる考察~ア・ラ・カルト~
全国にあるダム約3000カ所(堤体の高さ15m以上)のうち、建設から半世紀近く経って再開発が必要なものや洪水・水需要対策から改修・かさ上げなどが求められているものが少なくない、と聞く。だがダム建設ブームはすでに去り、新規建設が大幅に減っていることから、高度な技術を必要とするダム技術者が国や都道府県を問わず減ってきているのが実情のようである。都道府県が建設管理している治水・利水用ダムは少なくないが、都道府県や市町村の中にはダムや河川の専門技術者をかかえていないところが結構多いのである(鬼怒川決壊で市域の大半が水没した常総市も河川技術職がいなかった)。
2017/09/04
-

-
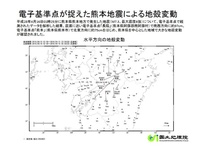
-

-

-

-

-

-

2017 年上半期に発生した自然災害の概観
かつて紙媒体の『リスク対策.com』での連載記事で、世界最大級の再保険ブローカーである Aon Benfield 社が発表した報告書『2015 Annual Global Climate and Catastrophe Report』を紹介させていただいた(注 1)。 これは 2015 年の一年間に世界で発生した自然災害を、主に人的被害と経済損失、および保険金支払額を中心にまとめたものだが、同社はこのようなデータを常時収集しており、世界各国で発生した自然災害のデータをまとめた報告書を毎月作成し、さらに毎年 7 月には、上半期を総括した報告書を作成している(注 2)。
2017/08/01
-

-









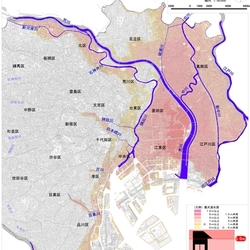














![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)





