2018/08/27
安心、それが最大の敵だ
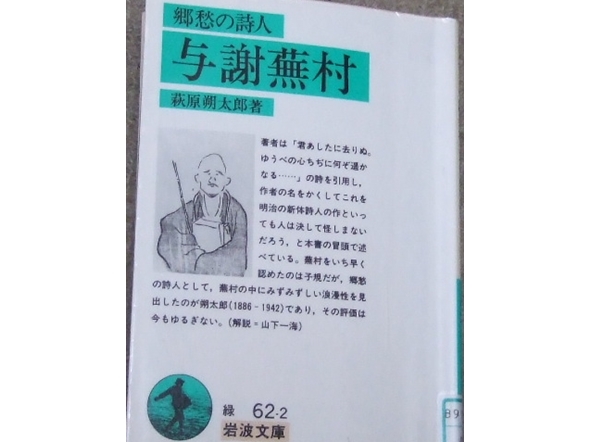
朔太郎しか書けない「蕪村論」
菜の花や月は東に日は西に
愁(うれ)ひつつ丘に登れば花茨
木枯や何に世渡る家五軒
与謝蕪村ならではの秀句である。私は本格的な句作や俳句研究をしたことはないが、それでも時に駄句をひねり古今の名句を鑑賞することを好んできた。近現代の俳句はもとより、江戸初期の松尾芭蕉、同中期の蕪村、後期の小林一茶の3俳聖の作品を愛読して来た。とりわけ蕪村には強く魅かれるものがある(蕪村は生前俳人よりも画家として著名であった)。蕪村俳句の魅力をみごとに喝破した作品論が、詩人・萩原朔太郎(1886~1942)の「郷愁の詩人 与謝蕪村」(昭和11年刊行)である。名だたる詩人が論じた稀有な「詩人論」として、氏の蕪村論に勝るものはない。私も共感するところが少なくない。朔太郎の「蕪村論」を論じてみたい(引用は岩波文庫版。同書「解説」から引用する)。
朔太郎は自著の冒頭で言う。「俳句嫌いであった自分にとって、蕪村だけが唯一の理解し得る俳人であった」。「彼の俳句だけを愛したという事実は、思うにおそらく蕪村における特異なものが、僕の趣味性や気質における特殊な情操と密に符合し、理解の感流するものがあったためであろう」。蕪村に同じ資質の詩人の魂を見出したのである。朔太郎は蕪村の句作の特徴として(1)万葉歌境に通じる春怨思慕の若々しいセンチメントがあること(2)画家らしく色彩の調子(トーン)が明るく、絵具が生々(なまなま)しており、強烈であること、即ち<若々しい明るさがあること>を挙げている。蕪村が心酔してやまない芭蕉と比較して、芭蕉が老の静的な美を慕い反青春的風貌を持っているのに対し、蕪村は色鮮やかな青春の情緒を描いていると指摘する。
朔太郎は蕪村評価の歴史を回顧して、江戸時代には影の薄かった蕪村が、近代になって再評価されたのは、正岡子規以来のことだとした上で、そこで作られた<定評>―即ち蕪村は客観的であり、芭蕉が主観的であることに対比して考えられるという<定評>が、無批判に受け継がれていると批判する。蕪村の客観的と見える背後に実は強い主観があることを指摘し、そこにこそ蕪村のポエジイ(詩情)があると強調する。いまこそ蕪村の詩境を考えなければならないとして、そのポエジイの本質を<郷愁>であると結論づける。同書では「春の部」「夏の部」「秋の部」「冬の部」と四季に分けて秀句を論じている。
朔太郎の蕪村読解
朔太郎の優れた作品解釈を思いつくままに列記してみよう。
「蕪村の情緒。蕪村の詩境を単的に詠嘆していることで、特に彼の代表作と見るべきだろう。この句の詠嘆しているものは、時間の遠い彼岸における、心の故郷に対する追懐であり、春の長閑(のどか)な日和の中で、夢見心地に聴く子守歌の思い出である」。
「この句の情操には、或る何かの渇情に似たところの、ロマンチックな詩情がある。『名も知らぬ虫』という言葉、『白き』という言葉の中に、それが現れているのである」。
「天明3年(1783)、蕪村臨終の直前に詠じた句で、彼の最後の絶筆となったものである。白々とした黎明の空気の中で、夢のように漂っている梅の気あいが感じられる。全体に縹渺(ひょうびょう)とした詩境であって、英国の詩人イエーツが狙ったいわゆる「象徴」の詩境とも、どこか共通したものが感じられる」。
「『愁ひつつ』という言葉に、無限の詩情がふくまれている。無論現実的の憂愁ではなく、青空に漂う雲のような、または何かの旅愁のような、遠い眺望への視野を持った、心の茫漠とした愁えである。そして野道の丘に咲いた、花茨の白く可憐な野生の姿が、主観の情愁に対象されている。西洋詩に見るような詩境である」。
「月が天心にかかっているのは、夜が既に更けたのである。人気のない深夜の町を、ひとり足音高く通って行く。町の両側には、家並の低い貧しい家が、暗く戸を閉ざして眠っている。空には中秋の月が冴えて、氷のような月光が独り地上を照らしている。ここに考えることは人生への或る涙ぐましい思慕の情と、或るやるせない寂寥とである。月光の下、ひとり深夜の裏町を通る人は、だれしも皆こうした詩情に浸るであろう。しかも人々はいまだかつてこの情景を捉え表現しえなかった。蕪村の俳句は、最も短い詩形において、よくこの深遠な詩情を捉え、簡単にして複雑に成功している。実に名句と言うべきである」。
「北風の吹く冬の空に、凧(たこ)が一つ揚っている。その同じ冬の空に、昨日もまた凧が揚っていた。蕭条とした冬の季節。凍った鈍い日差しの中を、悲しく叫んで吹きまくる風。ガラスのように冷たい青空。その青空の上に浮かんで、昨日も今日も、さびしい一つの凧が揚っている。飄々(ひょうひょう)と唸りながら、無限に高く、穹窿(きゅうりゅう)の上で悲しみながら、いつも一つの遠い追憶が漂っている!この句の持つ詩情の中には、蕪村の最も蕪村らしい郷愁とロマネスクが現れている」。
「木枯らしの吹く冬の山麓に、孤独に寄り合っている五軒の家。『何に世渡る』という言葉の中に、句の主題している情感がよく現れている。荒涼とした寂しさの中に、或る人恋しさの郷愁を感じさせる俳句である」。
優れた詩人のみが優れた詩人を見出すの感を深くする。
参考文献:「加藤楸邨句集」(岩波文庫)、「郷愁の詩人 与謝蕪村」(萩原朔太郎)、筑波大学附属図書館文献。
(つづく)
- keyword
- 安心、それが最大の敵だ
- 加藤楸邨
- 萩原朔太郎
- 俳句
- 詩
安心、それが最大の敵だの他の記事
おすすめ記事
-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2025/04/01
-

-

-

-

-

全社員が「リスクオーナー」リーダーに実践教育
エイブルホールディングス(東京都港区、平田竜史代表取締役社長)は、組織的なリスクマネジメント文化を育むために、土台となる組織風土の構築を進める。全役職員をリスクオーナーに位置づけてリスクマネジメントの自覚を高め、多彩な研修で役職に合致したレベルアップを目指す。
2025/03/18
-

ソリューションを提示しても経営には響かない
企業を取り巻くデジタルリスクはますます多様化。サイバー攻撃や内部からの情報漏えいのような従来型リスクが進展の様相を見せる一方で、生成 AI のような最新テクノロジーの登場や、国際政治の再編による世界的なパワーバランスの変動への対応が求められている。2025 年のデジタルリスク管理における重要ポイントはどこか。ガートナージャパンでセキュリティーとプライバシー領域の調査、分析を担当する礒田優一氏に聞いた。
2025/03/17
-

-

-

なぜ下請法の勧告が急増しているのか?公取委が注視する金型の無料保管と下請代金の減額
2024年度は下請法の勧告件数が17件と、直近10年で最多を昨年に続き更新している。急増しているのが金型の保管に関する勧告だ。大手ポンプメーカーの荏原製作所、自動車メーカーのトヨタや日産の子会社などへの勧告が相次いだ。また、家電量販店のビックカメラは支払代金の不当な減額で、出版ではKADOKAWAが買いたたきで勧告を受けた。なぜ、下請法による勧告が増えているのか。独占禁止法と下請法に詳しい日比谷総合法律事務所の多田敏明弁護士に聞いた。
2025/03/14























![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)






※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方