<人間探求派>俳人の人生
加藤楸邨(しゅうそん、1905~93、本名・健雄)は、近現代の日本俳句界を代表する俳人のひとりである。その作風は中村草田男や石田波郷らとともに「人間探求派」と呼ばれる。私は、楸邨の自然諷詠的な表現を排除し厳格に人生を探求する作風に強く魅かれるものがあり、楸邨について以下自己流に語ってみたい。粕壁(現埼玉県春日部市)の教師時代の作品を中心とする。
私は埼玉県内の河川を現地調査したことがあった。埼玉県は北に利根川、東に江戸川、西に荒川と大河に3方を囲まれ、県内を多数の中小河川や用排水路が網の目のように走っている。古利根川や中川は江戸期以前の利根川本川であり、元荒川はその名の通り江戸期以前の荒川本川である。同県は県内に河川面積の占める割合が全国一で、その昔は今日では考えられないほど水害多発地域でもあった。
同県内の河川調査の際、私は楸邨が古利根川や元荒川などの川べりを歩き、四季の風景を俳句に詠(よ)んでいることを知った。その作品群は彼が埼玉県立粕壁中学(現春日部高校)の国語教員時代のものであった。
◇
ここで彼の人生をスケッチする。「俳句遠近」(加藤楸邨、読売新聞社)などを参考にする。彼は東京市北千束(現東京都大田区北千束)に生まれる。父は内村鑑三の唱導する無教会主義クリスチャンで鉄道官吏であった。転勤が多く、駅長であった父の転勤に伴い若い楸邨は関東、東北、北陸の各地方を転居した。漂泊性の強い習性が身についてしまった、と回顧する。金沢中学(旧制)を卒業すると、定年退職した父に代わって家計を支えるため、進学を断念して小学校の代用教員となる。(代用教員に採用されたことは一面彼が秀才であったことをうかがわせる)。人生苦難の始まりである。この頃、アララギ派や石川啄木の短歌を好んで読んだ。父の病死を期に一家はそろって上京した。
勉学への情熱が捨てきれない青年は、大正15年(1926)東京高等師範学校(東京教育大学を経て現筑波大学)に併設された第一臨時教員養成所国語漢文科に入学した。苦学生は22歳で同学年中の年長者であった。「ほとんどの期間を家庭教師として過ごしたが、むさぼるように本をよく読んだ」(「俳句遠近」)。万葉集に強く魅かれた。哲学書も読み漁り、フランスの哲学者ベルグソンの「エラン・ヴィタール」(生命の躍動)や「純粋経験」に新たな人生観を見出した。
昭和4年(1929)、東京高等師範学校を卒業し、埼玉県立粕壁中学に赴任した。この年矢野知世子(俳人)と結婚した。24歳。高等師範卒の先輩教師に「いろいろ面倒を見てやるから、その代わりに俳句会のメンバーになれ」(同上)と誘われ俳句を始めた。俳人・村上鬼城の雄渾な作風に惹かれた。「残雪やごうごうと吹く松の風」の句などに「抵抗しがたい奇妙な力を感じた」という。決定的な出会いがあった。俳人で医師の水原秋桜子との邂逅(かいこう)である。楸邨は秋桜子に従って古利根川から関宿、野田あたりへかけて作句行に歩いた。「先生も思いつめたような沈黙の時間が多くなったが『あの頃の夕闇の中に光る古利根川の水を今もさむざむと思い浮かべることができる』という先生の文は、私の中にもそのまま生きていることなのだ」(同上)。








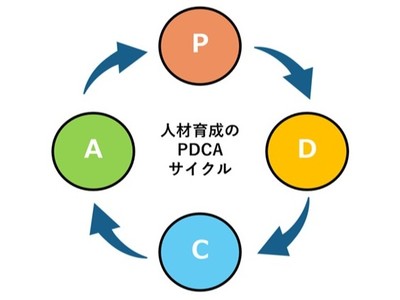
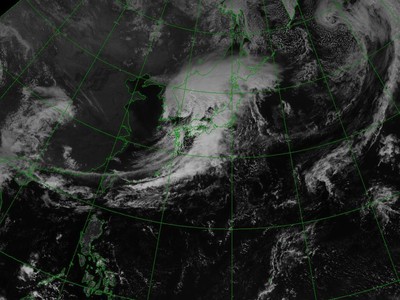











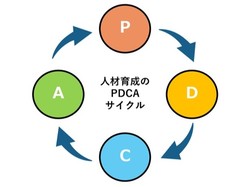











![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)






※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方