健康経営の実践に向けた土台をつくる
第11回:健康経営の要件(2)

本田 茂樹
現在の三井住友海上火災保険株式会社に入社、その後、出向先であるMS&ADインターリスク総研株式会社での勤務を経て、現職。企業や組織を対象として、リスクマネジメントおよび危機管理に関するコンサルティング、執筆活動を続ける一方で、全国での講演活動も行っている。これまで、早稲田大学、東京医科歯科大学大学院などで教鞭をとるとともに、日本経済団体連合会・社会基盤強化委員会企画部会委員を務めてきた。
2022/10/12
ウイズコロナ時代の健康経営

本田 茂樹
現在の三井住友海上火災保険株式会社に入社、その後、出向先であるMS&ADインターリスク総研株式会社での勤務を経て、現職。企業や組織を対象として、リスクマネジメントおよび危機管理に関するコンサルティング、執筆活動を続ける一方で、全国での講演活動も行っている。これまで、早稲田大学、東京医科歯科大学大学院などで教鞭をとるとともに、日本経済団体連合会・社会基盤強化委員会企画部会委員を務めてきた。

引き続き、企業が健康経営を実現するにあたり重要なポイントを確認します。
健康経営に取り組む法人を顕彰制度によって見える化する制度として「健康経営優良法人認定制度」がありますが、中小企業については「健康経営優良法人2022(中小規模法人部門)」の認定要件が適用されます[下表参照]。この制度の内容を知ることで、「健康経営推進のためには具体的に何をすればよいか」が見えてきます。
前回は「3.制度・施策実行」のうち「従業員の健康課題の把握と必要な対策の検討」を説明しましたが、今回は「健康経営の実践に向けた土台づくり」を確認します。
ここは、自社において健康経営を推進するために整備しておくべき体制や仕組みが評価項目として示されています。
「リテラシー」は、もともと「読み書きの能力」という意味ですが、ビジネスの場面では特定分野の能力や知識を活用する力、という意味で使われることが多く、例えば、ITリテラシーや金融リテラシーという使い方です。
ヘルスリテラシーは、健康や医療に関する正しい情報を入手するとともに、それを理解して活用する能力のことで、この能力が高まれば、従業員の病気を予防すること、そしてさらには健康寿命を延ばすことにもつながります。
まず、従業員に健康に関する正しい知識を身につけてもらうことが重要であり、次の取り組みが考えられます。
・健康や医療をテーマにした研修会を開催する
・社内報や社内ホームページ、またメールマガジンなどで、健康に関する情報を定期的に提供する
・行政が主催する健康づくり講座等への参加を奨励する など
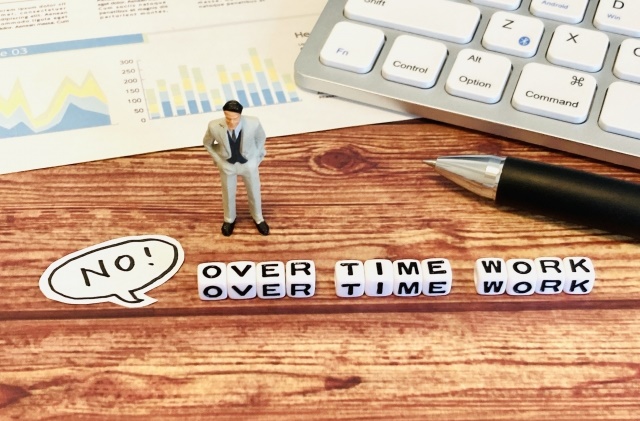
ワークライフバランスというと、「仕事と生活の調和」ということですが、その目指すところは、仕事が順調に進んでいれば私生活においても余裕を持つことができ、また私生活が充実することによって仕事もうまくいくとう流れです。私生活の中には、育児・介護、趣味や自らの学び、さらには地域活動などが含まれます。
従業員の仕事、そして私生活のそれぞれのバランスが崩れないようにするために、企業は次のような取り組みを行うことが肝要です。
・定時消灯や定時退勤(「ノー残業デー」など)の制度を導入する
・テレワーク制度を導入することで、子育てや介護を行っている従業員に働きやすい環境を提供する
・それぞれの従業員のワークライフバランスを実現するために必要な配置転換を検討する
・有給休暇の取得を奨励するとともに、上司が率先垂範する など
上司が部下に、「仕事を早く切り上げて帰ろう」と声をかけるだけではなく、それが実現できる具体的な仕組みが求められます。
ウイズコロナ時代の健康経営の他の記事
おすすめ記事

防災教育を劇的に変える5つのポイント教え方には法則がある!
緊急時に的確な判断と行動を可能にするため、不可欠なのが教育と研修だ。リスクマネジメントやBCMに関連する基本的な知識やスキル習得のために、一般的な授業形式からグループ討議、シミュレーション訓練など多種多様な方法が導入されている。しかし、本当に効果的な「学び」はどのように組み立てるべきなのか。教育工学を専門とする東北学院大学教授の稲垣忠氏に聞いた。
2025/04/10



リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2025/04/08



リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ
リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。
2025/04/05



※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方