事故・テロ
-

私が愛するアメリカ詩人R・フロスト~自然と人生~
私はアメリカに取材旅行や現場視察などで出かける際に、必ずと言っていいほど1冊の英語詩集を旅行カバンに入れた。現代アメリカを代表する詩人の一人ロバート・フロスト(1874~1963)の詩集である。何度も携帯したのでハードカバーの詩集はボロボロである。私はフロストの詩に学生時代に巡り合って以降、彼の作品を半世紀もの間愛読している。とりわけフロストが長年住みつき詩の舞台として描いた自然豊かなアメリカ北東部のニューイングランド地方を訪れる時には全集を持参して機内、ホテル、取材の合間に思いつくままページを開いては黙読した(私はフロストとともにエドガー・アラン・ポーの詩集も愛読した)。
2018/11/19
-

五輪中混雑予測、鉄道版を全日に拡大
東京都と東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会は6日、輸送連絡調整会議を東京都港区の組織委で開催した。国や関連自治体、輸送事業者なども参加。東京都ホームページにある、大会期間中の混雑予測である「大会輸送影響度マップ」の鉄道版を同日で2020年7月31日以外にも拡大した。また、大会輸送をつかさどる、輸送センターを今後設置する方針も決めた。
2018/11/07
-

米国メディア、トランプ大統領に対抗、一斉に立ち上がる
「新聞なき政府か、政府なき新聞か。いずれかを選べと迫られたら、ためらわず後者を選ぶ」。米国の<建国の父>で第3代大統領、報道の自由や人権を定めた憲法修正条項(権利章典)の生みの親トーマス・ジェファーソンのよく知られた言葉である。「言論と報道の自由」は権利章典の第1条が掲げる米国文明の魂である。原点である(ジェファーソンには別の側面があることを歴史は伝える。彼は奴隷の女性との間の隠し子スキャンダルを追及する新聞がよほど憎らしかったのか、その後新聞批判を強めた)。彼は奴隷制に反対しながら、大農場で多くの黒人奴隷を使役していた。黒白矛盾した面のある自由主義者ジェファーソンだった。これは200年も前の話である。
2018/11/05
-

私たちの周りのセキュリティ「モノ」(3)金属探知機
当連載では8月から私たちの周りにあるセキュリティ「モノ」についてお話をしています。今月はセキュリティチェックポイントの必需品、金属探知機について説明します。
2018/10/31
-

火災は科学で防御する
これまで排煙方法における場所やタイミングなどについて、世界各国の消防局で賛否両論があった。大学の火災研究施設などもエビデンスベースで参加し、さまざまな議論がなされてきた。 このたび、オランダの消防科学研究所が発表した「The Renewed View on Firefighting (火災防御の再検証) 2018」によると、①屋根に垂直排煙のための開口部を作る、②窓やドア等を利用して、水平排煙のために閉じている開口部を破壊して作る、③人工的に排煙を促し、火災建物の屋内を通気すること―によって、火点への酸素の流入が促され、確実に火災が拡大することが実証されたという。
2018/10/31
-

第4回 知ってましたか?消火栓は誰でも使えます!
前回(連載第3回)は、いかに消火器では実際の火災が消せないかを解説しました。ではどうしたら初期消火を成功させることができるのでしょうか。 身の回りに注意を向ければ、皆さんが住むマンションや勤務先のビルの共用部、通勤途中の駅、買い物に行くスーパー、高速道路のトンネル内、大きな倉庫や工場などの敷地内、道路脇のマンホールの蓋まで、いたるところに「消火栓」があることに気づきます。
2018/10/30
-

最も<古くて・新しい大学>筑波大学~その創成する精神、IMAGINE THE FUTURE~
「本学は二つの金メダル獲得を目指しています。一つはノーベル賞のそれ、もう一つはオリンピックのそれです」、「本学は国内外に<開かれた大学>を積極的に進めています。世界のトップレベルの研究者でUniversity of Tsukubaを知らない人はいないと思います」。
2018/10/29
-
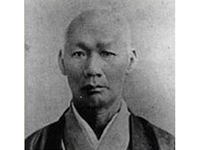
幕末群像~開明派の苦闘、江川太郎左衛門、ジョン万次郎、大鳥圭介~
本年は明治維新から150年。日本を震撼させたペリー率いるアメリカ東インド艦隊は、再来訪を予告して引上げたが、再びその威圧的姿を現したのは、幕府の予想より早く嘉永7年(1854)正月のことであった。ここに激動の幕末が幕を開ける。安政と年号が改まるのはこの年11月である。対応に苦慮した幕府首脳は、韮山代官・江川太郎左衛門英龍(ひでたつ)にアメリカ側と交渉して侵入を阻止するように命じた。老中・阿部正弘を首班とする幕閣は開明派江川の才覚に期待して彼を勘定吟味役格に任じ、対米交渉に参画させた。江川はひそかに「切り札」を用意していた。
2018/10/22
-

つながり支援や企業連携で災害対策強化
災害やテロなど有事に友人に無事を知らせるほか、支援の提供を申し出たり受けたりできるフェイスブックの機能である「災害支援ハブ」。安否確認については世界で1400回以上起動し、2017年11月時点で累計約30億人が利用した。日本でもここ2年で19回発動しているという。この機能ができたきっかけは2011年の東日本大震災だった。フェイスブック ジャパン代表取締役の長谷川晋氏に災害への取り組みを聞いた。
2018/10/19
-

第58回:BCPを発動した結果に着目したアンケート調査
BCMへの取組状況やBCPを作成したかどうかなどを調査した報告書はこれまで多数見てきたが、BCPを発動した後に関するアンケート調査はあまり多くないように思う。本稿ではそのような調査結果の一例として、BCMを中心とした情報サイト「Continuity Central」(https://www.continuitycentral.com/)が実施したアンケート調査の結果を紹介する。
2018/10/16
-

さらに進化したデジタルタイマー付き止血帯について
2018年6月9日、東海道新幹線「のぞみ」東京発新大阪行きの最終便で、愛知県在住の無職、小島一朗容疑者(22)が乗客にナタなどを振るって、男性1人が死亡。女性2人が重傷を負うという衝撃的な事件が起こった。 この事件を受けて、JR各社では警察官や警備員による駅や車内の巡回を強化しており、9月4日のJR東日本ニュースによると、今後は催涙スプレーや耐刃の手袋、ベストなどの車内への常備や、止血パッド、ゴム手袋などの医療器具の拡充も検討中との公式発表があった。
2018/10/11
-

五輪中のホテル不足、周辺エリアで吸収可能
2年後に迫った2020年東京オリンピック・パラリンピック。開催地の懸念材料のひとつが、宿泊施設不足だ。訪日外国人増加をめざす観光政策もあり、国内では大都市圏を中心に宿泊施設の新設計画が着々と進行している。だがオリンピック期間中の3週間余りは東京オリンピック・パラリンピックがすでに関係者向けに4万6000室を確保しており、一時的に供給不足が起こる可能性が高い。みずほ総合研究所では、2020年のホテル需給予測のレポートを定期的に発表し、動向を注視している。調査を担当する同所・主任エコノミストの宮嶋貴之氏に聞いた。
2018/10/05
-

第3回 消火器で火災は消せません!
初期消火といえばまず身近にある消火器ですね。しかし、消火器ではなかなか火が消せないんです。消火器で消火できる火災はほんとうに初期の、初期のものだけです。それでも、その場で消さないとたちまち火が大きくなってしまう。ですから、初動が極めて重要になるのです。
2018/10/02
-

「黎明の鐘」となれ!~<日本マラソンの父>金栗四三と恩師・嘉納治五郎~
2年後に東京オリンピック大会を控えて、戦前オリンピック大会初出場をはたした金栗四三(かなぐり しぞう、1891~1983)を語りたい。同時に師・嘉納治五郎との師弟愛にも触れたい。(金栗四三には、「かなくり しそう」との呼び方もある)。金栗を知らない読者も少なくないのではと考え、その功績を略記する。彼は近代日本を代表する名マラソン選手で、師範学校教師、熊本県初代教育委員長など公職を歴任した。箱根駅伝の実現に尽力し、日本に高地トレーニングを導入した。日本マラソン界の発展に大きく寄与するなど、日本の「マラソンの父」と称される(全国マラソン連盟会長、日本陸上競技連盟顧問でもあった)。
2018/10/01
-

都水道局、五輪向けテロ対策本格化
水を約1300万人の都民がいる首都に供給する東京都水道局。2020年東京オリンピック・パラリンピックを前に、テロ対策を進めていく中で情報の公開を絞っているという。同局の取り組みを取材した。
2018/10/01
-

私たちの周りのセキュリティ「モノ」(2)ボラード
8月の連載から私たちの周りにあるセキュリティ「モノ」についてお話をしています。今月はボラードについて説明します。
2018/09/28
-

<戦前最長>野田醤油労働争議と<関東大震災時>の福田村虐殺事件
私は柏市に転居して以来、柏市はもとより隣接する野田市・我孫子市など(東葛飾地方)の歴史に関心を持ってきた。野田市関連では、戦前最長の218日にも及んだ野田醤油(現キッコーマン株式会社)の労使紛争と関東大震災時に発生した福田村虐殺事件(当時の香川県三豊郡、現観音寺市および三豊市の薬売り行商人15人のうち、妊婦や2歳、4歳、6歳の幼児をふくむ9人が斬殺された事件。妊婦の胎児を含め10人とする見方もある)に強くひかれるものがあった。2つの事件は、地元野田市ではタブー視するか「黙して語らない」傾向にあった。
2018/09/25
-
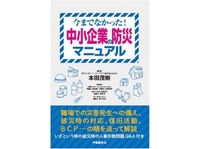
企業防災の要点、人事労務問題を平易に解説
地震・台風・豪雨など、今年も大きな自然災害が続き、市民生活だけでなく、企業活動にも少なからぬ影響をもたらしている。7年半前の東日本大震災をきっかけに、企業において防災マニュアルやBCP(事業継続計画)を策定する動きが急速に広がっているが、中小企業では未だ対応が遅れている現状がある。今年6月に発刊された同書は、こうした中小企業がゼロから防災対策を始められるための入門書。企業に求められる防災対策の基本事項から、被害を受けた拠点の早期復旧に至るまで一連の流れを時系列で押さえるとともに、その後の展開に必要となるBCPについても解説する。
2018/09/18
-

五輪で通勤や物流の混雑対策、企業は必須
2020年東京オリンピック・パラリンピックは、選手・関係者の移動で主に選手村から競技会場への移動でバスが調達台数で約2000台、乗用車は約4000台が必要と見込まれている。選手や関係者の移動は自動車、観客は主に鉄道。東京都、内閣官房、大会組織委員会では混雑緩和に向けた取り組みを「2020TDM推進プロジェクト」として民間にも協力を呼びかける。また道路や鉄道の混雑具合の予想として「混雑マップ」の作成も行う。
2018/09/18
-

第2回:自動運転車の登場で交通事故は減るか?
よく晴れた休日の朝、朝食を終えたあなたは、自宅の車庫に待機している自分で充電し終えたばかりの「自動運転車」に話しかける。「今日は絶好のドライブ日和だなあ。僕ら家族をどこかリフレッシュできる場所に連れていってくれないか?」。すると自動運転車は答える。「東名を通って箱根方面はいかがでしょう? 今日なら富士山もよく見えますよ…」。
2018/09/13
-

火災防御のタイムラインについて。Time is Life (時は命なり)
火災防御は時間との闘いだ。先着隊の初動が早ければ早いほど、救命率は上がる。要救助者が怪我をしていれば悪化を予防し、被災していない財産を守ることが出来る。 だが、火災防御力を上げるための訓練施設は限られている。昔のように古タイヤや廃材を訓練棟内で燃やして、黒煙を出すことも出来ない。スモークマシンによる白い煙と水は出せたとしても、実火災の熱や濃煙を体験できる施設は少ない。
2018/09/12
-

【講演録】国際的大規模イベントのセキュリティ対策
東京2020オリンピックは2020年7月24日に開幕し、33競技339種目で競われます。参加する選手は最大1万1090人。8月25日開幕の東京2020パラリンピックは22競技、540種目で選手数の最大4400人です。 1964年の東京オリンピックと比較すると、種目数は163から339とほぼ倍になっているにも関わらず、全体日程は2日間しか延びていません。東京2020オリンピック・パラリンピックは、規模が大きいだけではなく日程的にかなり過密で複雑なイベントになっています。
2018/09/11
-

りんかい線、コミケの経験五輪に生かす
2020年東京オリンピック・パラリンピックの会場が多く置かれる東京都の湾岸エリア。オリンピックは全42競技会場のうち14会場と中央区晴海に選手村、江東区有明の東京ビッグサイトにはメディアセンターが置かれる。このエリアの輸送で大きな役割を担うのが、東京臨海高速鉄道が運営するりんかい線だ。りんかい線は3日間で50万人近い参加者をビッグサイトに集める「コミックマーケット(以下コミケ)」で大人数が一度に集まるイベントの経験を積んでいる。
2018/09/11
-

第2回 昭和のバケツリレーに秘訣あり!
火災は人間が唯一防げて、コントロール可能な災害なのです(だから防火防災なのです)。江戸時代は水道などないわけで水が貴重であるためほとんど水による消火はなかったようです。さすまたは防犯用ではなく火災時の破壊道具として使われることもありました。ですから、消防署の地図には、さすまたのマークが使われていますよね。
2018/09/11
-

【講演録】「想定外」を乗り越える、多層リスク管理を
企業がリスクマネジメントを考える際、日本では地震・火災・事故・テロ・感染症など、被害の上流にある「原因」まで遡って対策をとることが多くあります。実際、火災が起きたあとの対策を考えるよりも、火事が起きない準備をすることが一番効果が高いのです。
2018/09/10



















![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)



