-

お笑い芸人赤プルと共に学ぼう!ちょっくら防災!
防災備蓄を今のうちに見直していくべ
「防災備蓄ってどこに置いたらいいんですか?」。3年前に答えられなかった質問に、いまこそ赤プルさんが答えます。ポイントの一つは、ご家族がどういう生活スタイルなのか、もう一つはその家にどういう災害リスクがあるのか。つまり備蓄品の置き場を決めるには、この二つを確認しなければなりません。それはご家族の防災意識を高めるだけでなく、日々の生活環境の改善にもつながります。
2020/08/06
-

知って得する気象・防災知識
避難の心得 基本編③水害・内水氾濫について
「令和2年7月豪雨」は、九州や中部地方などに甚大な被害をもたらしました。さらに今年は平年より長い梅雨となり、全国の広い範囲で水害が発生しています。雨のシーズンは秋まで続くうえ、梅雨明け後は局地的に降る強い雨が多くなる時期。「内水氾濫」への警戒と備えをぜひ確認しておいてください。
2020/08/05
-
予測できない豪雨災害の増加と、自助・共助・公助の限界を補う「新しい」防災のあり方
線状降水帯の発生など、予測の難しい豪雨災害が近年増えています。一方で、高齢化や過疎化などにより防災の基本である「自助・共助・公助」はいずれも限界を迎えつつあります。そのような状況下における、新たな防災のあり方を考えてみます。
2020/08/02
-

アウトドア防災ガイド あんどうりすの『防災・減災りす便り』
そのハザードマップで避難できますか?
2020年7月、各地で豪雨による甚大な被害が出ています。そして、中小河川についてはまだハザードマップ 化されていない地域もあるものの、大河川については、ハザードマップの想定に近い浸水となっていると事後に検証されることが増えています。みなさんはハザードマップを読み込んでいますか?今週は、避難を後押しできるハザードマップについて検証します。
2020/07/20
-

知って得する気象・防災知識
避難の心得 基本編②水害・河川氾濫について
日本列島は出水期(6月~10月)がスタートしています。6月下旬から7月にかけては梅雨末期の大雨、8月以降は台風や秋雨前線で災害につながる大雨など、これから水害への万全の対策が必要な時期です。「水害」には大きく分けて「河川氾濫」と「内水氾濫」があります。今回は「河川氾濫」の基本的な知識を解説します。
2020/07/06
-

緊急特別寄稿熊本豪雨 老人福祉施設の避難を再考せよ
7月4日早朝、球磨村の特別養護老人ホーム「千寿園」で14人が心配停止状態となって病院に搬送された。7時間で600ミリも降る大変な豪雨で、深夜未明という時間帯、立地はハザードマップでは浸水深10m超、夜間配置の職員が実際に何名いたかはわからないが、50名もの要介護高齢者を少人数で安全に移送するのは不可能だったはずだ。そうなると、この災害の主な原因は、このようなリスクの高い場所に要介護高齢者の入居施設の建築が認められてしまう法制度にあるのではないか。これを教訓に福祉施設の避難について考えたい。
2020/07/05
-

お笑い芸人赤プルと共に学ぼう!ちょっくら防災!
コロナ時代の避難 逃げ遅れなくすためにできること
緊急事態宣言が解除され、防災士赤プルさんも活動再開しました。梅雨入りした日本列島では、心配していた豪雨の被害がすでに発生。メディアも盛んに水害特集を組んで注意を呼びかけています。現在は新型コロナウイルス感染の影響で避難の在り方が変わってきていますから、今まで以上に備えておきましょう。
2020/07/03
-

コロナ禍は避難所の環境を改善する好機初動体制も見直し 長年の課題今こそ改革
熊本県益城町は5月下旬、感染症に対応した避難所運営訓練を全国に先駆けて実施。その検証結果をふまえ、6月上旬には職員を対象とする訓練を行った。もともと避難所の環境改善は同町の重点テーマ。「どの道やるべきことがコロナ禍で前倒しされた」と、危機管理監の今石佳太氏は話す。避難所の改善は避難のあり方や初動体制とも無関係ではなく、それらは阪神・淡路大震災以降変わらない課題。自治体の改革の動きをリポートした。
2020/07/03
-

アウトドア防災ガイド あんどうりすの『防災・減災りす便り』
痴漢防止アプリで避難所を性暴力から守る!
避難所での性暴力は現実の問題です。加害者が悪いことは当然にもかかわらず、被害を訴えることができない被害者も少なくありません。そこでアプリを使った新しい避難所運営を提案します。
2020/06/23
-

福祉と防災
福祉防災計画作成ガイド改訂 避難の内容を大幅充実
福祉施設が災害時にも高齢者や障がい者、乳幼児等を支援するためには「福祉防災計画」が必要。その中核となるのがBCPです。私たちは東日本大震災後、被災地の福祉施設職員らとの協働によりBCPのひな型を作成しましたが、このほど従来の研修テキストを改訂し、7月1日に「ひな型でつくる福祉防災計画~避難確保計画からBCP、福祉避難所~」を発刊します。
2020/06/23
-

葛西優香の23区防災ぶらり散歩
第22回【特別編】再考 コロナ禍における避難
東京23区の「その区ならでは」の取り組みをお伝えしている「23区防災ぶらり散歩」。今回は特別版として、コロナ禍における避難について、各区で区民から疑問の声があがり始めている中、提言を出された日本災害情報学会 企画委員会 委員 磯打千雅子先生にお話を伺いました。「自身にとっての最適な避難とは?」。今一度、考える時が来ています。
2020/06/16
-

平常時と災害時の両用可能な避難時用マット
古河電気工業はこのほど、壁緩衝材・床マット・パーティションの3つの機能を有する発泡ポリエチレン製『スキルフリー避難時用マット』を開発した。体育館等の避難所において、平常時は緩衝材として壁に設置し、災害時は壁から取り外してその場で簡単に組み立て、断熱用床マットやパーティションとして利用できるもの。快適性、プライバシー、ソーシャルディスタンス等を確保し、避難所生活の環境改善に貢献する機能製品として提案する。7月の販売開始を予定する。
2020/06/02
-

アウトドア防災ガイド あんどうりすの『防災・減災りす便り』
今日を愛し、明日に備える水害避難マンガ
新型コロナウイルスとどう向き合うかが今の社会の大きな課題です。水害シーズンが迫る中、こういうときだからこそきちんと備えたいもの。東京・江戸川区の有志が水害への備えをわかりやすくまとめたマンガを作りました。
2020/05/25
-

昆正和のBCP研究室
第21回:気候変動と私たちの危機意識
昨年、姫路市が夏場のエアコンの設定温度を28℃から25℃に下げる実証実験を行い、その結果、残業が14%減って職員の8割強が「作業効率が上がった」と答えたそうである。この発表を受けて、ネット上にはさまざまな意見が飛び交っていた。「28℃の科学的根拠なんてなかったのだ」「今まで28℃でがまんして損をした」「28℃にこだわる必要なんてない!」といった声も少なくなかった。
2020/01/09
-

昆正和のBCP研究室
第20回:「避難」をめぐるBCP的考察(その2)
前回は火災からの避難について取り上げた。同じ避難でも、自然災害の避難となると、企業はまた別の手順を考えなくてはならない。ここでは主に地震を想定した「訪問先での避難」「避難支援が必要な社員への対応」「避難用アイテム」の3つの側面から考えてみよう。
2019/12/19
-

アウトドア防災ガイド あんどうりすの『防災・減災りす便り』
冠水道、夜だとクルマで突っ込むワケ
10月の台風19号では、亡くなった方の4分の1にあたる21人が車での移動中の車中死であったと、報道されています。
2019/12/06
-

昆正和のBCP研究室
第19回:「避難」をめぐるBCP的考察(1)
災害が発生した時、BCP(事業継続計画)の最も初期の行動として重視されるのが、「いかにして社員の命を守るか」に関する手順、いわゆる初動対応や緊急対応と呼ばれるステップである。従来的な表現で言うところの「防災マニュアルに記載された手順」のことだ。
2019/12/05
-

アウトドア防災ガイド あんどうりすの『防災・減災りす便り』
台風で早期避難、自立生活センターの苦悩
各地で猛威をふるった台風15号、19号、21号。逃げ遅れによる被害も多々ある中、台風3日前には広域避難も含め、避難のためにできる策を実施した自立生活センターがあります。
2019/11/01
-
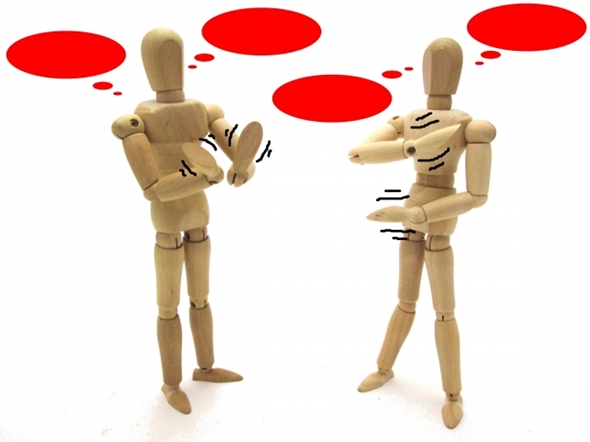
当事者防災研究会~要配慮者が自ら助かるための知恵と工夫~
聴覚障害者のヒアリングサポート「CPR」
災害時、さまざまな聴覚障害を持つ方々に急性期における避難誘導を行う際、どういうアプローチの仕方が有効なのかを調べてみた。
2019/06/27
-

離れた家族の地域の避難情報SMS通知
KDDIと沖縄セルラーは28日、登録した希望地域の災害・避難情報を携帯電話のSMSで受け取ることができる「登録エリア災害・避難情報メール」のサービスを7月4日から開始すると発表した。利用は無料。ユーザーから離れた地域に住む家族や知人に対する避難の誘導などを図る。
2019/05/28
-

アウトドア防災ガイド あんどうりすの『防災・減災りす便り』
防災情報はUD(ユニバーサルデザイン)フォントで!
令和時代になりました。同じ大きさの以下の元号、ぱっと見で見えやすいのはどちらでしょう?
2019/05/10
-

お笑い芸人赤プルと共に学ぼう!ちょっくら防災!
猫との避難について真剣に考えてみた
今回のタイトルのきっかけは、茨城県の動物指導センターにお邪魔したことです。以前からお世話になっている県庁の方が、動物指導センター担当だったためお声がけいただき、特別に視察させてもらいました。
2019/04/11
-

福祉と防災
第2回 福祉施設の防災力向上(2)
2016年8月30日、台風10号により岩手県岩泉町高齢者グループホーム「楽ん楽ん」で9人全員の高齢者が水害で亡くなり、社会に大きな衝撃を与えました。現地に行ってみると、隣地には大きな工場があります。仮に、平常時から施設と合同で避難訓練をしていたならば、きっと高齢者の避難を支援してくれたのではないでしょうか。また、福祉施設も工場に避難支援を頼めたのではないでしょうか。
2019/03/22
-

福祉と防災
最大リスクに備えた実効性ある計画・訓練
今月から「福祉と防災」について連載を始めます。私は、自治体職員の時に防災課、福祉事務所等を経験し、それ以来、福祉と防災をライフワークにして活動しています。
2019/02/28
-

台風時、雨が降り始めてからの避難情報では遅すぎる
8月25日頃にマーシャル諸島近海で発生した低気圧は28日9時、南鳥島の近海で台風となり、チェービー(Jebi)と命名された。8月に発生した台風の数は9個となり、1951年の統計開始以来2番目に多い数である。台風21号は速いペースで発達し31日9時には猛烈な勢力に達した。台風は北西に進み、その後北向きに進路を変え、9月4日正午頃に非常に強い勢力で徳島県南部に上陸した。上陸時の中心気圧は950hPa、最大風速は45m/sで、高知県室戸市室戸岬では最大風速48.2m/s、最大瞬間風速55.3m/s、大阪府田尻町関空島(関西国際空港)では最大風速46.5m/s、 最大瞬間風速58.1m/sとなるなど四国地方や近畿地方では猛烈な風を観測し、観測史上第1位となったところがあった。
2018/10/09
















![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)





