色と多言語表記を考える
ピクトグラムのメリットとデメリット

藤代 洋行
ピクトグラムアーティスト、甲種防火・防災管理者、防災士。ピクトグラムアートは世界初! 知的財産権(著作権・動き商標・商標)+知的財産権保護(著作権・確定日付)を取得しています。「動き商標」と「商標」をベースにしたデジタルアート作品です。伊勢屋グループの代表(Pictogram Art、手話指文字・点字アート、Origami Art、障害者コンサルタントコズミック、SOHOしあわせのハコ)
2020/02/07
防災とピクトグラム

藤代 洋行
ピクトグラムアーティスト、甲種防火・防災管理者、防災士。ピクトグラムアートは世界初! 知的財産権(著作権・動き商標・商標)+知的財産権保護(著作権・確定日付)を取得しています。「動き商標」と「商標」をベースにしたデジタルアート作品です。伊勢屋グループの代表(Pictogram Art、手話指文字・点字アート、Origami Art、障害者コンサルタントコズミック、SOHOしあわせのハコ)
この連載では、防災や危機管理におけるピクトグラムを使ったコミュニケーションについて、ピクトグラムのメリットとデメリットを、具体的な事例を用いながら解説し、効果的なピクトグラムを使った表現方法を考えてみたいと思います。
ピクトグラムのメリットは、事前の学習や特別な知識がなくても理解できることです。文字を使わなくても、見て直感的に情報を伝えられる視覚記号(サイン)なので、目の見えづらくなった高齢者、漢字が苦手な子ども、外国人、一部の障害者など文字の読めない人にも情報を伝えられることです。

非常口のピクトグラムの色を見て気になりませんか? 人は無意識のうちに色から大きな影響を受けています。しかし、「色が目立てばいい」ということではありません。
例えば、非常口は、緑色に白色の2色。消火器は、赤色に白色の2色です。安全標識は、遠くからでも容易に「禁止」「安全」などの指示内容が一目で認識できなければなりませんが、その認識性はデザインと色使いに左右されます。対応する国際標準との整合を保ちつつ、多様な色覚を持つ人々の安全標識に対する認識性を向上させるため、JIS Z 9103(図記号-安全色及び安全標識-安全色の色度座標の範囲及び測定方法)があります。
https://www.meti.go.jp/press/2018/04/20180420006/20180420006.html

安全色彩とは、安全上必要な個所を識別しやすくするために使用する色彩です。JISに規定される安全色は、赤、黄赤、黄、緑、青、赤紫に、対比補助色として白、黒を加えた8色です。意味は以下の通りです。
1.安全色:赤
意味:防火、禁止、停止、高度の危険
2.安全色:黄赤
意味:危険、航海・航空の保安施設
3.安全色:黄
意味:注意
4.安全色:緑
意味:安全、避難、衛生、救護、進行
5.安全色:青
意味:指示、用心
6.安全色:赤紫
意味:放射能
7.安全色:白
意味:通路、整頓
8.安全色:黒
意味:文字・記号・矢印などに使用、黄赤・黄・白の補助色
このように、視覚記号(サイン)に合わせて色でも情報を伝えているのです。
ピクトグラムのデメリットは、イメージでしか意思疎通が図れないことです。非常口やトイレなど大まかな場所を伝えるには適しています。しかし、注意など危険が及ぶものは、文字や音声などで欠点を補う必要があります。

例えば、津波注意のピクトグラムを見てどう感じますか? 津波注意のピクトグラムがあるから、この地域では津波があるかもしれない。波の向きが右向きだから左側が海であろうなど予想になるので、これだけでは情報は分からない方が多いと思います。もしかしたらこの津波注意のピクトグラムを見て全く違うことを連想させているかもしれません。
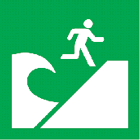
津波避難場所のピクトグラムでもまだ不十分ですが、津波からの避難啓発などにも見えるので少しは違うのではないかと思います。これも残念ながら、この津波避難場所のピクトグラムを見て全く違うことを連想させているかもしれません。
おすすめ記事

新任担当者でもすぐに対応できる「アクション・カード」の作り方
4月は人事異動が多く、新たにBCPや防災を担当する人が増える時期である。いざというときの初動を、新任担当者であっても、少しでも早く、そして正確に進められるようにするために、有効なツールとして注目されているのが「アクション・カード」だ。アクション・カードは、災害や緊急事態が発生した際に「誰が・何を・どの順番で行うか」を一覧化した小さなカード形式のツールで、近年では医療機関や行政、企業など幅広い組織で採用されている。
2025/04/12



防災教育を劇的に変える5つのポイント教え方には法則がある!
緊急時に的確な判断と行動を可能にするため、不可欠なのが教育と研修だ。リスクマネジメントやBCMに関連する基本的な知識やスキル習得のために、一般的な授業形式からグループ討議、シミュレーション訓練など多種多様な方法が導入されている。しかし、本当に効果的な「学び」はどのように組み立てるべきなのか。教育工学を専門とする東北学院大学教授の稲垣忠氏に聞いた。
2025/04/10



リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2025/04/08



リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ
リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。
2025/04/05
※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方