2023/03/05
インタビュー
どうすれば持続可能な建築・まちをつくれるか
工学院大学建築学部まちづくり学科 久田嘉章教授に聞く
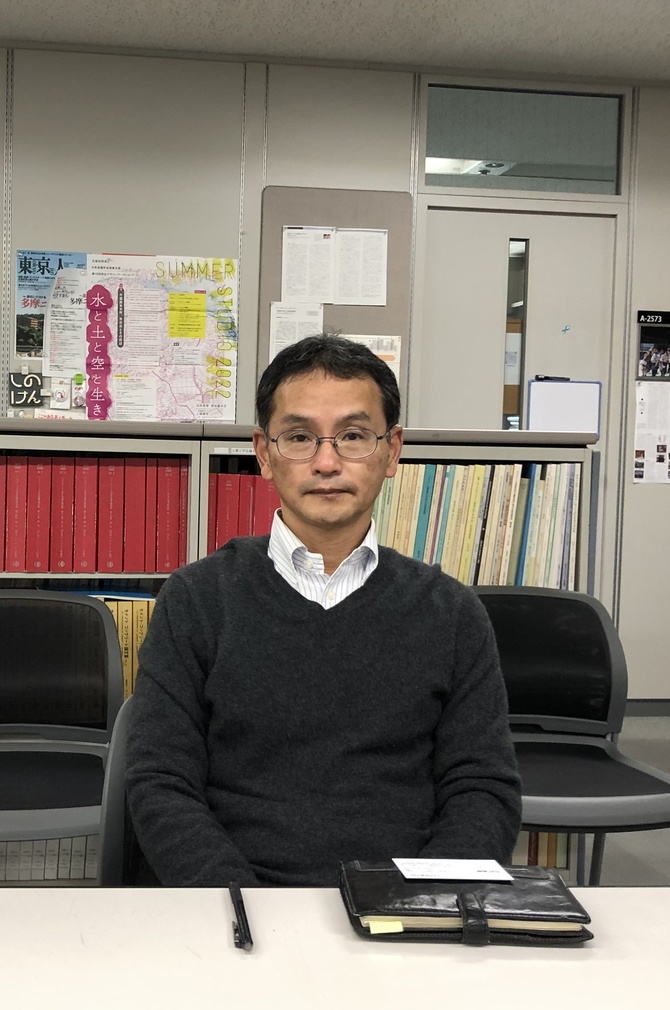
久田嘉章氏 ひさだ・よしあき
1984年早稲田大学理工学部建築学科卒業、89年同大学・研究助手、93 年南カルフォルニア大学地球科学科研究助手。95年から工学院大学工学部建築学科専任講師、助教授を経て、2003 年同教授、11 年同大学建築学部まちづくり学科教授。著書に「建築の振動-初歩から学ぶ建物の揺れ」(共著、朝倉書店)、「逃げないですむ建物とまちをつくる ―大都市を襲う地震等の自然災害とその対策」(共著・日本建築学会編、技報道出版)など。工学博士、専門は地震工学、地震防災。

トルコ南部のシリア国境付近で2月6日に発生したマグニチュード8に近い巨大地震とその後の揺れによる死者は両国合わせて5万人を超えた。プレート境界でひずみが溜まりやすい地域。長大な活断層が大きく動き、多くの建物が「パンケーキクラッシュ」と呼ばれる脆い倒壊を起こした。同じ地震大国の日本も他人事ではなく、特に住居・オフィス利用が始まってまだ歴史が浅い高層建築は、さまざまな面で安全性へのリスク評価が明確に定まっていない。工学院大学の久田嘉章教授に、日本の高層建築の地震対策についてハード・ソフト両面から聞いた。
建物を大きく変形させるパルス状の強震動
――トルコ・シリア地震で「パンケーキクラッシュ」があれほど発生したのはなぜですか?
パンケーキクラッシュは低層階の柱がつぶれ、そこに上階のスラブが次々と折り重なるように崩れ落ちていく破壊現象です。柱が弱いうえ、梁との接合部もおそらく弱いと推測します。
建築の耐震設計は、どこかが一気につぶれるような脆弱な壊れ方をしないようにするのが基本。特に高層建築では2段階設計法といって、一次設計は中規模の地震に対し構造部材が損傷しないことを確認する、二次設計は極めてまれな大地震に対し構造部材は損傷するも倒壊はしないことを確認する。つまり、規模の大きな地震に対してはさまざまな部材をバランスよく壊し、その間にエネルギーを建物全体に分散して吸収するという考え方に立っているのです。
低層階の柱が壊れると、建物が一気に崩壊する危険が高まります。なので、そうならないようにまず各階の梁から壊す。そこでエネルギーを吸収し、脆弱な破壊は起こさせない。この考え方は、高層建築であればRC(鉄筋コンクリート)造もS(鉄骨)造も同じです。
トルコの耐震基準は日本とほぼ同等ということですが、1999年のイズミット地震によって見直されたものですから、比較的新しい。現行基準以前の建物がまだ数多く残っていたと考えられます。
あとは、これは報道で知る限りですが、違法建築や手抜き工事で多くの逮捕者が出ています。仮に新しい建物でも、設計基準どおりにつくられていたのかどうか定かでない。ただ、間違いなくいえるのは、最大規模の内陸直下地震による地震動が極めて強かったということです。

――地震動が強く、かつ、RC 造と相性の悪い周期だったのでしょうか?
まず、内陸の活断層でマグニチュード(M)7.8 というのは、すさまじい地震です。阪神・淡路大震災の20倍以上のエネルギーといわれていますが、規模からいうと関東大震災と同じくらい、活断層の大きさで比較すれば日本で最大級とされる1891年の濃尾地震より一まわり大きい。当然、地震動は強いわけです。
このように大きな地震は、地震動に長周期の成分を多く含みます。なかでも建築にとって怖いのは、揺れが短時間で急激に脈打つパルス状の強震動。ガタガタという連続の振幅とは違い、1波、2波がドーンと来るイメージです。特に周期1~2秒のパルス状の地震動は「キラーパルス」と呼ばれ、建物を大きく変形させる力を持っています。
阪神・淡路大震災では、活断層近傍の「強震動生成域」と呼ばれる領域から数波のキラーパルスが出て、明石海峡から神戸に向かって破壊が伝播しました。周期1秒前後のパルス波が古い木造や中低層のRC造・S造を壊し、揺れの地盤増幅がダメージを拡大、さらに火災も発生して、大災害となったわけです。
トルコ・シリア地震も震度に換算すると一部で震度7が襲ったとみられ、キラーパルスも確認されています。横ずれ断層の場合、キラーパルスが出るのは一般的に断層直行方向です。阪神・淡路大震災で構造物の倒壊が南北方向に偏ったのはそのため。トルコでも、パンケーキクラッシュをあれほど引き起こした主要因は、活断層近傍からのパルス波による強震動の可能性が考えられます。
インタビューの他の記事
おすすめ記事
-

自社の危機管理の進捗管理表を公開
食品スーパーの西友では、危機管理の進捗を独自に制作したテンプレートで管理している。人事総務本部 リスク・コンプライアンス部リスクマネジメントダイレクターの村上邦彦氏らが中心となってつくったもので、現状の危機管理上の課題に対して、いつまでに誰が何をするのか、どこまで進んだのかが一目で確認できる。
2025/04/24
-

-

常識をくつがえす山火事世界各地で増える森林火災
2025年、日本各地で発生した大規模な山火事は、これまでの常識をくつがえした。山火事に詳しい日本大学の串田圭司教授は「かつてないほどの面積が燃え、被害が拡大した」と語る。なぜ、山火事は広がったのだろうか。
2025/04/23
-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2025/04/22
-

帰宅困難者へ寄り添い安心を提供する
BCPを「非常時だけの取り組み」ととらえると、対策もコストも必要最小限になりがち。しかし「企業価値向上の取り組み」ととらえると、可能性は大きく広がります。西武鉄道は2025年度、災害直後に帰宅困難者・滞留者に駅のスペースを開放。立ち寄りサービスや一時待機場所を提供する「駅まちレジリエンス」プロジェクトを本格化します。
2025/04/21
-

-

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視
4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。
2025/04/15
-

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入
日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。
2025/04/15
-

-

生コン・アスファルト工場の早期再稼働を支援
能登半島地震では、初動や支援における道路の重要性が再認識されました。寸断箇所の啓開にあたる建設業者の尽力はもちろんですが、その後の応急復旧には補修資材が欠かせません。大手プラントメーカーの日工は2025年度、取引先の生コン・アスファルト工場が資材供給を継続するための支援強化に乗り出します。
2025/04/14







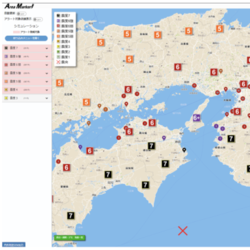














![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)






※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方