2015/11/25
誌面情報 vol52
洪水直後から現地で支援
茨城県常総市の鬼怒川決壊や宮城県大崎市の渋井川の決壊の被害によって、水と泥により汚染された産業機械や生産設備を救った企業がある。被災した機械や精密機器の復旧を専門とするベルフォアジャパン株式会社だ。
同社は浸水によって泥にまみれた機械や設備機器、精密機械を洗浄し、復旧させるサービスを提供している。鬼怒川、渋井川が決壊した翌日には提携している東京海上日動火災保険株式会社の栃木、茨城、宮城の拠点に入り、現地調査を開始した。同社の滝川直人社長は「ある機械部品の製造工場では約1m50cmまで水没し、被害は予想を超えていた。お客様はかなり疲弊していました」と振り返る。水害から機械や設備機器を救い出すには刻一刻と進む腐食との競争になる。
ベルフォアジャパンはドイツに本拠地を置くベルフォアグループと東京海上日動火災保険との共同出資により2004年に設立された。台風や集中豪雨、津波などの水害や火災による腐食や化学物質の付着、スス汚染などをドイツで開発された特殊な洗剤で洗浄し、腐食やダメージを受けた機械や設備を再生させる災害復旧専門の企業だ。被災した企業にとっては、新たに機械や設備を購入し直す必要がなくなり、通常なら数カ月かかる事業再開までの期間を短縮できるとあって、まさに「救いの手」となる。

現地調査から復旧までの手順
まず、被災地に駆けつけて実施するのが現地調査。工場などで機械や設備を徹底的に調べ、洗浄などで修復、再生可能なものを選別しオーナーや工場の責任者に伝える。火災現場ではQT(クイックテスト)という特殊な試験紙を20秒ほど汚染した機器の表面などに押しつける。まるでリトマス試験紙のようにQTの色変化によって消火剤や燃えた合成樹脂由来のハロゲン系の汚染物質の濃度を判定し、復旧の可否を判断する。復旧のファーストステップとして素早い調査と適切な判断が必要とされる。
調査によって復旧できる機械や設備を選別すると、腐食の進行を防止する暫定的な作業に入る。一般的に調査直後に復旧作業を開始するケースは少ない。というのも、まずは各企業で復旧計画が検討されるからだ。復旧作業にゴーサインが出るのは具体的な計画が決定された後になる。とはいえ、待機期間にも腐食が進むので早急の対応が必要になる。
高圧洗浄機を使って機械に付着した泥や汚染物質を水で洗い流す予備洗浄では、やみくもに水を吹き付けるのではなく、洗浄する機械や設備に応じた方法がとられる。表面上の汚染だけでなく、必要ならば機械を分解し、汚染を除去する。一般的にはこの後は自然乾燥させるが、自然乾燥だと腐食が進行するケースは少なくない。機械や設備の表面と空気とが反応するからだ。特に湿度が50%を超えると、腐食速度が急激に上昇し、錆が目立つようになる。そのため、予備洗浄後に湿度を厳密にコントロールし、防錆剤でコーティングして腐食の進行をくい止める。ベルフォアではこの一連の暫定的な作業を緊急安定化と言う。
緊急安定化の後に、各企業で事業再開に向けた具体的な復旧方針が決まると本洗浄に入る。予備洗浄では落としきれない汚染物質を洗い流し、腐食の進行を止める。マーケティング部の高橋言幸氏は「一般的な洗浄では腐食の進行を止めることは難しい。ベルフォアなら独自に開発した約50種類の洗浄剤を腐食の種類や状況に合わせて使い分け、腐食の進行を止めることができる」と高い技術力に胸を張る。最適温度に暖められた洗浄剤を高圧洗浄機で吹き付け、化学反応で腐食物質を中和し、物理的な水圧で汚染物質と洗浄剤を洗い流す。長期間にわたる水没でひどく錆付いた金属部品であっても、錆取り剤と超音波洗浄などを組み合わせた方法で錆を落とすことも可能だ。大型の超音波槽を備えているため、大型の機械にも十分対応できる。ドライアイスを吹き付け、汚染物質を急激に冷却して除去するアイスブラスターという方法をとることもある。本洗浄が終わると乾燥機で乾燥させる。
精密機械の復旧も

製造機械だけでなく、電子基板が組み込まれた精密機械の復旧も得意とする。実は、電子機器の汚染耐性は高く、被災時に通電していなければ復旧できるケースは多いという。ノズルを巧みに操り、電子基板上の細部まで洗浄し、汚染を除去するために使う刷毛も静電気が起こらない豚の毛を使うなど、念には念をいれて対応する。
続いて塩化物イオンなどの残存を防ぐために水道水ではなく純水で洗い流し、その後は55℃に設定したテントの中で一晩かけて乾燥させ、水をじっくり飛ばす。最後に真空乾燥機を使って完全に乾燥させる。平地に比べ気圧の低い標高の高い山では沸点が降下するように、真空乾燥機を使って気圧を下げると水の沸点が55℃になる。結果、電子基板にほとんど負担のかからない温度で水を完全に蒸発させることができるのだという。
7社の企業を支援
今回の災害でベルフォアが調査した件数は約50件。実際に作業に入ったのは7社で、内訳は金属精錬や研磨、製紙、プラスチック製造に関わる機械や設備から一般的なオフィスまで幅広い。
世界各国で災害復旧の現場で身を投じるベルフォアは約26カ国に300以上の拠点があり、グローバルなネットワークによって、ひとたび大規模災害が起こると世界中に技術者の「国際動員」がかかる。東日本大震災の際にも世界各国から数十人が来日。日本の製造業も大打撃を受けた同年のタイ大洪水では日本からも技術者が派遣され約100人が作業に入った。洗浄のための機材は世界中で同じものが使われ、表記も英語で統一されている。洗浄機や浴槽、ポンプなどはサイトキットと呼ばれるスチール製のボックスにまとめられ、運搬して現地で展開し同等の作業ができる体制になっている。
世界中のベルフォアグループを合わせると年間で9万5000件を超える復旧作業に携わっている。ベルフォアジャパンへの依頼件数は飛躍的に伸びているという。社長の滝川氏は「水災では物理的ダメージがなければ機械系の復旧はほぼ100%可能。精密機械の電子基板も通電していなければ高い確率で復旧できる」と話している。
おすすめ記事
-

自社の危機管理の進捗管理表を公開
食品スーパーの西友では、危機管理の進捗を独自に制作したテンプレートで管理している。人事総務本部 リスク・コンプライアンス部リスクマネジメントダイレクターの村上邦彦氏らが中心となってつくったもので、現状の危機管理上の課題に対して、いつまでに誰が何をするのか、どこまで進んだのかが一目で確認できる。
2025/04/24
-

-

常識をくつがえす山火事世界各地で増える森林火災
2025年、日本各地で発生した大規模な山火事は、これまでの常識をくつがえした。山火事に詳しい日本大学の串田圭司教授は「かつてないほどの面積が燃え、被害が拡大した」と語る。なぜ、山火事は広がったのだろうか。
2025/04/23
-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2025/04/22
-

帰宅困難者へ寄り添い安心を提供する
BCPを「非常時だけの取り組み」ととらえると、対策もコストも必要最小限になりがち。しかし「企業価値向上の取り組み」ととらえると、可能性は大きく広がります。西武鉄道は2025年度、災害直後に帰宅困難者・滞留者に駅のスペースを開放。立ち寄りサービスや一時待機場所を提供する「駅まちレジリエンス」プロジェクトを本格化します。
2025/04/21
-

-

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視
4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。
2025/04/15
-

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入
日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。
2025/04/15
-

-

生コン・アスファルト工場の早期再稼働を支援
能登半島地震では、初動や支援における道路の重要性が再認識されました。寸断箇所の啓開にあたる建設業者の尽力はもちろんですが、その後の応急復旧には補修資材が欠かせません。大手プラントメーカーの日工は2025年度、取引先の生コン・アスファルト工場が資材供給を継続するための支援強化に乗り出します。
2025/04/14






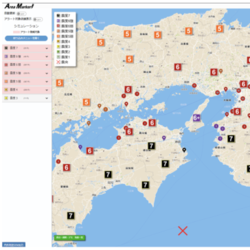














![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)






※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方