2015/05/25
誌面情報 vol49
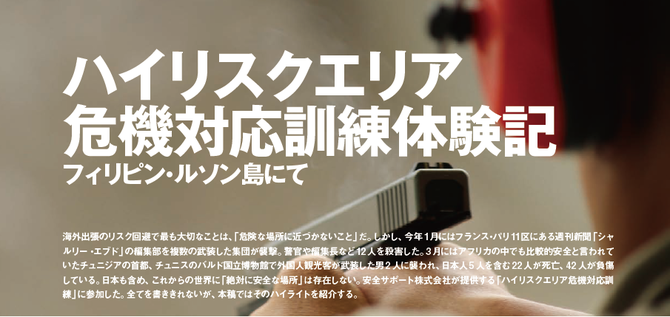
海外出張のリスク回避で最も大切なことは、「危険な場所に近づかないこと」だ。しかし、今年1月にはフランス・パリ11区にある週刊新聞「シャルリー・エブド」の編集部を複数の武装した集団が襲撃。警官や編集長など12人を殺害した。3月にはアフリカの中でも比較的安全と言われていたチュニジアの首都、チュニスのバルド国立博物館で外国人観光客が武装した男2人に襲われ、日本人5人を含む22人が死亡、42人が負傷している。日本も含め、これからの世界に「絶対に安全な場所」は存在しない。安全サポート株式会社が提供する「ハイリスクエリア危機対応訓練」に参加した。全てを書ききれないが、本稿ではそのハイライトを紹介する。
|
「Look Down!! Look Down!!」 (顔を下にしてうつむけ!) 突然バスが止められ、武装した覆面姿の男たちが乗り込んできた。私は両手を頭の後ろに組み、頭をさげた。抜き打ちで行われる「身代金目的誘拐訓練」が開始されたのだ。訓練の一環と分かっていても、車内に緊張が走る。 ハイジャック犯は、自分の顔を見られることを極度に嫌うとともに、まず人質を自分の支配下に置くために矢継ぎ早に、そして高圧的に命令を下す。全員にマスク とヘッドホンが付けられ、視覚と聴覚を奪われる。聞こえてくるのは犯人たちの怒号だけだ。そして一人ひとりを後ろ手にし、拘束具で固定する。  バスから降ろされ、道路にひざまずく。犯人は拙い英語で怒鳴るため、「Kneel!」が「ひざまずけ」を意味するものだと理解するのに、少し時間がかかった。人間はハイストレスにさらされると、視覚や聴覚が落ち、普段なら分かる英語 も聞き取れないことがあるという。しかし、危機が訪れた時に言語が通じないのは致命的だ。1992年にはアメリカで「Freeze!」(「動くな!」)と いう意味の単語がわからずに射殺された服部剛丈君の例もある*。ハイジャック犯やテロリストは人質を自分の支配下に入れるため、襲撃当初は必要以上に暴力 的になる。言葉が分からなかったために犯人の言動に従わず、 反抗的とみなされてしまえば、それだけで見せしめの意味も込めて殺害される危険性もある。 「目立たない人物になること」。テロリストに遭遇した場合に最も大切なことだ。 道路にひざまずくと、1分もたたずに膝から足首にかけて 痛みが走る。日ごろの運動不足が恨めしい。後ろ手を縛る拘束具も手首に食い込む。実は先刻までは「ここでブルース・ウィリスだったらどうするかな?」など と考えられるくらいの心の余裕があった。しかしまだ本番はこれからだった。長い時間が始まろうとしていた。 |
*1992年、当時高校生だった服部君は、留学生として米国ルイジアナ州に滞在中、現地のハロウィンパーティで間違った家を訪問してしまい、その家の家主に銃口を突きつけられて「Freeze!」(動くな!)と警告された。しかし彼はその意味がわからず、微笑んで「パーティに来たんです」と説明しながら近づいたところを撃たれ、出血多量により死亡した。
オーストラリア特殊部隊出身者による危機管理訓練

「ハイリスクエリア危機対応訓練」は、テロ・誘拐・銃撃戦・強盗といったリスクの高い地域に赴任する駐在員や出張者向けに設計された3日間のトレーニング・プログラムだ。ピストル実射訓練も含むため、フィリピン・ルソン島で開催され、トレーナーはオーストラリア特殊部隊出身者が務める。筆者は2015年3月下旬、訓練を受けるために成田空港から4時間半ほどのフィリピン・マニラ国際空港に降り立った。フィリピンは思ったほど暑くはなく、半袖だと少し肌寒いほどだった。
Day1
安全講習と応急処置、ピストル理論・実技
初日はまずホテル内の会場で安全講習から始まった。
誌面情報 vol49の他の記事
おすすめ記事
-

自社の危機管理の進捗管理表を公開
食品スーパーの西友では、危機管理の進捗を独自に制作したテンプレートで管理している。人事総務本部 リスク・コンプライアンス部リスクマネジメントダイレクターの村上邦彦氏らが中心となってつくったもので、現状の危機管理上の課題に対して、いつまでに誰が何をするのか、どこまで進んだのかが一目で確認できる。
2025/04/24
-

-

常識をくつがえす山火事世界各地で増える森林火災
2025年、日本各地で発生した大規模な山火事は、これまでの常識をくつがえした。山火事に詳しい日本大学の串田圭司教授は「かつてないほどの面積が燃え、被害が拡大した」と語る。なぜ、山火事は広がったのだろうか。
2025/04/23
-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2025/04/22
-

帰宅困難者へ寄り添い安心を提供する
BCPを「非常時だけの取り組み」ととらえると、対策もコストも必要最小限になりがち。しかし「企業価値向上の取り組み」ととらえると、可能性は大きく広がります。西武鉄道は2025年度、災害直後に帰宅困難者・滞留者に駅のスペースを開放。立ち寄りサービスや一時待機場所を提供する「駅まちレジリエンス」プロジェクトを本格化します。
2025/04/21
-

-

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視
4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。
2025/04/15
-

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入
日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。
2025/04/15
-

-

生コン・アスファルト工場の早期再稼働を支援
能登半島地震では、初動や支援における道路の重要性が再認識されました。寸断箇所の啓開にあたる建設業者の尽力はもちろんですが、その後の応急復旧には補修資材が欠かせません。大手プラントメーカーの日工は2025年度、取引先の生コン・アスファルト工場が資材供給を継続するための支援強化に乗り出します。
2025/04/14





















![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)






※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方