2011/09/25
誌面情報 vol27
隠れた情報を見抜く力
危機発生時における状況判断
対談
前東京消防庁警防部長 佐藤康雄氏 × 前東京都総務局総合防災部情報統括課長 齋藤實氏
危機発生時においては、指揮者の迅速で的確な状況判断が求められる。特に消防などの第一線では、その判断1つで地域全体の明暗を分けることもある。
東日本大震災で緊急消防援助隊東京都隊の指揮にあたった前東京消防庁警防部長の佐藤康雄氏と、前東京都総務局総合防災部情報統括課長の齋藤實氏に話をうかがった。
司会:東日本大震災の対応においては、様々な場面で難しい判断をされてきたと思いますが、今、振り返ってみて特に印象に残っているのはどのような時ですか。
佐藤氏:東京都内の被災状況の全体像がつかめない中、地震発災から50分後に総務省消防庁長官から東北への緊急消防援助隊の派遣要請が入り、その派遣体制をどう整えるかが、発災直後の喫緊、かつ、重要な判断の1つでした。 一番心配したのは、東京も震度5強の被災地であるということです。発災直後に入ってきた災害情報への対応は勿論大切ですが、あまりに被害がひどいがために、その災害情報を伝えられない地域があるのではないかということを常に念頭においていました。阪神淡路大震災でも、被害が大きなところほど情報が伝わりにくい状況がありました。そうした隠れた情報を見逃さないようにしないと判断を誤ると考えていました。
齋藤氏:注意しなければならないのは、最初に来る情報は、連絡手段が確保されている被害が少ない地域の情報で、最も被害が大きいところの情報は遅れてくることです。最初の情報は氷山の一角といってよく、そこにこだわりすぎてはいけない。大規模災害のときには、情報を受ける側が、多数の情報が次々に入ってくることを考慮しておかなければなりません。
司会:災害発生後、次々と入ってくる情報に判断が鈍ることはないのですか。
佐藤氏:1つとして同じ災害はありません。その場の状況をよく見定めて判断することが肝要です。震災のような広域災害では、はじめの情報で即応しないと危ないこともありますが、手持ちの限られた戦力をいかに有効に使うかが最重要課題となります。そのためにも多くの情報をキャッチすることが必要で、東京消防庁ではヘリを飛ばすなど被害の全体像をつかむことに努め、そのうえで1時間半後に東北への援助隊派遣につなげることができました。かなり早い対応ができたと思います。
これには、昨年11月に実施した関東ブロック緊急消防援助隊訓練の際に、全署員の情報に対する感度を徹底的に高めていたことが大きく寄与しました。どの情報を取り上げて流すべきか、といった重要情報のトリアージを全職員の共通認識にまで高める訓練ができていたのです。
齋藤氏:情報の「トリアージ」が何より重要です。情報を収集するだけならば早さだけが問われますが、その中には緊急性の要するものや再確認しなければならないものなど、様々な情報が含まれています。どの情報を取り上げるかということを、各機関の担当者が理解していないと難しいのです。
また、それらを踏まえて訓練をしておく必要があります。東京都の総合防災部は、都全体として被害状況をまとめることが最重要ですから、そうした情報の判別態勢を整えています。
司会:災害対策にはさまざまな組織が関わります。そのため情報はバラバラな状態で上がってくると思うのですが、どのように判断されるのですか。
佐藤氏:集まってくる情報は千差万別ですから、どういう情報が大事かということは、トップとトップをサポートする担当者の共通認識でなければなりません。
東京消防庁では指揮官と指揮官をサポートする指揮隊を組織しています。私は指揮官として、それぞれの指揮隊の練度をすぐに見抜けます。 指揮隊の練度は3段階で評価しています。まず初期の段階は「マニュアルを見ないと自分のやることがわからない」、それが中期の段階になると「自分のやることがわかる」。最終の段階は「自分のやることは当然わかっていて、周りの人のやることもわかる」。つまり、指揮隊の中で不足している部分があれば、共通認識により、そこを相互にサポートできるようになるということです。
齋藤氏:情報は現場から上がってきます。上がってきた情報のうち必要なものを、トップである指令官にあげ、指令官から対応の指示が出されることになる。その連携が上手くいかなければなりません。
一番大切なことは、いろいろな情報が入ってきても、まだ他にも何かあるのではないかという、ある程度ゆとりのある判断ですが、一方で情報をどれだけ早く集められるかということも大事です。そのためにはトリアージをしっかり行い、それを共通認識にしていくことです。その根本を支えるのは訓練です。
司会:最後に状況判断をするにあたり、最も大切にされているポイントはどのようなことでしょうか。
齋藤氏:私が大切にしているのは「平常心」です。災害時に情報がどんどん集まってくると、時に、情報に流されたり、惑わされてしまうことがあります。ですから、情報を受けている自分と、それを一歩下がって客観的に見ている自分をイメージして平常心を保ちます。
その平常心を支えるのは、心と身体の健康です。今回の震災で私は、地震発生当日から数日、24時間体制に近い勤務になっていましたが、その間、常時緊張状態でいたわけではありません。かなりの疲労状態にはありましたが、安定した心の状態で判断し、指示を出すようにしました。
佐藤氏:私は「変化」という言葉がキーワードだと思います。指揮官という立場は、変化に対する感覚が敏感でなければいけません。練度の低い指揮官は、情報を取りまとめるのに精一杯で現場を見ていないことがある。火災対応を例にとりますと、2、3人を救助した後、爆発が起きたり、あるいは他の場所で火災が出たりしたときに、変化した現場の状況を把握していなければ、適切な判断や指示を与えられません。現場の変化に鈍感で、自分の頭の中だけの思い込みにとらわれてしまう指揮官では任務の完遂はおぼつきません。自分の部隊の隊員がどこで動いていて、どれほどの危険にさらされているかをしっかりと把握しておかなければなりません。変化に対するアンテナを常に張っておく。そうしなければ災害対応も部下の安全確保も図ることはできないと考えます。
誌面情報 vol27の他の記事
おすすめ記事
-

自社の危機管理の進捗管理表を公開
食品スーパーの西友では、危機管理の進捗を独自に制作したテンプレートで管理している。人事総務本部 リスク・コンプライアンス部リスクマネジメントダイレクターの村上邦彦氏らが中心となってつくったもので、現状の危機管理上の課題に対して、いつまでに誰が何をするのか、どこまで進んだのかが一目で確認できる。
2025/04/24
-

-

常識をくつがえす山火事世界各地で増える森林火災
2025年、日本各地で発生した大規模な山火事は、これまでの常識をくつがえした。山火事に詳しい日本大学の串田圭司教授は「かつてないほどの面積が燃え、被害が拡大した」と語る。なぜ、山火事は広がったのだろうか。
2025/04/23
-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2025/04/22
-

帰宅困難者へ寄り添い安心を提供する
BCPを「非常時だけの取り組み」ととらえると、対策もコストも必要最小限になりがち。しかし「企業価値向上の取り組み」ととらえると、可能性は大きく広がります。西武鉄道は2025年度、災害直後に帰宅困難者・滞留者に駅のスペースを開放。立ち寄りサービスや一時待機場所を提供する「駅まちレジリエンス」プロジェクトを本格化します。
2025/04/21
-

-

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視
4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。
2025/04/15
-

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入
日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。
2025/04/15
-

-

生コン・アスファルト工場の早期再稼働を支援
能登半島地震では、初動や支援における道路の重要性が再認識されました。寸断箇所の啓開にあたる建設業者の尽力はもちろんですが、その後の応急復旧には補修資材が欠かせません。大手プラントメーカーの日工は2025年度、取引先の生コン・アスファルト工場が資材供給を継続するための支援強化に乗り出します。
2025/04/14

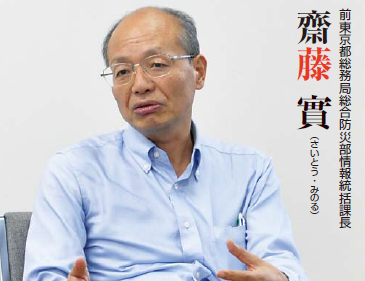




















![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)






※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方