2011/11/09
誌面情報 vol28
3月11日、東京都心で発生した公共交通機関のマヒにより、多くの帰宅困難者が発生した。東日本大震災の経験を経て、森ビルシティエアサービス株式会社(東京都港区、以下MCAS)はヘリコプターを活用したBCP(事業継続計画)の提案として「震災対策フライトプラン」を商品化。2012年のサービスインに先立ち既に数社が申込みをしている。震災などの緊急時、空を移動手段にするというものだ。10月13日に行われたMCASのBCPセミナー(東京都港区、アークヒルズクラブにて)では、バークレイズ・キャピタル証券株式会社ヴァイスプレジデントの佐柳恭威氏が、都内交通機関がマヒした際のヘリコプター活用について話した。外資系企業のバークレイズ・キャピタル証券が、なぜヘリコプターのソリューションに関心を持つことになったのか、移動手段として空を活用することのメリットは?講演内容を抜粋して紹介する。
■BCPは投資かコストか
BCPは投資なのかコスト(必要経費)なのか、と言われることがあるが、私は投資としての分析を行うことがBCPを実行可能かつ継続可能なものとする面において重要だと考えている。ある一手を欠いたために、事業が続かなかった、お客様や収益機会を失った、訴えられてしまったなどということは
十分にありうる話だ。一方で、企業が社会的責任を果たし事業を存続させるために莫大な投資を行ってしまえば震災前に企業の存続が危ぶまれる。BCPは継続可能な投資レベル内になければならない。
東日本大震災で起きたことを解析して、これから先、自社に影響することを具体的にイメージしてみることで、BCPによって回避できるリスク、得られるメリットが浮き彫りになるはずだ。重要なことは対策の目的と期待値を明確にすること。最初は難しいかもしれないが、あらあらでも定量評価(数値化)してみると良い。
リスクと対策投資の検討方法は多岐に渡るが、最も簡便な方法は過去データを分析し自社と類似した事例を探し出すことだ。予想される首都直下型(M7.3)と同規模の阪神・淡路大震災の被害データをもう一度見直し、自社の被災リスクを予想することから始めるとよい。内閣府や神戸新聞のHPにも詳細な検証記録が残っている。やる気になれば、現地を訪ねて話を聞くこともできるはずだ。また、教訓(=対策)の効果を算定するという例では3年の間隔をおいて発生した新潟県中越地震と新潟県中越沖地震の記録から学ぶことも多い。
■有事の際、東京から出られるか
MCASとヘリコプターを使ったBCPの話を始めたのは4月の上旬だった。東日本大震災を経て、有事の際に東京から出ることの難しさを痛感した。私ども外資系企業の多くは日本に限られた営業拠点しか持たず、その多くは東京に集中する。郊外に複数のバックアップオフィスを持ってはいるが、緊急時に事業の継続のため、社内の重要業務を支えるスタッフをどう移動させたらいいのかはかねてからの課題だった。
例えば、メガバンクのように他の地域にも常設の営業拠点をつくり平常時からスプリットオペレーションを行うことができる仕組みがあれば、被災時の人員移動リスクは軽減できる。だが、これには設備の維持、人員のコストなどとてもお金がかかる。 人選や教育も課題。以前勤務していた富士銀行(当時)では、少ない人員で業務を行う必要のある新設店舗には精鋭部隊が送り込まれていた。しかし本社から優秀な人を出してしまうと本社の競争力やモチベーションが低下するなど管理面、人事面などで別の問題が出てしまう。したがって、人材に厚みと余力があり、新しく設置した営業拠点でも十分に収益を上げられる裏づけがないとスプリットオペレーションの採用は極めて難しい。
では、どうしたらいいのか。災害時に業務を支える精鋭部隊を、できるだけ迅速に移動させれば良いのだが、その手段がない。新幹線や車、飛行機を使ったらいいじゃないかと思われるかもしれないが、道路や鉄道、公共交通網も被害を受けるため発災後はしばらく使えない。飛行機はかろうじて運航しているだろうが、空港まで行くことができない。3月11日の当日、成田に向かおうとした人も数多くいるかと思うが、あのとき交通手段は全く機能していなかった。電車やバスが止まり、都内から出ることができなかった。
災害発生当日から数日間、どうやって人を送り出すかを議論する中でヘリの災害時利用の話が浮上し、MCASに相談し「震災対策フライトプラン」を組み上げるに至った。
■鈴与グループもヘリを活用
実は、空の移動で事業継続を考えている企業はほかにも国内にある。
静岡エアコミュータ㈱(SACC)の事例を紹介したい。同社は鈴与グループが出資する航空運送会社で、ヘリコプターや小型のビジネスジェット機などでチャーター事業や航空撮影などを行っている。同社は、被災時に行うことを5つのプライオリティとして整理している。第一優先課題は鈴与グループ全体の被災状況を把握すること。鈴与グループは海上輸送、コンテナなどの港湾事業、エネルギー事業、工場など大規模な設備を多数持つため、会社設備の被害状況をつかむには、空から見るのが一番早い。
2番目は、被災した顧客、株主、社員の救援。この2つの目的を達成するには、他に頼るより、自社でヘリやジェット機を持っていたほうが柔軟に対応できる。ただ、維持し続けるためには膨大なコストがかかる。鈴与グループはROI(リターン・オン・インベストメント)の観点から、BCPの目的を果たす手段の1つとしてのヘリやジェット機の保有コストを下げるため、航空会社をつくって一般のお客様を乗せるサービスを行うことにしたのではないかと思われる。
3番目は行政からの依頼による被災地の救援活動。東日本大震災の際は3月中旬に交通網が分断され孤立してしまった岩手県花巻まで、同じ鈴与グループの中で定期航空による運送事業を営むフジドリームエアラインズの小型ジェット旅客機(76∼84人乗り)を5往復飛ばし、医療スタッフや支援物資の輸送を行ったと聞く。驚くべき行動力だ。
4番目は報道各社の依頼による飛行、5番目に民間各社などからの依頼による飛行となっている。 私どもが相談したかったのは5番目で、結果的に同社への依頼を進めることができなかったが、将来的にMCASとSACCのアライアンスが実現すれば、MCASのヘリの弱点である航続距離の問題をSACCのビジネスジェットへの乗り継ぎで解決できるのではないかと考えられる。
鈴与がBCPに向かう姿勢、時代を先取りした鋭い分析力、対策を実現する行動力のどれをとっても卓越していると感じた。
■自社のBCPが地域救済になる
最初の頃は、社内で「ヘリを活用したBCPソリューション」と言っただけで眉をしかめられたこともあった。しかし、首都圏が震災に見舞われるリスクシナリオとその発生確率、その際どのような状況に陥るのか、警視庁による交通規制の影響や被害エリアなど被災状況を具体的にイメージできるような説明を行ううちに理解が得られるようになった。決め手は「この対策は事業継続のための保険だと考えれば良いのか」という質問だった。
営者はBCPに対しても「どのようなリスクがあるのか」「それぞれのリスクの発生頻度はどのレベルか」「対策を行わない場合の損失はどの程度なのか」「どのリスクに対しいくらかけて対策を行うのか」「その対策を行うことによりどの程度リスクを軽減することができるのか」「代替策は何か」という点をついてくる。これはプロジェクトファイナンスや投資を行う際のチェック項目とも重なる。BCPは単なるコストではなく事業への投資であると再認識し、ROIの分析を加えることが重要だと私は考える。そのためには定量化が必要で、自社の被るリスクと被害想定のイメージを過去の被災データを参考に作り上げることが大切だと思う。
■社会的責任を果たすために
社会的責任を果たすために我々がやるべきことは何か、それをするために何が必要なのかを具体的にイメージすることから始めるとよい。金融機関において最重要業務とは資金決済になる。重要なことは、被災時であっても計画通りに資金決済業務を行うこと。金融機関のサプライチェーンはたった1つが滞っても、ドミノ倒しのように全体が崩壊してしまうリスクがあるからだ。数字を聞くと驚くかもしれないが、金融機関全体では1日平均100兆円ぐらいの決済の取り扱いがある。実際にお金が来ないと、次に支払いができない。最終的にお客様の手元に資金が届かなければ大変なこと。一行が破たんしてしまうと、金融システム全体が倒壊してしまうことになりかねない。
私が以前務めていた富士銀行(当時)のニューヨーク支店は2001年の9.11米国同時多発テロの際、業務開始時間の直後に2機目の飛行機の直撃を受けワールド・トレードセンター・ビルと共に崩れ去った。携帯電話もつながらず、何の指示も受けられない中、生き残った行員たちは孤独と不安に耐え、何時間もフェリーの列に並び、ハドソン・リバー対岸のバックアップオフィスに向かい、その日の深夜までかけて必死に業務を立て直した。同僚を失い、オフィスを失い、それでもこの日の資金決済をやり遂げた。この日のことを知る人は少ない。私は親友たちを失った深い悲しみの中、富士銀行員であることに誇りを感じた。
そのときの経験を振り返ると、金融機関も社会インフラとしての責任を担っており、従業員もそのことを十分認識していたのだと思う。物流や資材、医療品関連など、どんな企業でも同じだ。自社だけでなく社会を支えるのがBCPの大きな目的でもある。
■30キロメートルの円から脱出
社会的責任を果たすためには資金決済を行えるスタッフをできるだけ早くバックアップサイトに送り届ける必要があるが、関西のバックアップオフィスまでヘリを飛ばすなどと大胆なことを考えているわけではない。航続距離、巡航速度、燃費などヘリの特性を考えればこの方法は得策ではないからだ。中央防災会議や東京都などの分析資料を詳しく調べると気づくことだが、首都直下型地震の被災規模想定では、都心から30キロメートル離れれば公共交通機関は動く。被災もほとんどない。50キロメートル離れるとほぼゼロ。我々が外に行かなければいけないのは、被災地を中心とした30キロメートルの円からの脱出である。この中が大変な混乱状態になると見られるからだ。阪神淡路大震災を思い出してほしい。加古川を一本渡ったら普通の生活があったことに驚いたのは私だけではないだろう。 都心から成田まではヘリで20分弱、成田で国内線やビジネスジェットにも乗り継ぎができる。チャーターしたバスを待たせておいてもいい。また事前に離着陸登録さえすれば首都圏近郊のゴルフ場などをヘリからバスへの乗り換え拠点にすることもできる。
この際、帰りのヘリは“カラ”になる。ここに被災地で不足する人材、医師、看護師、救命救急士などを無料で乗せて都心に入ってきてもらうのはどうだろうか。医療物資は備蓄できるが、医療を行う人材を備蓄することはできない。地震発生後の公共交通機関のマヒや交通規制の影響は、中から外に出られないだけでなく、救助が外から中に入りにくいという問題もあるため、ヘリコプターの活用がそうした困難の一助にもつながる。このフライトプランを多くの企業が活用すれば往復回数が増え、それだけ多くの人を運ぶことができる。自社のBCPが地域全体の救援にもつながるのではないか。
誌面情報 vol28の他の記事
おすすめ記事
-

自社の危機管理の進捗管理表を公開
食品スーパーの西友では、危機管理の進捗を独自に制作したテンプレートで管理している。人事総務本部 リスク・コンプライアンス部リスクマネジメントダイレクターの村上邦彦氏らが中心となってつくったもので、現状の危機管理上の課題に対して、いつまでに誰が何をするのか、どこまで進んだのかが一目で確認できる。
2025/04/24
-

-

常識をくつがえす山火事世界各地で増える森林火災
2025年、日本各地で発生した大規模な山火事は、これまでの常識をくつがえした。山火事に詳しい日本大学の串田圭司教授は「かつてないほどの面積が燃え、被害が拡大した」と語る。なぜ、山火事は広がったのだろうか。
2025/04/23
-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2025/04/22
-

帰宅困難者へ寄り添い安心を提供する
BCPを「非常時だけの取り組み」ととらえると、対策もコストも必要最小限になりがち。しかし「企業価値向上の取り組み」ととらえると、可能性は大きく広がります。西武鉄道は2025年度、災害直後に帰宅困難者・滞留者に駅のスペースを開放。立ち寄りサービスや一時待機場所を提供する「駅まちレジリエンス」プロジェクトを本格化します。
2025/04/21
-

-

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視
4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。
2025/04/15
-

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入
日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。
2025/04/15
-

-

生コン・アスファルト工場の早期再稼働を支援
能登半島地震では、初動や支援における道路の重要性が再認識されました。寸断箇所の啓開にあたる建設業者の尽力はもちろんですが、その後の応急復旧には補修資材が欠かせません。大手プラントメーカーの日工は2025年度、取引先の生コン・アスファルト工場が資材供給を継続するための支援強化に乗り出します。
2025/04/14



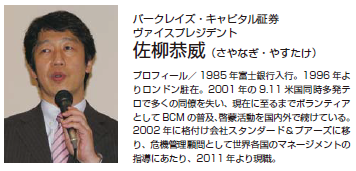




















![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)






※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方