2011/11/25
誌面情報 vol28
対応能力を向上させるポイント
「まずやってみる」 こと
「BCP に取り組んでいて本当に良かった」 。東京 都 BCP 策定支援事業に参加いただいた多くの中小 企業の社長の皆さまから3月 11 日以降に頂戴した ありがたいメッセージです。
弊社は、東京都が 22 年度に行った BCP 策定支援 事業において、当事業の受託企業として、都内の中 小企業 35 社に対して、BCP 策定支援を実施しまし た。ご参加いただいた企業の皆様からこうした生の 声をいただけたことは、この仕事をしていて良かっ たと思える大きな出来事でした。
さて、東日本大震災が発生した3月 11 日午後2 時 46 分は、重責を担う役職員が外出されていたと いう企業も多かったのではないでしょうか。対策本 部メンバーが揃わず、被災想定通りに事は運ばず、 その場で起きることは、考えていた被災シナリオ以 外のことばかり。これは、多くの企業・組織にとっ て同じような状況だったと思います。それでも、先 ほど紹介した企業においては、BCP は確かに役に 立ったのです。
社長不在の中、代行の意思決定者を決めていたお かげで、2番目、3番目の意思決定者が対策本部を 立ち上げ、情報収集、社内外への連絡など速やかに 実施されました。社員を守り、取引先からは大いに評価され、信用という財産を得ることとなったのです。
これまで多くの経営者と一緒に BCP 策定に携わり、東日本大震災を経験した中で、BCP を機能さ せるためのポイントについて、確信したことがいく つかあります。それは起きた事象に対し、対応する 人の能力を向上させることが大いに意味を持つとい うことです。 優れた BCP(ハード)を策定する為の手法は多 く語られていると思いますのでここでは述べませ ん。今回はソフト的な部分「対応能力」を向上させ るためのポイント3点をご紹介したいと思います。
1.経営者・現場が中心となって構築する
被災した場合に実際に判断し、行動するのは経営 者、現場担当者です。彼らが BCP 構築時に中心メ ンバーとして参加し議論することが何より重要ということです。BCP 構築時に専門家や事務局が中心 となっていくら考えても、そこには自社の真実はあ りません。何を大切にするのか?どのサービスは止めてはいけないのか?どのお客様には止めてはいけ ないのか? BCP においては事務局や専門家では判 断できないことが多々あります。実際に起きた時ど うするのか?それは有事における経営そのもので す。「意思決定する責任者、実行する現場」で動く BCP こそ求める姿なのです。
2.演習を実施する
BCP 策定はゴールではありません。組織の中で BCP 策定に関わるメンバーは全体の一部になるこ とがほとんどです。BCP の活動は計画を策定して からが本番になるのです。重要な事業や業務を分析 し、それらを脅かすリスクを想定し、事業継続するための計画を作ったのは本番の活動に入るためで す。
最初はプロジェクトメンバーのみで検証のための 演習を実施する。それから自社 BCP の成熟度に合 わせて、対策本部、事務局、一部の事業部が単体で、 またはそれらの組み合わせにより合同訓練へと範囲 を広げ、最終的には全社員にまで浸透させていく。 その内容も発災後 30 分、1日、2日、など、シナ リオを変えてみる。このように、実際に起きたらど う動くのか「疑似の被災体験」を繰り返します。 演習は「悪夢」を見るようなものだと思います。 「社長が負傷した」、「工場が倒壊した」次々に起こ る嫌な夢、それはまさに「悪夢」です。でも、緊張 して冷や汗をかきながら対応している中で、 「これ は現実ではなかった」と、はっと気付くのです。み んなで一緒に「悪夢」を見て、夢で良かった、実際 に起きる前に「ああしよう、こうしておこう」と自 然に対策が検討されます。
なんら経験のないことへの対応は難しく、初動の 遅れが、社員の命、会社の事業に大きな影響を与え ます。疑似被災体験をしておくことで慌てず適切な 行動へと近づけるのです。
3.改善活動を継続する
演習を実施すると、多くの課題が見えてきます。 対応策もいろいろと議論されるこ とになります。 しかし、演習の際には BCP の 活動を継続する重要性を共有でき ていたメンバーも、 いつの日にか、 日々の仕事に追われ BCP の為の 活動は、ついついおざなりになっ てしまいます。そこで、会社とし ての経営計画と一体化した BCP の活動を年間計画に落とし込み、 定期的にその進捗が確認できるよ うにすることが有効です。 「災害 は忘れたころにやってくる」 。い つ来るかわからない災害に対応するためには、会社として活動を継続すると決めて行 うことが非常に重要です。
どのポイントも特に目新しいことを申し上げてい るわけではないですが、実際に起きた事象に対応す るための「対応能力」を向上するポイントはそうし た当たり前のことを当たり前に行うことにあると言 えます。しかも、実はこれらは実行するのは結構難 しいのが実態です。何故難しいのでしょうか?大き な要因としては完璧な仕事、緻密な計画を求める日 本人の気質にあるのかもしれません。どうしても素 晴らしい「BCP を作る」ことをつい目的化してし まいがちです。抜け漏れのない、あらゆる事象に対 応できる BCP をつくること、そうでないと価値が ないと考えてしまいがちなのです。素晴らしい計画 の価値を否定はしません。しかしながら、何が起こ るかわからない未来に対し何でも対応できる「魔法 の杖= BCP」だけを求めるだけでは限界がありま す。できる限り準備した BCP を使って適切に対応 できる「対応能力」を向上させることにもっとフォ ーカスを当ててみてはいかがでしょうか? 我々のす べきことはいきなり 100 点を目指すことではありま せん。「まずやってみる」ことであり、そこから改 善活動を継続していくことです。魔法の杖を持った 専門家を待たずに、自ら「まずやってみる」それこ そが「動く BCP」への早道だと思います。
誌面情報 vol28の他の記事
おすすめ記事
-

自社の危機管理の進捗管理表を公開
食品スーパーの西友では、危機管理の進捗を独自に制作したテンプレートで管理している。人事総務本部 リスク・コンプライアンス部リスクマネジメントダイレクターの村上邦彦氏らが中心となってつくったもので、現状の危機管理上の課題に対して、いつまでに誰が何をするのか、どこまで進んだのかが一目で確認できる。
2025/04/24
-

-

常識をくつがえす山火事世界各地で増える森林火災
2025年、日本各地で発生した大規模な山火事は、これまでの常識をくつがえした。山火事に詳しい日本大学の串田圭司教授は「かつてないほどの面積が燃え、被害が拡大した」と語る。なぜ、山火事は広がったのだろうか。
2025/04/23
-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2025/04/22
-

帰宅困難者へ寄り添い安心を提供する
BCPを「非常時だけの取り組み」ととらえると、対策もコストも必要最小限になりがち。しかし「企業価値向上の取り組み」ととらえると、可能性は大きく広がります。西武鉄道は2025年度、災害直後に帰宅困難者・滞留者に駅のスペースを開放。立ち寄りサービスや一時待機場所を提供する「駅まちレジリエンス」プロジェクトを本格化します。
2025/04/21
-

-

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視
4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。
2025/04/15
-

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入
日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。
2025/04/15
-

-

生コン・アスファルト工場の早期再稼働を支援
能登半島地震では、初動や支援における道路の重要性が再認識されました。寸断箇所の啓開にあたる建設業者の尽力はもちろんですが、その後の応急復旧には補修資材が欠かせません。大手プラントメーカーの日工は2025年度、取引先の生コン・アスファルト工場が資材供給を継続するための支援強化に乗り出します。
2025/04/14
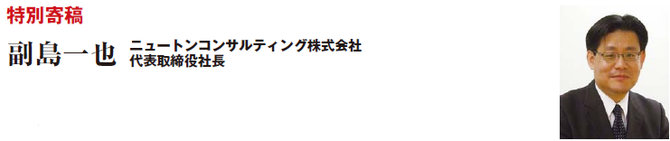





















![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)






※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方