2017/02/17
防災・危機管理ニュース
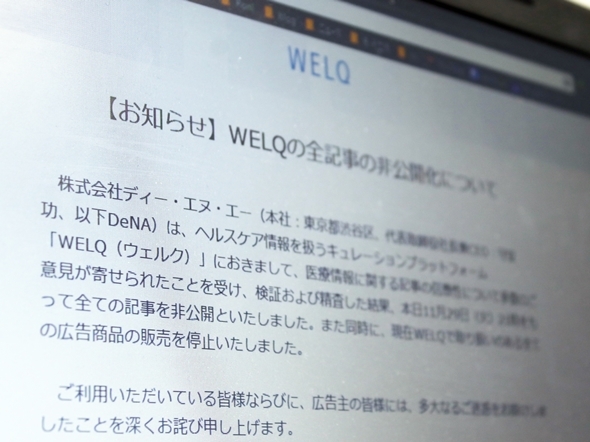
昨年末、医療系キュレーションメディア「WELQ」をはじめとした大手IT企業のDeNAが運営する「まとめサイト」が、著作権法や記事の内容について数々の問題点を指摘され、閉鎖に追い込まれた。しかしこの問題は一般企業にとっても対岸の火事ではない。老舗の総合ネットセキュリティ企業イー・ガーディアンは「今回の問題が企業のオウンドメディアに波及する恐れもある」とし、昨年12月に「コンテンツ・ガーディアン」を発足。Webコンテンツの健全化支援に取り組んでいる。
イー・ガーディアンは1998年に設立。現在は東証一部にも上場し、掲示板やSNS投稿監視などを主たる事業として行うネットセキュリティのリーディングカンパニーだ。現在は監視業務のほか、IT系企業のカスタマーサポートや薬機法(医薬品、医療機器等の品質、 有効性及び安全性の確保等に関する法律)や景表法(景品表示法)などを中心としたインターネット広告に関わる審査代行業務※も展開している。※弁護士法72条に定める法律事件に関する法律事務は含まれない。
昨年12月に発足した「コンテンツ・ガーディアン」は、インターネット広告審査代行業務からさらに一歩踏み出し、インターネットメディアの記事そのものが著作権法などさまざまな法律に抵触していないかをパトロールし、健全化を支援するサービス。
インターネットメディアの運営者やクラウドソーシング事業者向けに、記事チェック体制の構築から薬機法、景表法の審査代行サービスを提供するという。
前述した「WELQ問題」を受け、ほかにも一部上場企業が運営するWebサイトで閉鎖(非公開)、もしくは記事の削除に踏み切っているケースは後を絶たない。インターネットという新しい潮流の中で、企業はどのようにコンテンツの信頼性を担保していかなければいけないのだろうか。
企業のオウンドメディアは社内体制の確立が不可欠

取材に応じた同社営業部の本田良平氏は「サービスの対象は主にインターネットメディア事業を営む企業だが、オウンドメディアを展開する一般企業にも当てはまるのでは」と話す。
オウンドメディアとはメーカーなどの一般企業が自社の責任において制作し、所有する媒体のこと。広義では広報誌などもオウンドメディアに入るが、ここでは「企業が運営する自社所有のWebサイト」について話を進める。
同社の前職では広告会社に勤務していた本田氏は、「あくまで主観だが、企業が発信する紙のカタログや広報誌は、たとえば表紙を1文字間違えただけでも刷り直しなどの対応をする場合があり、校正はプロに任せ、編集にも時間をかけており、緊張感が漂っていた。Webは記事をアップ後も修正可能な点は便利な一方、公開するハードルが低いとも言える。また、(紙の冊子などに比べて)コンテンツに対する社内のチェック体制が確立できていないのではと感じる時もある」と話す。
Webサイトは簡単に大量のページを作成でき、さらに記事が多ければ多いほどSEO(検索エンジン最適化)にもつながる。そのためページビューを稼がねばいけないWeb担当者は、絶えず多くのコンテンツを制作し、公開することが必要になる。しかし本田氏は「コンテンツが増えれば増えるだけ、リスクも増える可能性があると認識した方がよい」と語気を強める。
さらにソーシャルメディアが発展している昨今、もしコンテンツが悪い意味で大量に拡散される、いわゆる「炎上」という事態になれば、企業に対するダメージは計り知れないだろう。
「少なくとも、インターネットでコンテンツを広く公開すれば質問やクレームが来ることもある。そういった時に、誰がどのような責任をもってどのように回答するのか、そういう社内体制を整えることが必要なのではないか」(同氏)
企業の発信責任
ブロガーやユーチューバーと呼ばれる人々に代表されるように、インターネットの世界では、誰もが世界に向けて情報を発信することができる。誰でも「メディア」になることができる一方で、従来からあるメディアの「発信責任」に対する考え方は明らかに変化してきている。通常のメディアであれば、記事の内容に関しては編集長や監修者が責任を持つ。間違ったことを発信した場合は速やかに訂正してお詫びするなどの判断を行い、その信頼性を担保する。
本田氏は「オウンドメディアも本来は同じ。自社で作るとどうしてもブランディングや購買目標が先行しがちだが、客観的な目で監修してもらったり、いろいろな部署の意見を反映したり、守りの部分を固めることはとても重要なこと。最近、企業はセキュリティの部分には費用をかけ始めているが、外部発信のリスクを、全社課題として認識している企業はまだ少ないのが現状」としている。
(了)
防災・危機管理ニュースの他の記事
おすすめ記事
-

自社の危機管理の進捗管理表を公開
食品スーパーの西友では、危機管理の進捗を独自に制作したテンプレートで管理している。人事総務本部 リスク・コンプライアンス部リスクマネジメントダイレクターの村上邦彦氏らが中心となってつくったもので、現状の危機管理上の課題に対して、いつまでに誰が何をするのか、どこまで進んだのかが一目で確認できる。
2025/04/24
-

-

常識をくつがえす山火事世界各地で増える森林火災
2025年、日本各地で発生した大規模な山火事は、これまでの常識をくつがえした。山火事に詳しい日本大学の串田圭司教授は「かつてないほどの面積が燃え、被害が拡大した」と語る。なぜ、山火事は広がったのだろうか。
2025/04/23
-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2025/04/22
-

帰宅困難者へ寄り添い安心を提供する
BCPを「非常時だけの取り組み」ととらえると、対策もコストも必要最小限になりがち。しかし「企業価値向上の取り組み」ととらえると、可能性は大きく広がります。西武鉄道は2025年度、災害直後に帰宅困難者・滞留者に駅のスペースを開放。立ち寄りサービスや一時待機場所を提供する「駅まちレジリエンス」プロジェクトを本格化します。
2025/04/21
-

-

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視
4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。
2025/04/15
-

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入
日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。
2025/04/15
-

-

生コン・アスファルト工場の早期再稼働を支援
能登半島地震では、初動や支援における道路の重要性が再認識されました。寸断箇所の啓開にあたる建設業者の尽力はもちろんですが、その後の応急復旧には補修資材が欠かせません。大手プラントメーカーの日工は2025年度、取引先の生コン・アスファルト工場が資材供給を継続するための支援強化に乗り出します。
2025/04/14







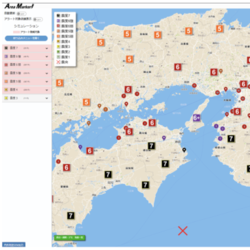













![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)






※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方