2016/08/05
事例から学ぶ

4月14日の「前震」では、発生後1時間程度でほぼ全社員が会社に集まり、顧客の安否確認にあたったというアネシス(熊本市東区)。九州は台風の上陸が多く、住宅の被害も多く発生することから、同社では10数年前から災害対応マニュアルを作るなど対策に力を入れてきた。
社員約100人の中小企業だが、災害の発生時には災害対策室を立ち上げることが決められている。「住宅被害が発生しそうなレベル」というのが設置の基準だ。

一戸紀見華氏(右)
災害対策室のメンバーは15人。社長や役員がいなくても迅速に対応にあたれるよう、予算を含め、ほぼすべての権限が災害対策室長となる前田優課長に与えられている。「もちろんその都度、社長と相談しますが、基本的には災害対応にかかる判断はすべて任されています」(前田氏)。
平時の業務と調整しながら災害対応にあたれるよう、対策室長および副室長の下に、各事業部長でつくる執行部を介して、情報班、指示班、緊急班、訪問班、積算班を置く。
災害発生時には、災害対策室が立ち上がるだけでなく、子供がいる母親などを除いて、全員が会社に集まるというのが同社のルール。14日夜に発生した熊本地震の前震でも、ほぼ全員が集まった。「参集の基準を明確に決めているわけではありませんが、毎年のように大きな台風が来るので、社員の心の準備もできていたのでしょう」(前田氏)。
緊急連絡は日常的にメールやLINE(ライン)を使っている。社員の安否を確認しながら、並行して約2100件にのぼる既存顧客(住宅オーナー)すべてに電話かけを実施した。
「お客様がご無事かどうかを確認するのが基本。翌日以降でも不具合があれば、遠慮なく連絡してほしいということを伝えました」と前田氏は説明する。
事例から学ぶの他の記事
おすすめ記事
-

新任担当者でもすぐに対応できる「アクション・カード」の作り方
4月は人事異動が多く、新たにBCPや防災を担当する人が増える時期である。いざというときの初動を、新任担当者であっても、少しでも早く、そして正確に進められるようにするために、有効なツールとして注目されているのが「アクション・カード」だ。アクション・カードは、災害や緊急事態が発生した際に「誰が・何を・どの順番で行うか」を一覧化した小さなカード形式のツールで、近年では医療機関や行政、企業など幅広い組織で採用されている。
2025/04/12
-

-

-

防災教育を劇的に変える5つのポイント教え方には法則がある!
緊急時に的確な判断と行動を可能にするため、不可欠なのが教育と研修だ。リスクマネジメントやBCMに関連する基本的な知識やスキル習得のために、一般的な授業形式からグループ討議、シミュレーション訓練など多種多様な方法が導入されている。しかし、本当に効果的な「学び」はどのように組み立てるべきなのか。教育工学を専門とする東北学院大学教授の稲垣忠氏に聞いた。
2025/04/10
-

-

-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2025/04/08
-

-

-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ
リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。
2025/04/05










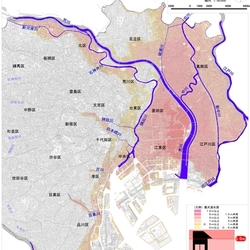













![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)






※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方