2024/03/28
令和6年能登半島地震
木造住宅の耐震化 実務者の視点
一級建築士事務所・技術士事務所SERB代表
樫原健一氏
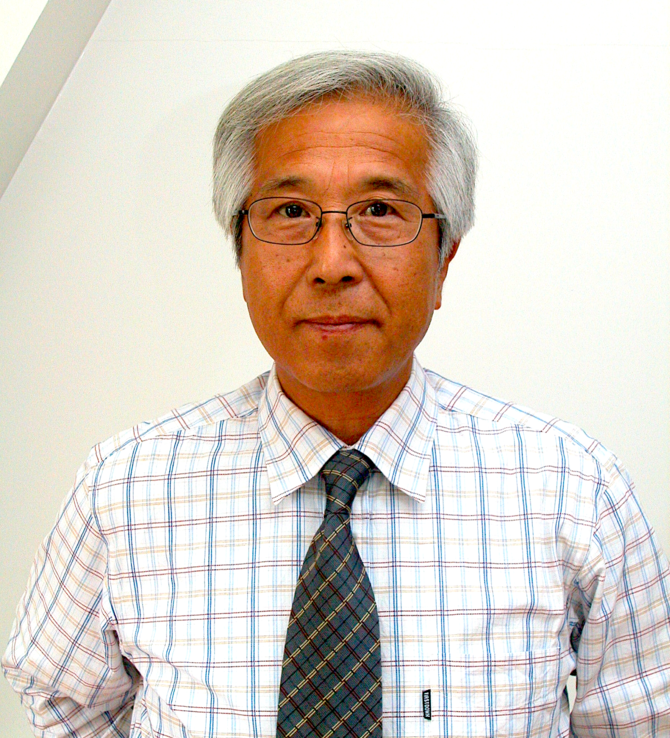
かたぎはら・けんいち
1973年、神戸大学大学院工学研究科修士課程建築学専攻修了後、鴻池組に入社。2006年に退職し同本社技術顧問に就任するとともに、一級建築士事務所・技術士事務所SERBを設立。一級建築士、建築構造士、技術士。著書に「木造住宅の耐震設計-リカレントな建築をめざして」(共著、技報堂出版)「震災復考」(新建新聞社)など。
能登半島地震の死者の大半が、倒壊した建物の下敷きになったことで命を落とした。珠洲市や輪島市の耐震化率は50%程度と、全国平均の87%に比べ極端に低く、過疎高齢化地域の耐震化の困難さを物語る。そしてそれは、能登地域だけの問題ではない。家屋の倒壊からいかに命を守るのか。一級建築士事務所・技術士事務所SERB(サーブ)代表で、伝統的建築物の構造計算適合性判定に長年携わってきた樫原健一氏に、木造の耐震化をめぐる課題を聞いた。
耐震化率は形骸化している
――能登半島地震では、家の倒壊で多くの死者が出ました。実務者の立場で、今回の被害をどう見ますか?
被災地を直接見ていないので、被害様相は語れません。ただ、専門家が「新耐震基準以前の建物が倒れた」「新耐震基準以上に改修せよ」といっているのを聞くと、違和感を覚えます。珠洲市や輪島市の耐震化率は50%程度ということですが、過疎高齢化地域で耐震改修が進まないのはわかっていることです。
わかっていながら「新耐震基準以前の建物が倒れた」「新耐震基準以上に改修せよ」というのは、できないなら倒壊しても仕方ないという突き放しに聞こえます。専門家がいうべき言葉ではない。問題は、そうした社会状況をわかったうえで、ではどうしたら家の倒壊から人の命を守れるのかでしょう。

そもそもでいえば、耐震化率は100%であるべきものです。違反建築でないとはいえ、現行の耐震基準を満たさない家が半分もあるのは、倒壊のリスクを考えたら本来はおかしい。しかし、その状況が常態化しているということは、耐震化率が単なる表向きの数字にしか思われていないことの証左ではないでしょうか。
耐震化率を100%にせよといっているのではありません。耐震化率は現行法の構造規定に合致していることを担保しているだけであって、その規定はあくまで最低限の基準です。常用設計に用いるにはよいでしょうが、過疎高齢化地域で古くからある家をどう安全にしていくかという話とは文脈が違う。数字合わせをしても意味はありません。
当然ですが、建築基準法の目的は基準それ自体を満たすことではなく、人命を守ること、つまり倒壊による死者をなくすことです。新耐震基準にすれば倒壊を防げるかのようないい方は、便宜的ないい換えだと思います。
人の命を奪う壊れ方をさせない
――すると、求めるべき住宅の耐震安全性とは何なのでしょうか?
究極的には、今回の能登半島地震のような非常に強い揺れに見舞われても、人の命を奪うような壊れ方をしない。つまり、完全につぶれてしまうような壊れ方をしないことだと思います。
どこか一部が壊れても、傾いても、踏みとどまってさえいれば何とかなります。逃げることができ、もしかしたらあとで修復もできる。とにかく、ぺちゃんこになる壊れ方をさせない。しかし、最悪の揺れにおいて建物がどういう壊れ方をするかは、必ずしも研究が進んでいるわけではありません。
木造住宅の耐震設計において、構造計算の結果を検証するクライテリア(判定基準)は、最大で層間変形角15分の1程度です。ただ、実際の被害では5分の1くらいまで傾いても残っている建物がある。それが許容されれば、いきなり耐震診断評点1.0を求めなくても補強方法はあります。しかし、最悪の揺れにおけるクライテリアは設定自体ができません。

――なぜ設定できないのでしょうか?
最大の理由は、震度階級における震度7の揺れは青天井だからです。法律で定める「極めてまれな地震」は震度6強で、クライテリアも震度6強を見込んで設定されています。それを超える震度7は、青天井ゆえに、揺れを定義できない。当然、最悪の揺れを満足させるクライテリアも存在しません。
つまり、ここまでやったら安全だといい切ることは不可能です。だから、新耐震基準で線引きしたほうが楽だというのはわかります。しかしその結果、実際の被害で踏みとどまった古い建物があっても「たまたま運がよかった」で終わってしまう。それは、自然現象と虚心に向き合う姿勢とはいえません。
インタビューの他の記事
おすすめ記事
-

自社の危機管理の進捗管理表を公開
食品スーパーの西友では、危機管理の進捗を独自に制作したテンプレートで管理している。人事総務本部 リスク・コンプライアンス部リスクマネジメントダイレクターの村上邦彦氏らが中心となってつくったもので、現状の危機管理上の課題に対して、いつまでに誰が何をするのか、どこまで進んだのかが一目で確認できる。
2025/04/24
-

-

常識をくつがえす山火事世界各地で増える森林火災
2025年、日本各地で発生した大規模な山火事は、これまでの常識をくつがえした。山火事に詳しい日本大学の串田圭司教授は「かつてないほどの面積が燃え、被害が拡大した」と語る。なぜ、山火事は広がったのだろうか。
2025/04/23
-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2025/04/22
-

帰宅困難者へ寄り添い安心を提供する
BCPを「非常時だけの取り組み」ととらえると、対策もコストも必要最小限になりがち。しかし「企業価値向上の取り組み」ととらえると、可能性は大きく広がります。西武鉄道は2025年度、災害直後に帰宅困難者・滞留者に駅のスペースを開放。立ち寄りサービスや一時待機場所を提供する「駅まちレジリエンス」プロジェクトを本格化します。
2025/04/21
-

-

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視
4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。
2025/04/15
-

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入
日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。
2025/04/15
-

-

生コン・アスファルト工場の早期再稼働を支援
能登半島地震では、初動や支援における道路の重要性が再認識されました。寸断箇所の啓開にあたる建設業者の尽力はもちろんですが、その後の応急復旧には補修資材が欠かせません。大手プラントメーカーの日工は2025年度、取引先の生コン・アスファルト工場が資材供給を継続するための支援強化に乗り出します。
2025/04/14





















![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)






※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方