2024/02/04
令和6年能登半島地震
高齢化・過疎化社会という脆弱性を直撃
顕在化した課題 防災の専門家に聞く
関西大学社会安全学部特別任命教授/社会安全研究センター長
河田惠昭氏
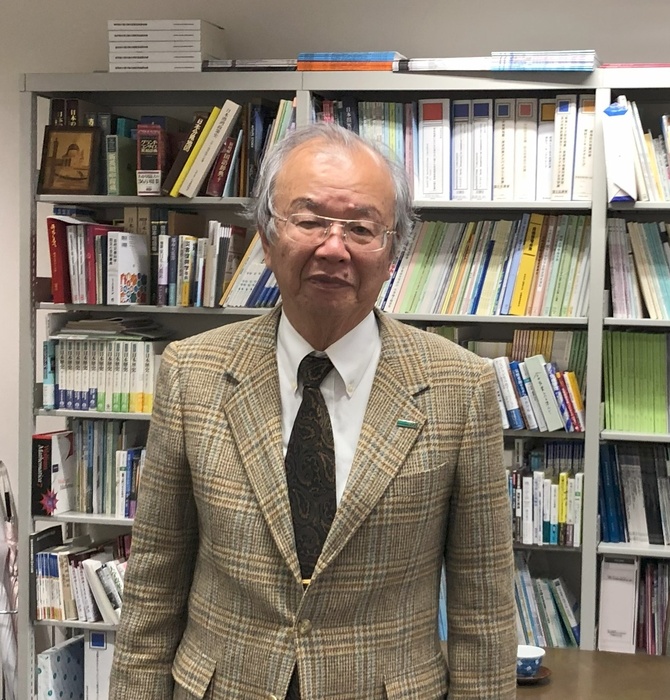
かわた・よしあき
1946年大阪府生まれ。専門は防災・減災・縮災研究。京都大学大学院工学研究科修了、同大学名誉教授。工学博士。同大学防災研究所巨大災害センター長、所長などを歴任し現職。人と防災未来センター長。ニューレジリエンスフォーラム共同代表。著書に「津波災害」(岩波新書)など。
半島奥地という地域条件、高齢化・過疎化という社会環境、元旦というタイミング。令和6年能登半島地震の被害は「脆弱性」を突いて拡大した。突きつけられた課題は何か、どう手を打てばよいのか。関西大学社会安全学部特別任命教授で社会安全研究センター長の河田惠昭氏に聞いた。
日本社会の問題を突きつけた
――令和6年能登半島地震をどう見ているか。
高齢化が進む過疎地を襲った地震。しかも元旦の夕方に起きた。元旦にこれほど大きな災害が起きたのは過去に類を見ない。自然は人間の都合など考えないことが目のあたりに示された。いわゆる「想定外」は、人間が勝手につくり上げた概念だと突きつけられた。
高齢化が進む過疎地において、自助はまったくといっていいほど機能できなかった。道路の寸断をはじめ、水や電気、通信の途絶、住宅の倒壊が、速やかな避難、救助・救援を妨げ、地域の共助も難しくした。
公助の投入に向け地元の建設業者は発災直後から道路啓開に動いたが、半島奥地のため業者数が少なく、平時さえ人が足りていない。余力がないうえ、地理的な条件から、応援受け入れのキャパシティーも限られた。
――政府の初動が遅かったのでは。
政府の初動が遅かったとは見ていない。「資源の逐次投入が被害を拡大した」という批判があるが、申し上げたとおりインフラがやられ、受け入れの余力がない状況。港湾も津波や地盤隆起でやられ、かといって大規模な空輸も難しい。現地のキャパを無視して人を送り込んだら逆に混乱する。
むしろ問題なのは、そのように初動をセーブせざるを得ない状況があるにもかかわらず、それを常態化させてきてしまったことだ。自然現象に対する想定が甘かったといえばそれまでだが、国の運営そのものが問われる。いま南海トラフ地震が起きたら、能登と同じ状況が複数の県で発生し、もっとひどいことになるのは明らかだ。
しかも、今回は被災地のキャパを考えて初動をセーブしたためにリソースが足りなくなったが、南海トラフ地震ではリソース自体が足りなくなる可能性が高い。最大限の公助を行ったとしても、住民の自助、地域の共助は絶対に必要になる。そのためには事前の対策が不可欠だ。
高齢化・過疎化が進む日本社会において、どう対策すれば自助、共助を有効に発揮できるのか、そして最大限の初動対応、公助ができるのか。今回の地震で突きつけられた問題と真剣に向き合い、あらゆる面から検討し、具体的な手を打たなければならない。
インフラの強靭化・冗長化は必須
――インフラの途絶と復旧の遅れが初期の対応を困難にしたならば、まずはそこを何とかする必要がある。
総合的に取り組まなければならないが、ハードについていえば、今回の地震では道路網がほぼ壊滅した。背景には、高規格道路や国道が少なかったことがある。生活のための交通・流通の主力が市道や町道だったため、財政事情もあり、国道に比べメンテナンスが行き届いていない。結果、如実にやられてしまった。

道路下には上下水道管も敷設されている。ライフラインもいっしょにやられ、通信も途絶えた。ならば、今度はそうした事態を想定し、大規模災害時でも最低限の機能を担保すべき道路を選抜。そこを高規格化し、共同溝を設けて上下水道管や通信ケーブルを通し、ライフラインを強靭化・冗長化する取り組みが必要だ。
「人口が減る一方の地域にそんな投資をするのは無駄だ」という批判があるが、その考え方こそ変えないといけない。投資をしないから人口が減る一方なのであり、インフラがしっかり整備されることで利便性や安全性が向上すれば、産業誘致の可能性が高まる。雇用の場が生まれれば、住民が地域で生活していける。
いままで通りの考え方でいままで通りのことをしていたら、被災地は復興できない。住民は戻りたくても戻れない。どんどん人口が減り、いずれゴーストタウンになる。そして全国に存在する能登と同じような状況の地方都市で、また能登と同じ被害が発生する。
――復興のビジョンと計画をどう描くかが重要になる。
被災地はキャパを完全に超え、瀕死の状態にある。市町の職員は直接対応にあたっている。いま彼らに復興の将来像と計画を示せといっても無理だ。そのため、石川県の役割が非常に重要になる。
まずは短期的な復興ビジョンと計画を示す必要がある。「1カ月後はここまで回復する」「2カ月後はここまでの姿にする」といった将来像を見せることは極めて重要だ。それがないと被災者はどんどん不安になる。具体的な目標がないとがんばれない。
そのうえで、いまよりも地域をよくするという中長期的な復興ビジョンを示す。県単独ではできないだろうから、国の力を借りるべきところは政府に要請し、実現に向けて確実に取り組む。その取り組みが他の地方都市にとっても試金石になる。
- keyword
- 令和6年能登半島地震
- 初動対応
- インフラ整備
- 耐震化
- 河田惠昭
インタビューの他の記事
おすすめ記事
-

自社の危機管理の進捗管理表を公開
食品スーパーの西友では、危機管理の進捗を独自に制作したテンプレートで管理している。人事総務本部 リスク・コンプライアンス部リスクマネジメントダイレクターの村上邦彦氏らが中心となってつくったもので、現状の危機管理上の課題に対して、いつまでに誰が何をするのか、どこまで進んだのかが一目で確認できる。
2025/04/24
-

-

常識をくつがえす山火事世界各地で増える森林火災
2025年、日本各地で発生した大規模な山火事は、これまでの常識をくつがえした。山火事に詳しい日本大学の串田圭司教授は「かつてないほどの面積が燃え、被害が拡大した」と語る。なぜ、山火事は広がったのだろうか。
2025/04/23
-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2025/04/22
-

帰宅困難者へ寄り添い安心を提供する
BCPを「非常時だけの取り組み」ととらえると、対策もコストも必要最小限になりがち。しかし「企業価値向上の取り組み」ととらえると、可能性は大きく広がります。西武鉄道は2025年度、災害直後に帰宅困難者・滞留者に駅のスペースを開放。立ち寄りサービスや一時待機場所を提供する「駅まちレジリエンス」プロジェクトを本格化します。
2025/04/21
-

-

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視
4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。
2025/04/15
-

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入
日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。
2025/04/15
-

-

生コン・アスファルト工場の早期再稼働を支援
能登半島地震では、初動や支援における道路の重要性が再認識されました。寸断箇所の啓開にあたる建設業者の尽力はもちろんですが、その後の応急復旧には補修資材が欠かせません。大手プラントメーカーの日工は2025年度、取引先の生コン・アスファルト工場が資材供給を継続するための支援強化に乗り出します。
2025/04/14





















![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)






※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方