2023/04/17
インタビュー
インボイス制度の注意点(前)
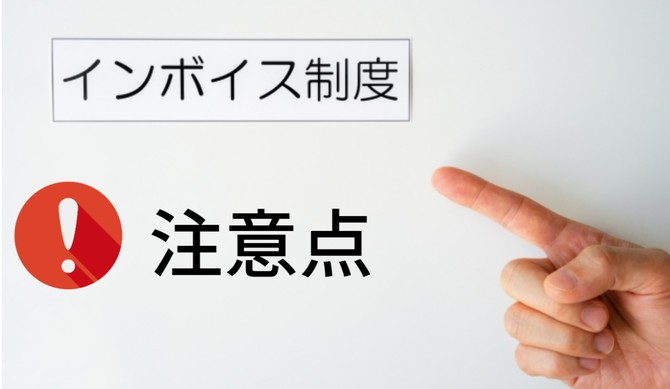
2023年10月1日から開始予定のインボイス制度は、免税事業者側だけでなく、免税事業者と取引を行う企業側にも注意が必要だ。企業担当者が気をつけるべきポイントについて、ネクセル総合法律事務所の藪木健吾弁護士に聞いた。

2023年10月1日からのインボイス制度開始に向けて、多くの企業が、適格請求書発行事業者登録番号の確認のために取引先に対するアンケート調査を行っています。
取引先が適格請求書発行事業者か否かによって経費計上できる額が変わってくるわけですから、企業としては、「できれば適格請求書発行事業者としか取引をしたくない」「取引先には、ぜひ適格請求書発行事業者として登録して欲しい」という思いが生じるのは当然のことかもしれません。
そのため、適格請求書発行事業者登録を行うかどうかが不明確な取引先に対しては、「適格請求書発行事業者登録を行う予定があるか、登録を行う場合にはいつまでに行う予定なのか」といった聞き取りを行っている企業も多いことと思われますが、アンケート調査時の文言やアンケート調査後の対応が独占禁止法や下請法に抵触しないよう、注意が必要です。
独占禁止法の特別法に位置する下請法については取引の内容や事業者の資本金規模という比較的明確な基準を満たす場合に問題となるため、取引内容や事業規模によって適用の有無は予測しやすいものです。他方、独占禁止法自体には下請法のような明確な基準があるわけではなく、全ての事業者が対象となり得るため、下請法に該当しない企業においてもリスク管理は不可欠です。
取引先に対して「適格請求書発行事業者登録を行って欲しい」という打診を行うことが直ちに問題となるわけではありません。また、「登録を行わずに免税事業者であり続ける場合には、インボイス制度が開始した後に生じる報酬額を調整したい」といった交渉を行うことも可能ですし、その結果として取引を終了させることになったとしても、直ちに独占禁止法や下請法違反に問われるわけではありません。
注意が必要な例としては、取引先に対して交渉の機会を設けず、免税事業者に不利益となる取引条件を一方的に決定・通知してしまうことが挙げられます。具体的には、取引先に送付するアンケートの中で「適格請求書発行事業者として適格請求書を発行いただけない場合には、消費税分をお支払いすることはできません」や「今後は適格請求書発行事業者のみと取引を行っていきます」など取引価格の引き下げや契約の打ち切りと捉えられかねない文言を用いているようなケースは要注意です。
このような文言をアンケートで用いていたからといって、前後の文脈や実質的な交渉対応の状況等を踏まえて判断する必要があるため、それだけで必ずしも法に抵触するわけではありません。ただ、一般的にこのような文言は、受注者側が「その申し出を受け入れるしかない」と感じるような心理的圧迫を招きやすく、仮に企業が交渉を行っていたとしても形式的な交渉にすぎないと考えられる可能性もあり、独占禁止法における『優先的地位の濫用』(優先的地位の濫用とは、自己の取引上の地位が相手方に優越している一方の当事者が、取引の相手方に対して、その地位を利用して正常な商慣習に照らし、不当に不利益を与える行為を指します。独占禁止法第2条第9項第5号)にあたると判断されるおそれが高いといえます。これらは一例であり、その他の場面でも、適格請求書発行事業者にならない場合に取引先に不利益を被らせるような内容(協賛金等の負担の要請や、特定の商品の購入やサービスの利用を強制するような場合、適格請求書発行事業者となることへの慫慂等)を通知、申し出るような場合には注意すべきです。インボイス制度の実施を契機として取引先に対する適格請求書発行事業者としての登録状況の調査のためのアンケートを実施する際や取引内容の見直しを検討したい場合には、独占禁止法や下請法に反しないように慎重に対応しましょう。
どのような対応が独占禁止法や下請法に抵触しうるかについては、中小企業庁がまとめた資料が参考になります。
参考:インボイス制度後の免税事業者との取引に係る下請法等の考え方/中小企業庁
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/download/duty_invoice_s03.pdf
参考:免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A/財務省・公正取引委員会・経済産業省・中小企業庁・国土交通省
https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/invoice_qanda.html
また、令和4年1月26日に改正された下請法の運用基準の改正によって、労務費、原材料費、エネルギーコストの上昇を取引価格に反映しない取引は、下請法上の「買いたたき」に該当するおそれがあることが明確化されています。
運用基準では、直接的にインボイス制度に触れられてはおりませんが、「インボイス制度後の免税事業者との取引に係る下請法等の考え方」の事例2では、一部の交渉行為が「買いたたき」として問題となるおそれがある旨紹介されていることからも、合わせて確認しておくと良いでしょう。
参考:(令和4年1月26日)「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」に関する取組について(2「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」の改正)/公正取引委員会
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2022/jan/220126.html
独占禁止法上の優越的地位の濫用に該当すると判断された場合には、公正取引委員会による排除措置命令(独占禁止法20条、61条)を受けるだけでなく、違反行為に係る期間(始期は調査開始日から最長10年前まで遡及)における違反行為の相手型との取引額に算定率(1%)を掛けた額の課徴金納付命令を受ける可能性があります(独占禁止法20条の6、62条)。また、下請法が適用され、「下請代金の減額」(下請法4条1項3号)や「買いたたき」(下請法4条1項5号)行為でると判断された場合には、公正取引委員会から違反行為に対する勧告(下請法7条)を受けるだけでなく、50万円以下の罰金(下請法10条)が課せられる可能性があります。
これらに違反したと判断された場合には、社名や違反した内容等が公正取引委員会のホームページ上で公表されるほか、メディアに取り上げられる可能性もあり、レピュテーションの観点でも企業が受けるダメージは決して少なくありません。
インボイス制度についての相談窓口はもちろん、公正取引委員会は独占禁止法や下請法に関する情報提供フォームや相談窓口等を広く設けており、誰もが気軽に相談できる設計を行っておりますので、企業としては、自社が下請法や独占禁止法に違反したと通報されないようご注意ください。
インタビューの他の記事
おすすめ記事
-

自社の危機管理の進捗管理表を公開
食品スーパーの西友では、危機管理の進捗を独自に制作したテンプレートで管理している。人事総務本部 リスク・コンプライアンス部リスクマネジメントダイレクターの村上邦彦氏らが中心となってつくったもので、現状の危機管理上の課題に対して、いつまでに誰が何をするのか、どこまで進んだのかが一目で確認できる。
2025/04/24
-

-

常識をくつがえす山火事世界各地で増える森林火災
2025年、日本各地で発生した大規模な山火事は、これまでの常識をくつがえした。山火事に詳しい日本大学の串田圭司教授は「かつてないほどの面積が燃え、被害が拡大した」と語る。なぜ、山火事は広がったのだろうか。
2025/04/23
-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2025/04/22
-

帰宅困難者へ寄り添い安心を提供する
BCPを「非常時だけの取り組み」ととらえると、対策もコストも必要最小限になりがち。しかし「企業価値向上の取り組み」ととらえると、可能性は大きく広がります。西武鉄道は2025年度、災害直後に帰宅困難者・滞留者に駅のスペースを開放。立ち寄りサービスや一時待機場所を提供する「駅まちレジリエンス」プロジェクトを本格化します。
2025/04/21
-

-

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視
4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。
2025/04/15
-

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入
日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。
2025/04/15
-

-

生コン・アスファルト工場の早期再稼働を支援
能登半島地震では、初動や支援における道路の重要性が再認識されました。寸断箇所の啓開にあたる建設業者の尽力はもちろんですが、その後の応急復旧には補修資材が欠かせません。大手プラントメーカーの日工は2025年度、取引先の生コン・アスファルト工場が資材供給を継続するための支援強化に乗り出します。
2025/04/14




















![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)






※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方