2014/11/25
誌面情報 vol46
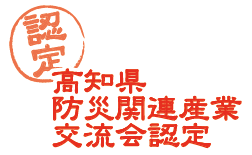
シェルターステップほか 株式会社西宮産業
高知県が認定した防災関連製品の中に、プラスチック加工技術を生かし、防災製品を開発するユニークな会社がある。高知市内に本社を構える西宮産業だ。同社の開発した再生プラスチック製の避難階段「シェルターステップ」はコンクリート工事が難しい急な傾斜地や、大型トラックが入れないような山間部でも施工可能。高知県内ですでに40カ所以上に設置され、東北の被災地でも導入の検討が始まっている。

津波対策には避難経路の確保が重要だが、裏山など急斜面で足場の悪い場所に逃げ込む場合、避難階段が重要な役割を果たす。東日本大震災では、先達が残した裏山に上がる細い避難階段が人命を救った例もある。避難階段はコンクリートで造るのが一般的だが、コンクリート工事には大掛かりな山の造成工事が必要になるほか、山間部など重機が入りにくい場所では作業が困難だ。
そのような問題を解決したのが、西宮産業が開発した再生プラスチック製の階段「シェルターステップ」だ。山肌に鋼製の杭を打ち込み、プラスチック製の階段を下から設置していくため施工がしやすく、傾斜50度までの斜面に対応する。例えば右写真の施工現場(白浜海岸防災対策工事)は、急斜面である上に高さが26mあるため、仮にコンクリートで避難階段を作る場合はポンプ車に26m以上の配管をつなぎ、上からコンクリートを流し込む作業が必要になり、かなりの費用がかかる。山間部では道路も通じていないため、ミキサー車など大型車両が通れずコンクリート工事は困難だ。
専門業者でなくても施工可能
西宮産業代表取締役の宮田稔久氏は「シェルターステップは軽トラックが入れる道があれば資材を運ぶことができ、プラモデルを作るように専門工事業者でなくても階段が設置できる」と話す。
また、山の地表面を削るような大規模な造成工事の必要はなく、作りたい場所の木を切り倒して地表をならす程度の準備があれば施工できる。階段の下は風通しが良いため、土などが堆積することもない。土砂崩れ防止用のネットを敷くため、除草作業も省略化できる。

災害などが発生した場合にパーツの1部が外れる可能性は考えられるが、強度については実証実験を繰り返し十分な安全性を確保できているとする。通常の使用範囲であれば点検の必要もなく、メンテナンスフリーだ。
高知県内では既に40カ所以上で設置が完了。散歩道として普段から利用している住民からは「コンクリートよりも柔らかいので膝にもいい」との評価も得ているそうだ。現在は被災した気仙沼などで設置の検討が始まっているという。
同社は再生プラスチック製の階段を、東日本大震災が発生する前から試験的に製作していた。当時は高速道路の点検用階段などに使われたが、その後あまりニーズはなかったという。
防災用に展開しようと考えた理由は「東日本大震災が発生し、小学生が避難階段で高台に逃げたという記事を見た時に、そのイメージが私が考えていたものと一致した。もう一度、避難階段用に1から開発し直した」(宮田氏)。
現在では被災者が歩きやすいように段差や角度、幅も改良され、手すりや蓄光材を取り付けるなど避難者に配慮された設計になっている。
プラスチックで安心・安全製品を
同社は、このほかにもさまざまな防災・危機管理製品を開発している。
宮田氏は大学卒業後、東京でプラスチック加工会社の開発者として20年あまりを過ごした後、高知に帰省。プラスチック商品の販売会社を起業した。技術畑出身だったため、自分でプラスチック製品を開発したいと考えていたところ、2009年に四国高速道路の高松自動車道通谷橋付近で橋梁から重さ約6kgのコンクリート片が落下するという事故が発生した。幸いけが人などは出なかったが、西日本高速道路は緊急点検を実施するなどコンクリートの剥落対策が必要になった。その補強材料に何か良いものがないかと宮田氏に声がかかり、開発したのが「NSネット」だ。従来のコンクリート剥落防止対策は、黒いポリエステルを漁網のように編みこんで作ったネットが一般的。ただし耐久性は良くなく、黒1色しか作れないために外観検査を行いにくかった。「NSネット」は、基布素材に高強力ビニロン系を用いたため、従来のネットより対候性に優れたものとなった。また、白色で製造できるため、躯体の経年劣化状況も外から確認しやすくなったという。赤外線などの機器を使用した検査にも対応できる。

現在はトンネルなどの内側から貼ってコンクリート剥落対策ができる「NSメッシュ」、剥落対策と同時に湧水を防ぐ「NSメッシュD」とラインナップが広がり、被災した会津若松のトンネルや、釜石付近の高速道路でも採用されている。
2012年には、笹子トンネルで天井落下事故が発生。9人が死亡し2人が重軽傷を負った。笹子トンネルの場合、原因は違うものだったが、古いトンネルではコンクリート剥落による落下事故の危険性があると西宮氏は指摘する。
西宮氏は、「NSネットの商品化を始めたころから、プラスチック素材を加工した安全・安心に関する製品を作っていくという会社のテーマを決めた。まだまだ会社の認知度は低いが、災害の多い高知県で生まれた防災関連製品として、県とも協力しながら認知度向上に努めたい」と話している。

誌面情報 vol46の他の記事
おすすめ記事
-

自社の危機管理の進捗管理表を公開
食品スーパーの西友では、危機管理の進捗を独自に制作したテンプレートで管理している。人事総務本部 リスク・コンプライアンス部リスクマネジメントダイレクターの村上邦彦氏らが中心となってつくったもので、現状の危機管理上の課題に対して、いつまでに誰が何をするのか、どこまで進んだのかが一目で確認できる。
2025/04/24
-

-

常識をくつがえす山火事世界各地で増える森林火災
2025年、日本各地で発生した大規模な山火事は、これまでの常識をくつがえした。山火事に詳しい日本大学の串田圭司教授は「かつてないほどの面積が燃え、被害が拡大した」と語る。なぜ、山火事は広がったのだろうか。
2025/04/23
-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2025/04/22
-

帰宅困難者へ寄り添い安心を提供する
BCPを「非常時だけの取り組み」ととらえると、対策もコストも必要最小限になりがち。しかし「企業価値向上の取り組み」ととらえると、可能性は大きく広がります。西武鉄道は2025年度、災害直後に帰宅困難者・滞留者に駅のスペースを開放。立ち寄りサービスや一時待機場所を提供する「駅まちレジリエンス」プロジェクトを本格化します。
2025/04/21
-

-

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視
4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。
2025/04/15
-

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入
日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。
2025/04/15
-

-

生コン・アスファルト工場の早期再稼働を支援
能登半島地震では、初動や支援における道路の重要性が再認識されました。寸断箇所の啓開にあたる建設業者の尽力はもちろんですが、その後の応急復旧には補修資材が欠かせません。大手プラントメーカーの日工は2025年度、取引先の生コン・アスファルト工場が資材供給を継続するための支援強化に乗り出します。
2025/04/14




















![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)






※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方