新型コロナ対応のちぐはぐさはどこから?
第1回:免疫システムと防災システム

河村 廣
1967年3月神戸大学大学院工学研究科修士課程建築学専攻修了。同年、川崎重工業入社。その後、山下設計を経て70年4月神戸大学工学部助手となり、助教授、教授を経て2005年3月に定年退職、同年4月より同大学名誉教授。88年9月から10カ月、テキサスA&M大学客員研究員、04年度は東北大学客員教授、05~06年度は東北大学非常勤講師。工学博士、一級建築士。
2020/11/25
免疫防災論

河村 廣
1967年3月神戸大学大学院工学研究科修士課程建築学専攻修了。同年、川崎重工業入社。その後、山下設計を経て70年4月神戸大学工学部助手となり、助教授、教授を経て2005年3月に定年退職、同年4月より同大学名誉教授。88年9月から10カ月、テキサスA&M大学客員研究員、04年度は東北大学客員教授、05~06年度は東北大学非常勤講師。工学博士、一級建築士。
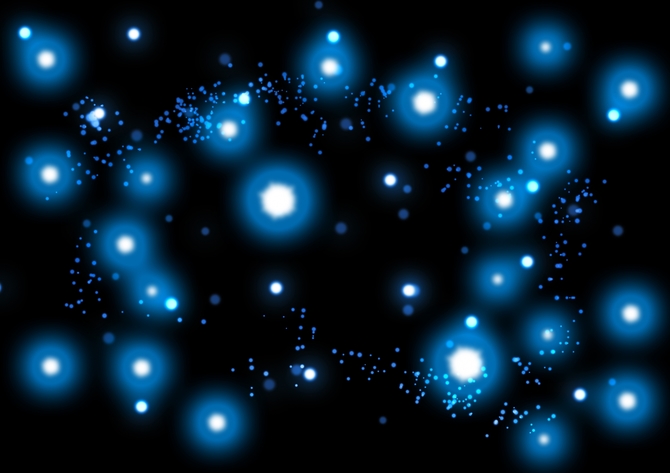
新型コロナウイルスの対応に明け暮れた2020年も11月半ばを過ぎ終盤を迎えた。世界的感染爆発(パンデミック)は収まる気配がなく、日本でも冬本番を前に第3波の到来が指摘され、経済対策とのバランスが大きな課題となっている。
このたびのコロナ対応に関係各位が必死に努力しておられることには敬意を表したい。しかし、行政的な対応あるいは対症療法的な措置がかえって問題をこじらせ、意図と結果をちぐはぐにしている感を拭えないのは筆者だけだろうか。端的にいえば、科学的なアプローチがいささか足りないと思うのである。
筆者は感染症に対しては門外漢であり、素人のそしりは免れない。それでも、そのことを自覚したうえで、パンデミックを含めた想定外の災害というものに対応できる「社会防災システム」とはいったいどのようなものなのか、この機会に考察してみたいと思う。
その前に、防災の基本的な手続きについて筆者の考えを整理したい。今回のコロナ禍において、本来は不可欠であるはずのアプローチが大きく欠落していると感じるからだ。
大規模な地震災害であれば、まずは向こう50年、100年の間にどれだけの揺れがどこに、どれだけの確率で発生するか予測し、そしてそれが発生したときに社会がどれだけの損失をこうむるかを試算することが前提だ。損失に確率を掛けた数値を「期待値」というが、これを把握したうえでいかに抑えるかが、防災における「公助」の重要な部分を占める。
地震の場合は事故と違って起きる確率を減らすことはできないから、こうむる損失をいかに減らすかがカギ。そのためには、ハード・ソフト両面から投資をしなければならない。例えば堤防や道路などのインフラを整備したり、いざというときの連携体制や避難体制を強化したり。そうした投資を行ったうえで、どれだけ「期待値」の抑制に効果があるのかを常に検証しながら取り組みを進めていくプロセスが不可欠だ。

こうした基本的なアプローチは、パンデミックにおいてもおそらく変わらない。実際、過去の文献やデータをひも解けば、将来におけるパンデミックの発生確率やそれによる社会的損失を導くことは困難ではないだろう。これに対して有効な投資を行うこと、例えば医師・看護師を確保したり病床を増やしたりして医療資源を守ることが、感染症対策における「公助」の重要な部分を占める。
しかし、今回のコロナ対策においては、そうした議論がほとんどみられず、政府・行政は場あたり的な対応に終始している。

どのような対策をどのレベルで行うかの判断には、もちろん政治的・経済的な意図が入り、国情も関係する。難しさがあるのは承知だが、前述のような手続きを踏まず、当座の感染者数をベースに政治・行政と専門家がなれ合って、子どもにいいきかせるがごとく「マスクをしなさい」「三密を避けなさい」「手を洗いましょう」と繰り返すさまは、ただコロナを恐れているだけといわざるを得ない。
そもそも手洗いやうがい、マスク着用、三密回避などは生活習慣上の知恵であり、庶民が行うことだ。防災でいえば「自助」に該当する。政治・行政が行うべきはあくまで「公助」であって、庶民が経験則にもとづいて行う公衆衛生上のアプローチを『科学的知見』と称してことさらに取り立て「みなさん何とかしのぎましょう」というのは、科学的でないばかりか、人道的でもない。
免疫防災論の他の記事
おすすめ記事

自社の危機管理の進捗管理表を公開
食品スーパーの西友では、危機管理の進捗を独自に制作したテンプレートで管理している。人事総務本部 リスク・コンプライアンス部リスクマネジメントダイレクターの村上邦彦氏らが中心となってつくったもので、現状の危機管理上の課題に対して、いつまでに誰が何をするのか、どこまで進んだのかが一目で確認できる。
2025/04/24


常識をくつがえす山火事世界各地で増える森林火災
2025年、日本各地で発生した大規模な山火事は、これまでの常識をくつがえした。山火事に詳しい日本大学の串田圭司教授は「かつてないほどの面積が燃え、被害が拡大した」と語る。なぜ、山火事は広がったのだろうか。
2025/04/23

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2025/04/22

帰宅困難者へ寄り添い安心を提供する
BCPを「非常時だけの取り組み」ととらえると、対策もコストも必要最小限になりがち。しかし「企業価値向上の取り組み」ととらえると、可能性は大きく広がります。西武鉄道は2025年度、災害直後に帰宅困難者・滞留者に駅のスペースを開放。立ち寄りサービスや一時待機場所を提供する「駅まちレジリエンス」プロジェクトを本格化します。
2025/04/21


大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視
4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。
2025/04/15

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入
日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。
2025/04/15


生コン・アスファルト工場の早期再稼働を支援
能登半島地震では、初動や支援における道路の重要性が再認識されました。寸断箇所の啓開にあたる建設業者の尽力はもちろんですが、その後の応急復旧には補修資材が欠かせません。大手プラントメーカーの日工は2025年度、取引先の生コン・アスファルト工場が資材供給を継続するための支援強化に乗り出します。
2025/04/14
※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方