2017/04/14
熊本地震から1年
関連死166人孤立死14人という数字は非常に重い。
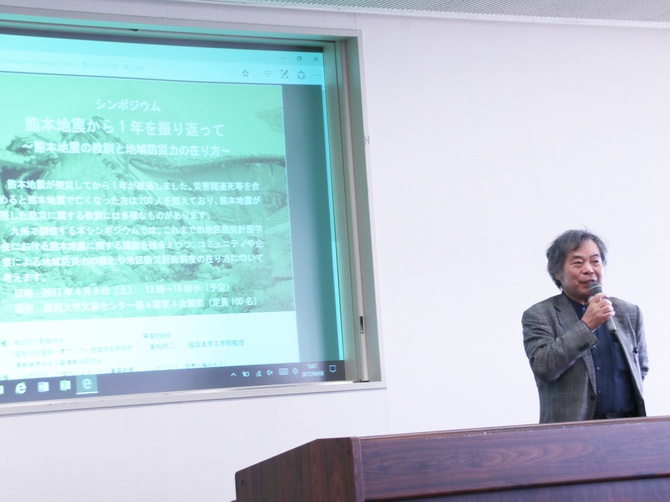
熊本地震では直接死が55人に対し、関連死が自殺も含めて166人でした。本来だったらこの166人は救える命。さらにみなし仮設や応急仮設に避難していた方などで孤立死してしまった方が14人も(※2017年4月12日現在)出てしまい、今後もっと出る可能性もあります。これは絶対に曖昧にしてはいけない数字です。
本来であればこれらの人は社会的なケアが受けられたはずで、ケアが受けられれば命を落とすことがなかったはずでした。しかし社会的なセーフティネットからこぼれ落ちてしまったことで適切なケアが受けられず、命を落としてしまった人たちが生まれ始めているのです。これから公営住宅に入ると引きこもりという形での孤立死が出てくるので、今しっかりしないと今後とんでもない数字が出てくる可能性も高いのです。
本来であれば、亡くなった方たち一人ひとりの状況を分析しなければいけませんが、個人情報その他の壁もあり、行政を含めてその分析には積極的ではありません。しかし原因が分からない限り次の関連死が防げず、特に孤立死に関しては徹底的に原因を追究しないと次の孤立死を防ぐことはできません。
みなし仮設…震災などで住居を失った被災者が、民間事業者の賃貸住宅を仮の住まいとして入居した場合に、その賃貸住宅を国や自治体が提供する「仮設住宅」(応急仮設住宅)に準じるものと見なすこと。また、そうした賃貸住宅や関連する制度。(出典:Weblio)

関連死は「防ぎえた死(Preventable Death)」
現在は超高齢化社会なので、みなし仮設で1人暮らしの高齢者がとても多い。高齢者になればなるほど、コミュニティのネットワークから切り離されると全く見えなくなります。みなし仮設は空いている資源を活用できるという点では非常にプラスな制度ですが、その人たちをきちんと捉えられるシステムがなければ、誰がどこに行ったか全くわからなくなってしまうのです。
これは自らを責めることになりますが、何のために被災者台帳を作っているのだろうと考えてしまいます。本来であれば被災者一人ひとりのカルテとなる台帳を作り、全員の居場所を把握することで孤立死を防ぐケアをしなければいけません。
関連死にもさまざまな問題があります。基本的には避難生活そのものの暮らしの厳しさと、それが継続する時間の長さです。本来、災害救助法では避難所は原則として1週間となっています。それゆえに、できることなら災害が発生した次の日から仮設住宅を建てなければなりません。復興計画もなるべく早く作らねばなりません。現在はずるずると計画が遅れていて、時間の概念があいまいになっていることも関連死につながるのではないでしょうか。
また、病院や福祉施設の耐震化が遅れ、地震によって機能を果たせなくなり、新しい病院や施設に転院したりする過程で、30人近くの方が関連死しています。その意味でも、病院や福祉施設の耐震化は非常に大事だと思っています。
関連死は、「防ぎえた死(Preventable Death)」を防げなかったということで、災害後の対応の在り方を厳しく問いかけるものです。被災地には保健士や看護師によるボランタリーケアと住民によるコミュニティケアが必要なのですが、関連死や孤立死を防ぐためにはコミュニティによるケアが重要になります。
本来であれば、日本中どこに行っても元のコミュニティの人が移動した人を把握しケアするようなシステムがなければいけません。しかしバラバラになってしまった人をコミュニティがどのように捕捉してケアしていくかということは、事前の計画がないと難しいと考えています。孤立死を防ぐためには、このようなコミュニティケアのシステムをきちんと機能させなければいけないのです。
もちろん、直接死にも課題はありました。危険な家屋へ立ち戻ったところに2回目の地震が発生し、亡くなった方がいました。本来はそのような事態を防ぐための「応急危険度判定」だったのですが、余震や2次災害に対する警戒の弱さがあったのではないでしょうか。私たちが作った応急危険度判定ですが、もう一度見直さなければいけないと考えています。
地区防災計画はどうあるべきか
このような問題を解決するために重要なのが「地区防災計画」であると考えています。私自身、熊本地震では3つの教訓がありました。「地域コミュニティの重要性」「事前計画の必要性」そして最後は「ボトムアップ」です。これらは「地区防災計画」の根幹そのものです。
これまでは正直、まず何でもいいから作ってほしいと言っていましたが、これからは「作ればいい」というレベルではなく、「これだけはちゃんとやろう」という専門家によるアドバイスがもっと必要になると感じています。熊本でも素晴らしいコミュニティはたくさんありました。市内のとある小学校では震災の次の日から温かいお味噌汁が出ました。ほかの小学校では何日も冷たいおにぎりだけなのに、なぜ温かい食事を作れたのかというと、事前に話し合いをして計画を作っていたからです。地区防災計画でいうと、1週間分の避難所の献立計画を各町内できちんと作っておきましょうと言っています。
私は、地域コミュニティが主体的に防災に取り組む「ボトムアップ型」の防災が欠かせないと思っています。そのためには、以下の5つが重要です。
② 密着性…地域に根差した対応ができる
③ 即応性…限られた時間内に対応できる
④ 協働性…みんなで力を合わせて対応できる
⑤ 内発性…それぞれの思いをつないで対応できる。
言い換えれば、「自立」「自助」「自治」「自尊」が大切です。自尊とは、自分たちのことを誇りに思うことです。誇りをもって、コミュニティをオペレーションしてほしいと思います。そのために、地区防災計画を作らなくてはいけないと思っています。
(了)
熊本地震から1年の他の記事
- 「想定内」の中の「想定外」が問題~熊本地震から感じたこと三題~
- 熊本地震、LINEでの情報収集が4割
- 防災を起点に地域コミュニティを活性化~地区防災計画の概要<熊本地震から1年>
- 関連死166人孤立死14人という数字は非常に重い。熊本地震が投げかけた課題と地区防災計画のあり方
- LINE、熊本市と防災で協定
おすすめ記事
-

自社の危機管理の進捗管理表を公開
食品スーパーの西友では、危機管理の進捗を独自に制作したテンプレートで管理している。人事総務本部 リスク・コンプライアンス部リスクマネジメントダイレクターの村上邦彦氏らが中心となってつくったもので、現状の危機管理上の課題に対して、いつまでに誰が何をするのか、どこまで進んだのかが一目で確認できる。
2025/04/24
-

-

常識をくつがえす山火事世界各地で増える森林火災
2025年、日本各地で発生した大規模な山火事は、これまでの常識をくつがえした。山火事に詳しい日本大学の串田圭司教授は「かつてないほどの面積が燃え、被害が拡大した」と語る。なぜ、山火事は広がったのだろうか。
2025/04/23
-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2025/04/22
-

帰宅困難者へ寄り添い安心を提供する
BCPを「非常時だけの取り組み」ととらえると、対策もコストも必要最小限になりがち。しかし「企業価値向上の取り組み」ととらえると、可能性は大きく広がります。西武鉄道は2025年度、災害直後に帰宅困難者・滞留者に駅のスペースを開放。立ち寄りサービスや一時待機場所を提供する「駅まちレジリエンス」プロジェクトを本格化します。
2025/04/21
-

-

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視
4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。
2025/04/15
-

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入
日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。
2025/04/15
-

-

生コン・アスファルト工場の早期再稼働を支援
能登半島地震では、初動や支援における道路の重要性が再認識されました。寸断箇所の啓開にあたる建設業者の尽力はもちろんですが、その後の応急復旧には補修資材が欠かせません。大手プラントメーカーの日工は2025年度、取引先の生コン・アスファルト工場が資材供給を継続するための支援強化に乗り出します。
2025/04/14



















![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)






※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方