IT・テクノロジー
-
三菱UFJ銀、ネットバンク復旧=サイバー攻撃で不具合
三菱UFJ銀行は28日、個人向けインターネットバンキング「三菱UFJダイレクト」で発生した不具合が解消され、復旧したと明らかにした。サイバー攻撃を受け、26日から生体認証によるログインができない場合があるなど不安定な状態が続いていた。
2024/12/28
-
米オープンAI、営利主導へ=公益と開発資金調達を両立
【シリコンバレー時事】生成AI(人工知能)サービス「チャットGPT」を開発した米オープンAIは27日、営利企業が経営を主導する体制に転換する計画を公表した。人間の知能を超えてさまざまな仕事をこなせる汎用(はんよう)AI(AGI)の実現に向け、膨大な開発資金を調達しやすくする狙いがある。
2024/12/28
-
三菱UFJ銀、不具合「ほぼ解消」=サイバー攻撃が原因
三菱UFJ銀行は27日、個人向けインターネットバンキング「三菱UFJダイレクト」で発生した不具合が「ほぼ解消した」と明らかにした。サイバー攻撃を受け、26日から生体認証によるログインができない場合がある状態が続いていた。
2024/12/27
-

火災時の初動対応を支援する防災クラウド
ホーチキは、火災の発生をSMSやEメールで速やかに通知し、火災情報の迅速な伝達、早期の避難誘導を支援する防災クラウドサービス「HOCHIKI as a Service」(HCKaaS)を提供する。火災受信機が保有する火災情報を集約したクラウドに災害情報提供APIを装備し、建物OSや他サービスとの連携を容易にしたもの。
2024/12/27
-
AIリスク対応、国が調査=次期国会に関連法案―司令塔機能強化へ戦略本部
政府は26日、人工知能(AI)に関して国民の権利侵害など重大事案が発生した際に国が調査を実施するための法案を来年1月召集の通常国会に提出する方針を固めた。AI政策の司令塔機能強化を目的に、全閣僚で構成する「戦略本部」も新設する。
2024/12/26
-
三菱UFJ銀、ネットバンク不具合=サイバー攻撃か、「データ流出ない」
三菱UFJ銀行で26日、個人向けのインターネットバンキング「三菱UFJダイレクト」の不具合が発生した。生体認証によるログインができたり、できなかったりと不安定な状態になっている。同行は「外部からの不正な大量データ送付に起因するものだ」と説明。サイバー攻撃を受けたとみられる。
2024/12/26
-
日航にサイバー攻撃=一部で遅延・航空券販売も一時停止―午後システム復旧
日本航空は26日、社内外をつなぐネットワーク機器がサイバー攻撃を受けたと発表した。利用客の搭乗手続きや荷物の預け入れに不具合が生じ、国内線、国際線とも一部の便で最大4時間超の遅れが発生。同日出発の航空券の販売も一時停止するなど影響が広がったが、午後1時20分にシステムは復旧した。
2024/12/26
-
AI事業者協力へ法整備=司令塔機能強化、国家戦略も―政府有識者会議
政府は26日、人工知能(AI)政策の方向性を議論する「AI戦略会議」(座長・松尾豊東大大学院教授)の会合を首相官邸で開き、下部組織に当たる有識者会議「AI制度研究会」の中間取りまとめを決定した。政府の司令塔機能強化や国家戦略の策定に加え、事業者への協力要請などに関しても、法整備の必要性を明記した。
2024/12/26
-
日航にサイバー攻撃=一部で遅延、航空券販売停止
日本航空は26日、社内外をつなぐネットワーク機器がサイバー攻撃を受け、システム障害が発生したと発表した。利用客のチェックインや荷物の預け入れに不具合が出るなどし、国内線、国際線ともに一部の便で遅れが生じている。
2024/12/26
-
自動運転の路線バス運行=全国初「レベル4」―松山
伊予鉄グループ(松山市)は25日、特定の条件下で無人の自動運転が可能になる「レベル4」に対応した路線バスの営業運行を市内で開始した。レベル4での路線バスの営業運行は全国初。伊予鉄バス(同)が高浜駅―松山観光港(片道約800メートル)に電気自動車(EV)を導入。
2024/12/25
-
三井住友海上、顧客情報12万件流出か=ランサムウエア被害
三井住友海上火災保険は25日、業務委託先の東京損保鑑定(東京)のサーバーがランサムウエア(身代金要求型ウイルス)被害に遭った件で、流出した可能性のある顧客情報が約12万件に上ると発表した。
2024/12/25
-
AIでSNS投稿分析=危機の兆候、早期発見へ―金融庁
金融庁が、人工知能(AI)を活用し金融機関などに関するSNSへの投稿を分析する試みを始めることが25日、分かった。2025年春にも実証実験を開始する。大規模言語モデル(LLM)による分析で、大量の投稿の中から金融危機に発展しかねないリスクの兆候や、金融機関が抱える問題の早期発見につなげる狙いだ。
2024/12/25
-
交換業者に自主点検要請=DMMビットコインの流出問題で―金融庁
金融庁は24日、5月に暗号資産(仮想通貨)交換業者のDMMビットコイン(東京)が北朝鮮のハッカー集団のサイバー攻撃を受けてビットコインが流出した問題で、業界団体の日本暗号資産等取引業協会を通じ、交換業者にセキュリティー体制などの自主点検を行うよう要請した。金融庁は9月にも自主点検を求めていた。
2024/12/24
-
FIXERの生成AI、政府安全基準でリスト登録=政府調達で有利に
FIXERは24日、同社の生成AI(人工知能)サービス「GaiXer(ガイザー)」が政府情報システムのためのセキュリティー評価制度「ISMAP-LIU(イスマップ・ロー・インパクト・ユース)」の特別措置サービスリストに登録されたと発表した。
2024/12/24
-
DMMビットコイン、北朝鮮側の攻撃=米と共同でハッカー集団特定―警察庁
暗号資産(仮想通貨)交換業者のDMMビットコイン(東京)からビットコイン(BTC)約482億円相当が流出した問題で、警察庁は24日、北朝鮮のハッカー集団「トレイダートレイター」によるサイバー攻撃と特定したと公表した。
2024/12/24
-

第52回:デジタル時代のピカレスク(後編)
ISF CEOのスティーブ・ダービンがテクノロジージャーナリストのジェフ・ホワイト氏に行ったインタビューの前編では、システムや人の隙をついていつの間にか国家を背景とする犯罪ネットワークが会社に侵入してしまう世相を紹介しました。後編では、デジタル犯罪者の視点からテクノロジーや暗号通貨の進展を見る意義を語っていただきます。
2024/12/24
-
加速する中国「低空経済」=ドローン配送、空飛ぶクルマも
中国で、主に高度1000メートルまでの低空域を利用したビジネス「低空経済」が注目を集めている。ドローンによるデリバリーサービスが始まっているほか、「空飛ぶクルマ」の量産化に向けた取り組みも加速している。
2024/12/23
-

第1回:パスワードの使い回しに注意!!
SNSやウェブ上のサービスを利用するときに入力するIDとパスワード。複数のサービスを利用していると、その数に比例してパスワードの数も増えていきます。今回は、パスワードを不正利用されないための対策と管理方法の一例を紹介します。
2024/12/17
-
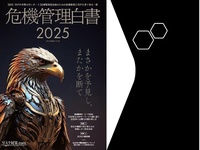
危機管理白書2025年版
A4サイズ、100ページ(本文96ページ)、カラー12月17日からECサイト「BASE(ベイス)」より発売。※2024年12月23日から順次発送いたします(12月28日~2025年1月6日は年末年始休業となります)。
2024/12/17
-

第51回:デジタル時代のピカレスク(前編)
サイバー犯罪のニュースがお茶の間に流れる時代になりました。オレオレ詐欺のレベルから企業の事業資金、ひいては国家資金の強奪まで、大小さまざまな事件が世界中で日々起きています。そんなニュースの背景を理解するため、ISF CEOのスティーブ・ダービンがテクノロジージャーナリストのジェフ・ホワイト氏に行ったインタビューを紹介します。
2024/12/13
-
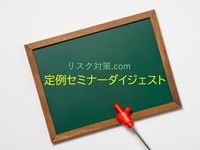
リスク対策.com 11月のセミナーダイジェスト
リスク対策.comは毎月、一般会員(登録無料)とPRO会員向けのセミナー・勉強会を行っています。11月に開催した「危機管理塾(リスク対策.PRO会員無料、PRO会員以外1万円)」「ESGリスク勉強会(視聴無料/一般会員登録必要)」「リスクトレンド研究会(同)」の概要を紹介します。このうち「ESGリスク勉強会」は、PRO会員(ライトは除く)のアーカイブ視聴が可能です。
2024/12/12
-

生成AI活用で出現した新たなリスク
前回、企業活動におけるコンプライアンスの重要性について解説しましたが、その際、コンプライアンスは法令遵守だけでなく、企業のルールや社会規範も重要であること、そして、守るべきルールや規範そのものが変わり得るということもお伝えしました。今回は、企業のコンプライアンス違反の落とし穴について、事例をあげて説明したいと思います。
2024/12/12
-

日韓サイバーセキュリティの違いから考える企業対策韓国テクノロジー会社からのアドバイス
今回は韓国を代表するセキュリティー企業であるS2Wの三好 平太氏に、対岸からみる日本のサイバーセキュリティについてお話しいただきます。
2024/12/10
-

サイバー保険などの注意点
デジタルファーストが進展して、組織がサイバー機能停止に直面するリスクは着実に増している。機能停止に遭遇かどうかというリスクではなく、いつ遭遇するかというリスクである。準備を怠らないことが求められる。そのためには、サイバー保険を強化する、事前準備的なリスクマネジメント体制を整備する、効果的な復旧戦略を策定することが不可欠となる。
2024/12/04
-

デジタルツールと人の組み合わせで価格を抑えた中小企業向けリスクソリューション
損害保険ジャパンとSOMPOリスクマネジメントは、中小企業向けにデジタルツールと人を組み合わせた新たな手法によるリスクマネジメントサービスを提供する。従来のオーダーメイド型のコンサルティングサービスのみでは普及に限りがあることから、幅広く効率的に安価なサービスを提供する手法として開発したもの。パートナーによる簡易リスクコンサルティングと「中小企業向けサービスサイト」を通じた動画・研修サービスなどのソリューションで構成する。
2024/11/22



















![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)



