2022/01/16
2022年1月号 レジリエンスとオールハザードBCP
2022年 年頭インタビュー
国立研究開発法人 防災科学技術研究所理事長 林春男氏に聞く
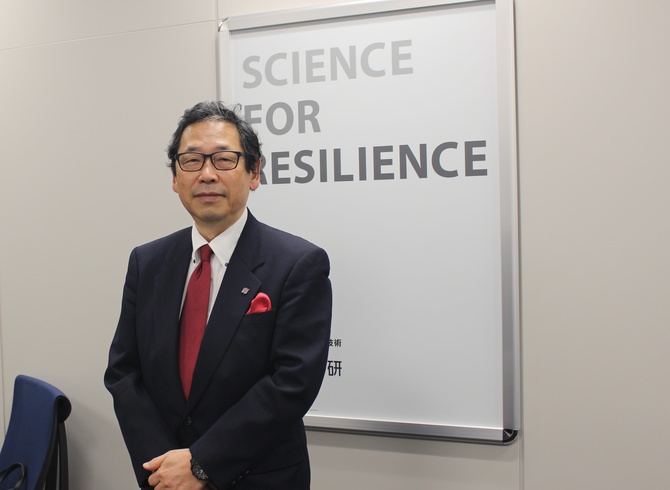
1951年東京生まれ。74年早稲田大学文学部心理学科卒、79年同大学大学院博士課程単位取得終了。83年カリフォルニア大学大学院心理学科博士課程修了(Ph.D)、弘前大学人文学部助教授、広島大学総合科学部助教授、京都大学防災研究所地域防災システム研究センター助教授を経て、96年に京都大学防災研究所巨大災害研究センター教授。2015年から現職。専門分野は社会心理学。著書に「いのちを守る地震防災学」( 岩波書店)「率先市民主義」(晃洋書房)など。
企業の事業継続力は、社会が危機を乗り越える力になる。
「オールハザードBCM」の意味はそこにある。
新型コロナウイルス感染症を筆頭に、昨年2021年も豪雨や地震、事件・事故など、さまざまな危機が日本社会を襲った。そこにみえてくるものは何か、企業・組織は何を教訓に、何を目指して、何に取り組めばよいのか。いま、急速に注目を集めている考え方が「レジリエンス」と「オールハザード」だ。リスク対策.com はこの2つをキーワードに、防災科学技術研究所の林春男理事長にインタビュー。昨年の災害・事故を振り返りながら、日本社会が抱える課題、企業が果たすべき役割と取り組みの方向性について語ってもらった。年頭の言葉として紹介する。
2021年の災害を振り返る
――昨年の事故・災害の様相をどう振り返りますか? 特徴的な出来事や印象に残る事象は?
過去5年で比較すれば、昨年2021年は、災害は起こるも大事には至らずに済んだ印象がある。社会がギリギリで踏みとどまっているともいえるかもしれない。
記憶に刻まれたのはやはり新型コロナで、昨年はそれがすべてだったといっても過言ではないが、自然災害に絞れば一昨年暮れから昨年1月にかけて起こった豪雪が印象深い。大規模な立往生によって12月は新潟で高速道路が止まり、1月にも新潟から福井にかけて高速道路・国道が止まった。
物流の根幹が長時間止まるわけだから、事業継続マネジメント(BCM)の観点でみると影響は極めて大きい。高速道路会社にとって最大の脅威は雨だが、雪もまた雨と同等のインパクトを持つ。高速道路は気象災害に弱いことを如実に示したのが昨年の豪雪だったのではないか。
熱海の土砂災害も衝撃が大きかった。民家が立ち並ぶ傾斜地の谷筋を大規模な土石流が襲い、被害が大きくなっただけでなく、その様子が映像として映し出された点で特徴的だった。

出典:国土地理院ウェブサイト https://www.gsi.go.jp/
冒頭、災害が大事に至らずに済んだ印象があると述べたが、個々の被災者の人生にとってどんな規模の災害であっても極めて大きな出来事であるのはいうまでもない。ただ、マクロ的にみれば、昨年はここ5年のなかでは比較的被害が少なかった年といえる。
――「被害が少なかった」という印象を受けるのは、激甚な自然現象にたまたま見舞われず、幸運だったからでしょうか?
2019 年の台風19号(令和元年東日本台風)で、北陸新幹線の車両基地が水没したのは記憶に新しい。これだけで被害額は百数十億にのぼるが、その後の運休・減便まで含めると経済損失はさらに膨らみ、長期かつ広範にわたって社会が影響を受ける。交通や物流の要衝がやられるインパクトは極めて大きい。
このことは、企業のBCMのうえで極めて重要。つまり、事業継続において「自社本社や自社の拠点がやられなければよい」わけではないということ。何が幸運なのかは一概にはいえない。
自治体であれば、住民を「面」で守る。守備範囲がポリゴン空間で構成されているから、我が町我が村が災害に見舞われないことが重要な関心事だ。しかし企業活動は「点」と「線」。各地に拠点があり、それを結ぶ交通網・物流網があってビジネスが成立している。影響を受ける範囲や要因ははるかに広い。
その意味で、昨年の熱海の土石流で東海道本線や東海道新幹線に被害が出なかったのはBCMのうえで幸運だった。もし寸断されていたら、災害の様相と影響、そして災害の印象も、まったく違ったものになっていただろう。
2022年1月号 レジリエンスとオールハザードBCPの他の記事
- 強さを増す脅威に企業はどう立ち向かうか
- レジリエンスとオールハザードBCP
おすすめ記事
-

自社の危機管理の進捗管理表を公開
食品スーパーの西友では、危機管理の進捗を独自に制作したテンプレートで管理している。人事総務本部 リスク・コンプライアンス部リスクマネジメントダイレクターの村上邦彦氏らが中心となってつくったもので、現状の危機管理上の課題に対して、いつまでに誰が何をするのか、どこまで進んだのかが一目で確認できる。
2025/04/24
-

-

常識をくつがえす山火事世界各地で増える森林火災
2025年、日本各地で発生した大規模な山火事は、これまでの常識をくつがえした。山火事に詳しい日本大学の串田圭司教授は「かつてないほどの面積が燃え、被害が拡大した」と語る。なぜ、山火事は広がったのだろうか。
2025/04/23
-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2025/04/22
-

帰宅困難者へ寄り添い安心を提供する
BCPを「非常時だけの取り組み」ととらえると、対策もコストも必要最小限になりがち。しかし「企業価値向上の取り組み」ととらえると、可能性は大きく広がります。西武鉄道は2025年度、災害直後に帰宅困難者・滞留者に駅のスペースを開放。立ち寄りサービスや一時待機場所を提供する「駅まちレジリエンス」プロジェクトを本格化します。
2025/04/21
-

-

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視
4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。
2025/04/15
-

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入
日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。
2025/04/15
-

-

生コン・アスファルト工場の早期再稼働を支援
能登半島地震では、初動や支援における道路の重要性が再認識されました。寸断箇所の啓開にあたる建設業者の尽力はもちろんですが、その後の応急復旧には補修資材が欠かせません。大手プラントメーカーの日工は2025年度、取引先の生コン・アスファルト工場が資材供給を継続するための支援強化に乗り出します。
2025/04/14






















![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)






※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方