2018/12/27
アウトドア防災ガイド あんどうりすの『防災・減災りす便り』
●三重県四日市市

まずは三重県四日市市。質問してくださった議員さんはこちら。
平野貴之さんです。

http://www.yokkaichi-jimin.jp/bin/cms/see_more.cgi?d=3&c=35
https://www.facebook.com/hirano.takayuki.yokkaichi/
質問はこちら。
しかし一方で、アパートなどの賃貸物件においては、ネジ止めなどが認められていない。もし穴をあけた場合には原状回復が義務付けられているケースがほとんどです。実は私も今、賃貸のアパートに住んでいるのですが、やはりネジ止めまでは認められていないので、突っ張り棒で済ませているのが現状です。
しかし、やはり最も効果的なのはL字金具などをネジ止めすることで、突っ張り棒では心許ないと、多くの専門家は指摘しています。
そんな中、全国の市営住宅では、家具の固定はエアコンなどと同様に、生活に必要なものであることから、原状回復義務を免除する。つまり、ネジで穴をあけても、もとに戻さなくていいですよ、と。そんな所が現れ始めました。東京都の昭島市や港区では、申請書を提出した場合にネジ止めが認められるそうです。
では、四日市の市営住宅はどうなのでしょうか。現状を教えてください。
この質問に対して、四日市は、賃借人が退去するとき、家具の転倒防止を実施していたとしても原状回復を特に求めていなかったと答えてくれました。そこで、平野さんが続けて、以下の質問をされました。
市営住宅の入居者に渡される「しおり」には、地震の時は家具が倒れることの危険について記載していますが、転倒防止やネジ止めのことは書かれていません。一般的に賃貸住宅ではネジ止め不可ですから、先入観としてネジ止めを避けて突っ張り棒で済ませてしまう。そんな方もいるかもしれません。
したがって、もう一歩進んで、家具固定のためのネジ止めを積極的に入居者の皆さんに促してはいかがでしょうか?
平野さんがおっしゃるようにせっかく実施されていても、入居者が知らなければ、多くの人は壁にキズをつけたら退去の時に請求されると思って、家具の固定を躊躇しますよね。で、四日市市の答弁の要約はというとこちらです。
嬉しいです!
四日市市の市営住宅でも「すまいのしおり」に明記してくださることになりました!この入居のしおりに記載するというのは、港区から始まった方法です。条例も、ガイドラインも変更せずに、すぐに実現できる方法として人気です。このように「しおり」に明記してくれるからこそ、賃借人は安心して家具を固定できますよね。
さらに平野さんはこう質問されました。
たしかに「すまいのしおり」は市営住宅の入居者向けの案内なので、それだけでは四日市市の取組やその意図が他の市民に伝わらないですよね。この原状回復義務免除を実施する意義は、市が原状回復義務を免除してまで家具の転倒防止は重要だと思っているということを多くの人に理解してもらい、住民の家具の固定を促すことにあるのです。周知してこそ、この意義は生かされます。
そして、災害大国のデフォルトとして、賃貸物件でも当たり前のように気兼ねなく家具固定できる街であれば、賃貸物件に住んでいる割合の高い、赤ちゃんがいるご家庭や、学生であっても、安心して住める街ということになります。では、四日市市の答弁はどのようなものだったのでしょうか?ここは、市長さん自ら、素敵な答弁をしてくださいました。以下、お伝えします。
一般的な賃貸住宅では原状回復義務が課せられるケースが多いと認識しておりますけれども、そういった方々についても家主さんに相談して頂くとか、金具を使わない手法を検討して頂くなど積極的に転倒防止策を講じて頂きたいと認識しております。
今後も四日市市民の誰ひとりとして家具の転倒によって尊い命が奪われる事態を起こさせないように強い思いをもって周知啓発に取り組んでいきたいと思います。
市営住宅だけでなく、民間物件についても言及してくださっているのですね!ちゃんと未来を語ってくださる市長さんは素敵ですね。災害大国として、そこに暮らす人の命が家具の転倒で奪われない未来は、実現可能な未来のはずです。
答弁をしてくださった四日市市の市長、森智広さんのHPはこちらです。
http://www.mori-tomohiro.net
https://www.facebook.com/tomohiro.mori2
●香川県観音寺市

次に議会で質問してくださったのは、香川県観音寺市の市議会議員、合田隆胤(ごうだ・たかつぐ)さんです。

質問はこちらになります。
近年の地震による「負傷者」のうち、30〜50%の原因は家具類の転倒・落下であると言われています。本市の「観音寺市防災マップ」でも、地震における家の中の安全対策として、つっぱり棒や金具を利用して家具を固定させることを推奨しています。
2017年4月に港区では、すべての家具で、港区の公営物件などの借主に原状回復義務を免除しました。その際、ガイドラインの変更はせずに「入居のしおり」という入居の際の案内の変更だけで実施しました。どんな変更かというと、家具の転倒防止をすることをあらかじめ届けたら、原状回復義務を免除しますという「一文」を、入居のしおりに加えただけです!
そこで本市でも、市営住宅において防災のための家具固定金具について原状回復義務の「免除」をぜひ実施して頂きたいと考えますが、行政の意見を伺います!
これに対し、観音寺市の答えはこちら。
なお、議員ご指摘の家具の転倒防止対策は、地震発生時、特に今後30年以内に70~80%の確率で発生することが予想されている「南海トラフ地震」の際に、防災面で非常に有効で、本市でも設置を推進しているところであります。今後は、その推進のためにも次回配布の「市営住宅のしおり」から、家具の転倒防止対策については、原状回復義務の対象外とする旨を追記いたします。
次回の配布の「市営住宅のしおり」から、家具の転倒防止対策は、原状回復義務の対象外と追記してくださるそうです。来年度ではなく「次回から」というのがいいですね。災害は待ってくれないので、素早い動きが心強いです。
また、「南海トラフ地震の際に、防災面で非常に有効」な家具の原状回復義務免除と答えていてくれるところも、うんうんとうなずきながら読みました。
合田さんも続いて、このような質問をされました。
今回の原状回復義務、免除のことは四国初・香川初と聞いていますので、ありがとうございます!「転倒防止対策」につて市民の方にしっかりとわかるようにお願いします!
本市の防災計画においても、家具の固定をはじめとする「自助」による市民の防災力向上の取り組みは非常に重要です!「市長 」自らPRして頂ければ、観音寺市が香川県の先駆けともなりますが如何でしょうか?
さて、観音寺市でもここで市長の答弁がありました。
観音寺市の市長さんはこの方、白川晴司市長です。
https://www.city.kanonji.kagawa.jp/site/shicho/
答弁はこちらです。
こちらも、「家具の転倒防止対策をして頂ければ有事の際に大切な命が助かる事例が沢山ありますので」という部分でぶんぶん頷いて、市長さん自ら「今後とも市民に対して防災意識の向上に向けて頑張って参りたいと思います」と宣言して頂けて、とってもありがたい!と思いました。
合田さんも同じように思われたらしく、以下のまとめの答弁をされていました。
「観音寺市は誰一人、家具の倒壊によって命を落とさせない!」という意気込みで今後とも宜しくお願いいたします!白川市長 自らPRして頂ければ、香川県の先駆けともなります!
本市の防災計画においても、家具の固定をはじめとする「自助」による市民の防災力の向上の取り組みは非常に重要です!「観音寺市は誰一人、家具の倒壊によって命を落とさせない!」と言う意気込みで、啓発を宜しくお願いします!
四国初、香川初の取り組みを実施してくださったことが嬉しいです。
四日市市とあわせて読んで頂けるとわかるように、今やこの原状回復義務の免除は、議員さんが質問すればすぐ実施してくれる、そういう案件になりつつあります!
●埼玉県日高市

つづいて、埼玉県日高市です。
質問されたのは市議会議員の田中まどかさんです。

https://www.facebook.com/madoka.tanaka.140
田中さんの質問はこちらです。
港区では賃貸住宅の転倒防止器具の取り付けを普及させるため、区営住宅など区が管理する賃貸住宅で家具転倒防止のためのビス穴などはエアコン設置用の穴と同様に現状復帰義務免除としています。
日高市の市営住宅で現状復帰免除することについて見解をお聞きします。
これに対する日高市の答えはこちらです。
日高市も、四日市市と同じように退去の際に原状回復義務の請求は行っていないパターンだったのですね。これは、質問して初めてわかるので、もしかすると皆様がお住まいの地域も同じかもしれません。そのような地域では、もう原状回復義務の免除を実施したのも同然です。あとは、入居のしおりなどに家具の転倒防止の意義を書いて頂くだけでいいのです。きっとそんな地域は四日市と日高市だけでなく、知られていないだけで他にもあるのかもしれませんね!
みなさんも地域の議員さんと一緒に地元で原状回復義務についてどのように取り扱っているから調べて頂ければと思います!もちろん議員さんに知り合いがいなければ、行政と一緒に変えて頂くこともできます。来年はもっとたくさんの自治体で実施したよーという声をお聞きできることを楽しみにしております。
ということで、今年1年、ありがとうございました。来年も引き続きみなさまと防災・減災について考えていければ嬉しいです。
(了)
アウトドア防災ガイド あんどうりすの『防災・減災りす便り』の他の記事
おすすめ記事
-

自社の危機管理の進捗管理表を公開
食品スーパーの西友では、危機管理の進捗を独自に制作したテンプレートで管理している。人事総務本部 リスク・コンプライアンス部リスクマネジメントダイレクターの村上邦彦氏らが中心となってつくったもので、現状の危機管理上の課題に対して、いつまでに誰が何をするのか、どこまで進んだのかが一目で確認できる。
2025/04/24
-

-

常識をくつがえす山火事世界各地で増える森林火災
2025年、日本各地で発生した大規模な山火事は、これまでの常識をくつがえした。山火事に詳しい日本大学の串田圭司教授は「かつてないほどの面積が燃え、被害が拡大した」と語る。なぜ、山火事は広がったのだろうか。
2025/04/23
-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2025/04/22
-

帰宅困難者へ寄り添い安心を提供する
BCPを「非常時だけの取り組み」ととらえると、対策もコストも必要最小限になりがち。しかし「企業価値向上の取り組み」ととらえると、可能性は大きく広がります。西武鉄道は2025年度、災害直後に帰宅困難者・滞留者に駅のスペースを開放。立ち寄りサービスや一時待機場所を提供する「駅まちレジリエンス」プロジェクトを本格化します。
2025/04/21
-

-

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視
4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。
2025/04/15
-

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入
日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。
2025/04/15
-

-

生コン・アスファルト工場の早期再稼働を支援
能登半島地震では、初動や支援における道路の重要性が再認識されました。寸断箇所の啓開にあたる建設業者の尽力はもちろんですが、その後の応急復旧には補修資材が欠かせません。大手プラントメーカーの日工は2025年度、取引先の生コン・アスファルト工場が資材供給を継続するための支援強化に乗り出します。
2025/04/14
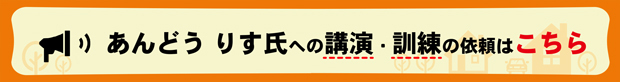



















![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)






※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方