2024/10/10
インタビュー
コンプライアンスの危機
成蹊大学文学部伊藤昌亮教授と考える

成蹊大学文学部教授
伊藤昌亮氏 いとう・まさあき
1985年東京外国語大学外国語学部卒業。2010年東京大学大学院学際情報学府博士課程修了。日本アイ・ビー・エム、ソフトバンク勤務を経て、09年愛知淑徳大学現代社会学部准教授、10年同大学メディアプロデュース学部准教授、15年から成蹊大学文学部教授。専門はメディア研究。著書に『炎上社会を考える―自粛警察からキャンセルカルチャーまで』(中央公論新社)など。最近では論壇誌『世界』に掲載した「ひろゆき論」が話題に。
企業の不正・不祥事が発覚するたび「コンプライアンスが機能していない」といわれる。が、必ずしもコンプライアンス自体が弱まっているわけではない。「うっとうしい」「窮屈だ」と、むしろその圧力は強まっているようだ。このギャップはなぜ生じるのか。ネットコミュニケーションなどから現代社会の問題を研究する成蹊大学文学部の伊藤昌亮教授とともに考えた。
インタビュー聞き手:新建新聞社記者 竹内美樹
コンプライアンスが目指したそもそもの方向
――企業による不正・不祥事が発覚するたび「コンプライアンスが機能していない」といわれますが、そもそもコンプライアンスとはどのようなもので、いつから用いられているのでしょうか。
コンプライアンスは法律や条例を順守するだけでなく、例えば就業規則、企業倫理、社会規範、そういったもろもろのルールを守る、そしてそのためのチェック体制を構築する、という意味を含んでいます。元来はアメリカの概念でしたが、2000年代前半、経済・政治情勢に固有の事情を抱えていた日本へ導入されました。
――日本が抱えていた固有の事情とは。
日本では90年代前半、バブル経済が崩壊し、55年政治体制が終焉。その後の低迷・混迷のなか、社会全体をつくり直そうとする動きが活発化します。その動きは新自由主義、すなわち市場競争の活力を最大化するため行政の介入を最小化するという考え方に収れんし、それが価値観変化の起爆剤となって、一連の改革につながっていきました。
橋本龍太郎内閣のもとで始まった改革は、森喜朗内閣を経て、小泉純一郎内閣で本格化。いわゆる「聖域なき構造改革」へと結実していきます。この一連の改革の指針として打ち出されたのが「事前規制から事後監視へ」という考え方でした。2000年12月、森内閣時代に閣議決定された「行政改革大綱」に次の記述があります。
「国民の主体性と自己責任を尊重する観点から、民間能力の活用、事後監視型社会への移行等を図る」
大綱にはこれ以外にも「事後監視」「事後チェック」という言葉が何度も出てきます。事前規制型から事後監視型へ、社会構造の大きな転換をともなう改革の狼煙(のろし)が、このときはっきり上がっているわけです。
――社会が事前規制型から事後監視型へ移行するタイミングで、コンプライアンスの概念が導入された、と。どのような意味があったのでしょうか。
それまでの日本は、行政が人や組織の活動にあらかじめ規制をかけることで、不正・不祥事の発生を未然に防ぐのが基本でした。ただ、そのやり方だと活動が規制に阻まれ、自由な競争ができにくい。かつ、さまざまな規制を細かくかけるがゆえに、その運用コストが膨らむ。そこで、規制緩和が求められたわけです。
とはいえ、規制を緩和するだけでは、これまで防がれていた問題が顕在化しかねない。規制が弱まったのをいいことに、やりたい放題となってはいけません。そこで打ち出されたのが、事前規制を緩和する代わりに事後監視を強化する方針でした。
事前規制を弱める分、活動は自由になる。一方で、問題が起きないかを常にチェックし、何か起きたら適切に対処する、と。ただ、チェックはあくまで事後ですから、どんな問題が起きるか事前にはわからない。コスト予測が立てられないため、行政が全面的に監視の役割を引き受けるのは困難です。
そのため、監視機能のかなりの部分は民間に任せざるを得ない。結果、自分たちの行動は自分たちでチェックし、自分たちで律する。自分たちで行動基準をつくり、自分たちで守る。それが事後監視社会の考え方で、この実現に向けて導入されたのがコンプライアンスでした。
つまり、事後監視型社会への移行を進めていくにあたり、自己責任によって自己を律していくための方法論です。事前規制にある意味で守られてきた日本人が、それを取り払い、自由競争へと乗り出していくために必要な「自律的な主体」をつくり出していく手段だったわけです。

日本的相互監視システムと結びついたコンプライアンス
――すごくポジティブな意味合いを含んでいますね。それがいま、どうもうまく機能していない。にもかかわらず「うっとうしい」「窮屈だ」といわれるように、コンプライアンスの圧力は強くなっている。自由のために導入されたのに、それが果たされず、逆に不自由になっているように感じますが。
確かにそうした意見が主流になっていますね。ただ、そこは少し冷静に見ないといけない。
昭和の時代のほうが自由だったといいますが、社会の「地」の部分では、いまのほうが自由な面が多々あります。例えば、自由な働き方や自分らしい生き方。女性の登用・活躍にしても、ライフステージに応じた休暇取得にしても、個人の裁量による勤務形態にしても、以前はそのような制度も考え方もなかった。
事前規制社会は物事の大筋があらかじめ決められ、それが人々の考え方にも影響を与えていました。「サラリーマンはこうあるべき」「男はこうあるべき」「女はこうあるべき」といった既成概念が浸透し、逸脱しようとする者には厳しい圧力が加えられた。現在はそのような締めつけが減少し、既成の枠にはまらなくても多様な働き方、生き方ができるようになっています。

しかし一方で、事後監視の圧力は強くなった。特に、人に迷惑をかけていないか、誰かに不快な思いをさせていないかが常に厳しくチェックされ、少しでも不届きが見つかると即座に告発されます。そこに昭和の窮屈さとは違った現在の窮屈さがあるわけですが、ただしこの事後監視も、実はいまに始まったものではない。昭和の時代も、何なら近代以前もありました。例えば「隣組」「五人組」の制度です。
結局、日本の統治システムは中央集権といっても、権力が隅々まで管理するのではなく、庶民がお互いを監視し合う仕組みをうまく取り入れてきた歴史があります。本来は自由のための自律を実現する手立てとなるはずのコンプライアンスですが、それが日本独特の封建的な相互監視のメンタリティーと結びついてしまったために、決めつけや締めつけが弱まって自由になった以上に監視の圧力が強まり、結果、自由に振舞えなくなってしまったのかもしれません。
――コロナ禍での「自粛警察」などはまさにそうですよね。
相互監視のメンタリティーは江戸時代の「五人組」から受け継がれているわけですが、昭和には「隣組」となり、その行動形態は「自粛」というかたちであらわれてきます。「自粛」は自ら慎むという意味では確かにコンプライアンス的ですが、実はすごく複雑で難しい。日本の自粛は、要は自己判断の名を借りた強制システムです。
誰にいわれるでもなく自ら行動を慎むことが自粛だとすると、そもそも「自粛要請」「自粛警察」などという言葉はおかしいですよね。自ら慎むことを要請する、自ら慎まない者を取り締まるなどというのは、矛盾以外の何物でもない。つまり、政府がやれとはけっしていわないのだけれど、国民が忖度して自己判断でやるよう仕向けるわけです。
生き残りのために政府に忖度し全員で歩調を合わせるのは「自己判断」「自己責任」ではなく「他者判断」「連帯責任」です。誰も責任を取らない都合のよいシステムといってもいい。コンプライアンスがそうしたシステムと結びついた結果、相互監視と強制の部分がすごく強まってしまった可能性は考えられます。
インタビューの他の記事
おすすめ記事
-
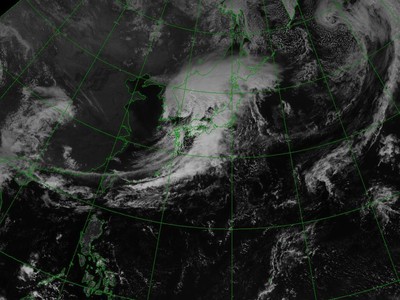
-

備蓄燃料のシェアリングサービスを本格化
飲料水や食料は備蓄が進み、災害時に比較的早く支援の手が入るようになりました。しかし電気はどうでしょうか。特に中堅・中小企業はコストや場所の制約から、非常用電源・燃料の備蓄が難しい状況にあります。防災・BCPトータル支援のレジリエンスラボは2025年度、非常用発電機の燃料を企業間で補い合う備蓄シェアリングサービスを本格化します。
2025/04/27
-

自社の危機管理の進捗管理表を公開
食品スーパーの西友では、危機管理の進捗を独自に制作したテンプレートで管理している。人事総務本部 リスク・コンプライアンス部リスクマネジメントダイレクターの村上邦彦氏らが中心となってつくったもので、現状の危機管理上の課題に対して、いつまでに誰が何をするのか、どこまで進んだのかが一目で確認できる。
2025/04/24
-

-

常識をくつがえす山火事世界各地で増える森林火災
2025年、日本各地で発生した大規模な山火事は、これまでの常識をくつがえした。山火事に詳しい日本大学の串田圭司教授は「かつてないほどの面積が燃え、被害が拡大した」と語る。なぜ、山火事は広がったのだろうか。
2025/04/23
-

リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2025/04/22
-

帰宅困難者へ寄り添い安心を提供する
BCPを「非常時だけの取り組み」ととらえると、対策もコストも必要最小限になりがち。しかし「企業価値向上の取り組み」ととらえると、可能性は大きく広がります。西武鉄道は2025年度、災害直後に帰宅困難者・滞留者に駅のスペースを開放。立ち寄りサービスや一時待機場所を提供する「駅まちレジリエンス」プロジェクトを本格化します。
2025/04/21
-

-

大阪・関西万博 多難なスタート会場外のリスクにも注視
4月13日、大阪・関西万博が開幕した。約14万1000人が訪れた初日は、通信障害により入場チケットであるQRコード表示に手間取り、入場のために長蛇の列が続いた。インドなど5カ国のパビリオンは工事の遅れで未完成のまま。雨にも見舞われる、多難なスタートとなった。東京オリンピックに続くこの大規模イベントは、開催期間が半年間にもおよぶ。大阪・関西万博のリスクについて、テロ対策や危機管理が専門の板橋功氏に聞いた。
2025/04/15
-

BCMSで社会的供給責任を果たせる体制づくり能登半島地震を機に見直し図り新規訓練を導入
日本精工(東京都品川区、市井明俊代表執行役社長・CEO)は、2024年元日に発生した能登半島地震で、直接的な被害を受けたわけではない。しかし、増加した製品ニーズに応え、社会的供給責任を果たした。また、被害がなくとも明らかになった課題を直視し、対策を進めている。
2025/04/15




















![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)






※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方