自然災害
-

避難からBCPまで一気の訓練をしてみては?
BCPの計画と現実とのギャップを、多くの企業に共通の「あるある」として紹介、食い違いの原因と対処を考える本連載。現在は第2章「BCPの実効性、事業継続マネジメント、発生コスト」のなかに潜む「あるある」を論じています。今回は、多くの企業が抱える訓練の予定調和と形式化の問題について。どのように解決できるかを考えます。
2024/09/17
-

Q&Aで解説 実務課題の超ヒント
「危機管理のマニュアル類が複雑すぎる」「キャリア採用のリスクマネジメント担当者が現場の声を吸い上げていない」など、本紙はこの半年間で聞いた読者の声を「Q(Question)」として集約、危機管理に詳しいコンサルタントに提示して「A(Answer)」をもらいました。危機管理の難問・疑問、その答えは――。防災・BCP編に続き、リスク管理・危機管理編をお届けします。
2024/09/16
-
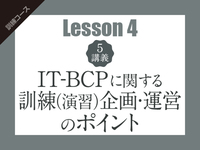
【Lesson4(5講義)】IT-BCPに関する訓練(演習)企画・運営のポイント
IT-BCPに関する訓練(演習)企画・運営のポイントを解説します。解説者は、合同会社グビー代表の永井勝氏です。
2024/09/13
-

不確実性の類型とリスク管理
将来に対する意思決定においては不確実性が存在する。このような状況においてわれわれはいかにして合理的な意思決定をすべきなのか。この問題は「不確実性下の意思決定論」として長らく学問の対象となってきた。そして、これはまさにリスク管理の実践そのものに関わる課題と言える。
2024/09/11
-

危機管理広報の体験学習―メディアトレーニング
本研修では記者会見の司会はじめ会社幹部(社長、担当役員、現場責任者等)の役になり、危機的状況についての説明や質問への回答、謝罪のポイントについて学んでいただきます。
2024/09/10
-

第11回: 新たな体制:地域とのより良い関係のために
紅葉山FCが利用している市営グラウンドが、近隣住民からの苦情によって使えなくなってしまったため、他の利用団体や関係者の協力を得ながらグラウンドの利用再開を目指しています。これまでの取り組みの中で問題の所在や近隣住民の意向がある程度分かってきましたので、監督の高宮と渉外担当の近藤、野球チーム代表の松嶋、県サッカー協会の藤崎と市役所OBの茅森、市の担当者の日吉が市役所の会議室に集まりました。
2024/09/08
-

非財務情報の開示動向 その2~最低限知っておくべき国際基準と開示項目~
9月のESGリスク勉強会の発表者は、国際的なESGの格付け会社CRIF(本社イタリア)日本法人Sales Manager/Business Development Specialistの村上裕貴氏です。
2024/09/06
-

防災月間いま何を見直す?企業防災をめぐる昨今のリスクから
リスク対策.com の連載陣が、自身の記事や最近の事象を解説する公開オンライントークです。最新のリスクトレンドや注視するポイントをお伝えします。聴講者の皆様がウェビナーのQ&A 機能を使って質問することも可能です。
2024/09/05
-
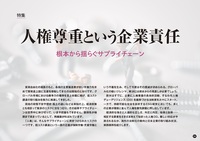
人権尊重という企業責任
安い労働力を求めて開発途上国に次々と生産を移転してきた結果、世界中に伸びて全体の把握ができなくなったサプライチェーン。いまそこに「人権」というリスクが突き付けられています。低コスト調達という一面の正義が生み出した、強制労働・児童労働という不義。ジレンマを抱えつつも、企業による人権尊重の取り組みは始まりました。先行する海外の動きと日本企業の状況、実践活動のポイントを紹介します。
2024/09/05
-

自然災害に備える企業の人事労務管理対策
今年は、1月の能登半島地震に続き、8月には南海トラフ地震臨時情報の発表や大型台風が上陸するなど、災害が相次いでいます。近年、日本では大規模な自然災害のリスクが高まっています。このような予期せぬ事態に備えることは、企業の事業継続を確保するだけでなく、従業員の安全と健康を守る上でも重要です。
2024/09/04
-

災害時の通信インフラ維持に向けたマイクロ風車実証
風向風速の変化に強い風力発電機の開発を行うチャレナジーはこのほど、アストモスエネルギーのLPガス受け入れ二次基地である金沢ターミナル(所在:石川県金沢市大野町4-ソ6)に寒冷地用の次世代マイクロ風力発電機「Type A」を設置し、北陸臨海部域での実証を開始した。スカパーJSATの衛星通信ExBirdの供与を受け、衛星通信の稼働実証などを行い、災害時の通信ネットワークの継続的な運用を目指す。
2024/09/04
-

温室効果ガス削減の停滞による、2030年最悪シナリオを描く
今回から始まる第二部では、私たちの社会や経済が既存の枠組みから抜け出すことができず、これまで通りのペースで大気中に温室効果ガスの放出を続けた2030年を描きます。どのようなリスクが顕在化し、ビジネスに降りかかるのか。さまざまな影響を見ていきます。
2024/09/04
-

大規模災害時に従業員が安心して滞在できる備え
主力の「スーパードライ」に代表されるアサヒビールをはじめ、アサヒ飲料、アサヒグループ食品などの日本事業を統括するアサヒグループジャパン。同社は大規模災害発生時の帰宅抑制に取り組む。対象となるのは、本社ビルに勤務する傘下の従業員約3000人。本社ビルに特化した対策を進め、従業員の安心感を高めることで、滞在の理解を得ようとしている。
2024/08/31
-

「改正入管法と育成就労制度」
2024年6月14日に「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、21日に公布されました。技能実習制度を解消し、人手不足分野における人材育成と人材確保を目的とする育成就労制度を新たに創設し、特定技能制度と連続性をもたせることで外国人材が日本国内でキャリアアップできる制度を構築し、長期にわたり日本の産業を支える人材の確保を目指すことになりました。
2024/08/30
-

第252回: マネジメントシステム規格の普及は今なお世界的に進んでいる
さまざまな国際規格を発行している国際標準化機構(International Organization for Standardization/ISO)は、各種マネジメントシステム規格による認証取得件数を集計して毎年発表している。今回はその最新版である「ISO Survey 2022」をもとに、世界各国におけるマネジメントシステム規格の普及状況を見ていきたいと思う。
2024/08/28
-

自立した蓄発電消費を可能にするエネルギーユニット
マイクロオフグリッド・グリーンエネルギ―事業などを展開するPoC TECH(東京都目黒区)と、IT関連機器販売などを手がけるコメイチ(青森県佐井村)は、太陽光発電を過酷な設置環境に適応させ、自立した自己蓄発電消費を可能にする太陽光利活用オフグリッドエネルギーユニット「SAI-KORO(サイコロ)」を提供する。暮らしの中で自然のエネルギーを有効活用しながらCO2削減を実現し、災害時にはフォークリフトで避難場所や電力喪失エリアまで運搬できるもの。
2024/08/28
-

個人の状況に即した情報提供で避難行動を支援
NTTアドバンステクノロジは、全国の自治体を対象に、個人の状況に即したパーソナライズ情報を提供することで逃げ遅れゼロをめざす避難行動支援サービス「ニゲドキ」を展開する。避難促進にかかる自治体職員の負担を軽減し、他の災害関連業務への対応を可能にすることで、災害に強い安心・安全な地域社会の構築を支援するもの。現在、自治体職員を対象に、手持ちのスマートフォンで各機能を試せるトライアル提供(無料)を行っている。
2024/08/27
-

一斉帰宅抑制後の帰宅許可をいつ誰がどう出す?
南海トラフ地震臨時情報による巨大地震注意の呼びかけが終了しました。とはいえ、リスクが去ったわけではありません。首都直下地震も含め、次の巨大地震への備えを根本から見直す必要があると考えます。7月には、内閣府の帰宅困難者対策ガイドラインも改定されたところ。企業BCPの視点から、いま一度、企業の帰宅困難者対策を考えます。
2024/08/26
-

企業の自衛消防隊が最低限知っておくべき消防知識(上級編)~実際に活動できる自衛消防隊にしよう・早く知って早く消して早く逃がそう~
8月29日(木)15時から、自衛消防隊向けの特別セミナー(上級編)を開催します。実際に活動できる自衛消防隊になっているか見直す内容となっています。講師は、元西宮市消防局北消防署長の長畑武司氏(一般社団法人 兵庫県消防設備保守協会 事務局次長兼点検推進指導員)です。
2024/08/22
-

気候変動の未来に向けた3つの問い
ここまで、さまざまな観点から気候変動によって変わりつつある、あるいは停滞したままの経済社会の様相を見てきました。最後に、この現状を将来に照らし、3つの疑問に置き換えてみます。それは「私たちの意識は変われるのか?」「エネルギーはどうなるのか?」「地球の気候はどう変化するのか?」。これらの解説をもって第一部のまとめとします。
2024/08/22
-

第251回: 損害保険市場の世界的なトレンドをつかむ
今回紹介させていただく報告書は保険市場の状況を四半期ごとにまとめたもの。保険商品(product)ごとのトレンドが地域ごとにわかりやすくまとめられている。
2024/08/21
-

「南海トラフ地震臨時情報」が発令されたなら
2024年8月8日、日向灘を震源とするマグニチュード7.1の地震が発生し、初めて南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)が発表されました。南海トラフ地震臨時情報に関する解説と対策のポイントについて説明します。
2024/08/20
-

臨時情報を受けて今すぐできること
本年1月に発生した能登半島地震に続いて、自然は私たちに「会社が平常運転の状況で災害が起きるとは限らないんだよ。」と改めて教えてくれている気がします。社員が少ない状況での災害に対する備えや、事業継続対策の必要性がますます増していますね。 本稿では、臨時情報の発表を受けて今すぐにできることを考えてみたいと思います。
2024/08/19
-

日高豪雨――8月の気象災害―
2003(平成15)年8月の台風第10号は、この年2個目の上陸台風である。沖縄県から北海道まで、すべての都道府県に影響を与えた。中でも、北海道の日高山脈の西側に位置する日高地方の豪雨被害が顕著であった。北海道では台風接近前から、防災関係の各機関が特別態勢を敷いて警戒にあたったが、結果的に様々な課題が残った。この災害を契機に、北海道では、北海道開発局、札幌管区気象台、北海道庁の三者による防災情報の共有に向けた動きが起こり、防災関係機関が連携して災害に備える体制が構築・強化される端緒となった。こうして、北海道の防災体制に一石を投じたこの豪雨は、道内の防災関係者から「日高豪雨」と呼ばれるようになった。
2024/08/18
-

自然災害と企業の責任~自然災害から従業員を守る防災対策~
日本は「災害大国」といわれ、世界的に見ても地震、台風、豪雨などの自然災害の多い国です。大規模地震発生の可能性は、南海トラフ地震が70%から80%、首都直下地震は70%とされています。2024年8月8日、宮崎県日向灘を震源とするマグニチュード7.1の地震が発生し、気象庁は、「南海トラフ地震臨時情報」の運用が開始されて以降はじめて、「巨大地震注意」を発表しました。
2024/08/17
















![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)



