第2回 地球温暖化に向けた世界の挑戦
地球危機の状況と方向性

島崎規子
大学関係の主たる内容は、駒澤大学経済学部、城西大学短期大学部、城西国際大学経営情報学部大学院教授などを歴任し、同大学定年退職。城西国際大学では経営情報学部経営情報学科長、留学生別科長などを務めた。大学以外の主たる内容は、埼玉県都市開発計画地方審議会委員、財務省独立行政法人評価委員会委員、重松製作所監査役などを務めた。
2024/01/10
環境リスクマネジメントに求められる知識

島崎規子
大学関係の主たる内容は、駒澤大学経済学部、城西大学短期大学部、城西国際大学経営情報学部大学院教授などを歴任し、同大学定年退職。城西国際大学では経営情報学部経営情報学科長、留学生別科長などを務めた。大学以外の主たる内容は、埼玉県都市開発計画地方審議会委員、財務省独立行政法人評価委員会委員、重松製作所監査役などを務めた。

2023年11月の世界気候機関(WMO : World Meteorological Organization)の報告書では、2023年10月までの地球表面の平均気温は、産業革命以前の1850年から1900年の基準に比べ1.40度(誤差±0.12度)上昇し、2023年11月と12月の気温を考慮しても、これまで歴代最高だった2016年のプラス1.29度を上回って、過去最高になると予想されています。また、欧州連合(EU)の気象情報機関「コペルニクス気候変動サービス」が先日、2023年の世界平均気温が14.98度と、記録が残る1850年以降で最高だったと発表しました。このような深刻な地球危機に対して、地球温暖化対策が世界でどのように進捗しているかの状況と方向性を解説いたします。
地球温暖化の進行が加速して、世界各地で干ばつや洪水、急速に溶けている南極の氷、減り続ける熱帯雨林、猛暑や豪雨、頻発する山火事、竜巻、突然のひょうやあられをはじめとする異常気象など深刻な被害の現状と危機が、世界気候機関(WMO)より発表されています。
その主たる原因の1つが、現在発生しているエルニーニョ現象です。これは、ピークを過ぎた後に地球の気温上昇に影響を与えることが多いため、今後、気温を加速させる可能性があるからです。最近は「スーパーエルニーニョ」とも呼ばれています。
2つめの原因は、二酸化炭素CO2の濃度が、産業革命以前に比べて約50%上昇して、大気中に熱を閉じ込めています。濃度の濃いCO2が長時間滞留する現象は、今後も気温が上昇し続けることを意味しているからです。
また、WMOは、地球の平均気温だけでなく、海の温度と平均海面水位の上昇が加速して、記録的な状況になっていることについても警告を鳴らしています。
海面上昇は、海の温度の上昇と氷河・氷床の融解により、1993年以降の衛星観測の記録としては過去最高を示しています。最近10年間の上昇率は、観測が始まった1993年からの10年間と比較しますと2倍以上で、海面上昇が加速していることがわかります。
日本の場合、2023年12月の気象庁の発表によりますと、平均気温が、平均より1.34度高くなり、過去最高でありました2020年を大きく上回り、統計開始以降、最高になると予想されています。また、日本近海の平均海面水温も平年に比べて1.07度高くなり、過去最高でありました2021年の0.74度を大きく上回り、年間を通して1908年の統計開始以降、最も高くなる見通しとなっています。
このような影響を受けて、事実、世界では多くの被害が発生しています。例えば、2023年に発生した熱波では、特に南ヨーロッパと北アフリカが、熱波の被害を直撃し、イタリアで48.2度、モロッコで50.4度など記録的な気温が報告されています。また、日本では、40度を超える地域が発生し、真夏日や猛暑日の最多記録の更新が発表されました。このように、世界では、夏の気温が歴代記録を大幅に超える状況となり、死活問題となっています。
さらに、大規模な山火事も多発しています。カナダでは、過去10年間平均の6倍以上の面積が焼失し、深刻な煙汚染を引き起こしています。ハワイの山火事では、多くの人々が犠牲になる悲惨な状況が報告されています。
それ以外では、熱帯低気圧Freddy(フレディ)や「メディケーン」と呼ばれる低気圧(ダニエル)により、ギリシャやリビアなどの地球海沿岸各地では大洪水が発生しています。直近2023年12月には、アメリカ西海岸カリフォルニア州に1時間で80ミリを超える過去最高の豪雨が発生し、また、ドイツでも3メートルの高潮警報が出され、川が氾濫して多大な被害を受け、多くの人たちが犠牲になりました。
このような地球の危機が、さらに拡大しないために、地球温暖化をストップする行動が、世界で実施されています。
環境リスクマネジメントに求められる知識の他の記事
おすすめ記事


リスク対策.com編集長が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2025/05/13

「まさかうちが狙われるとは」経営者の本音に向き合う
「困った人を助け、困った人を生み出さず、世界中のデータトラブルを解決します」。そんな理念のもと、あらゆるデータトラブルに対応するソリューションカンパニー。産業界のデータセキュリティーの現状をどう見ているのか、どうレベルを高めようとしているのかを聞きました。
2025/05/13



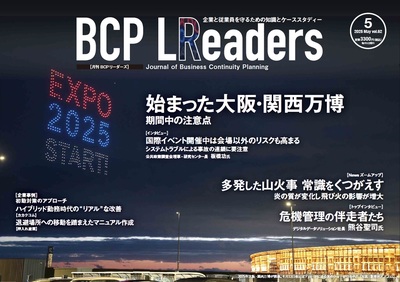
リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ
リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。
2025/05/05
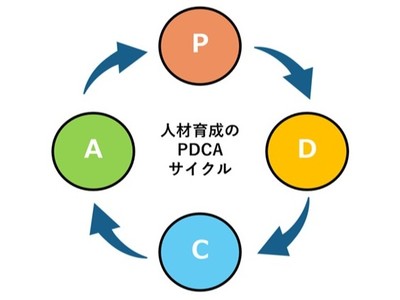
企業理念やビジョンと一致させ、意欲を高める人を成長させる教育「70:20:10の法則」
新入社員研修をはじめ、企業内で実施されている教育や研修は全社員向けや担当者向けなど多岐にわたる。企業内の人材育成の支援や階層別研修などを行う三菱UFJリサーチ&コンサルティングの有馬祥子氏が指摘するのは企業理念やビジョンと一致させる重要性だ。マネジメント能力の獲得や具体的なスキル習得、新たな社会ニーズ変化への適応がメインの社内教育で、その必要性はなかなかイメージできない。なぜ、教育や研修において企業理念やビジョンが重要なのか、有馬氏に聞いた。
2025/05/02


備蓄燃料のシェアリングサービスを本格化
飲料水や食料は備蓄が進み、災害時に比較的早く支援の手が入るようになりました。しかし電気はどうでしょうか。特に中堅・中小企業はコストや場所の制約から、非常用電源・燃料の備蓄が難しい状況にあります。防災・BCPトータル支援のレジリエンスラボは2025年度、非常用発電機の燃料を企業間で補い合う備蓄シェアリングサービスを本格化します。
2025/04/27
※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方