そもそも、防災士の役割ってなんだっぺ?
自助・共助の大切さを学ぶ!

赤プル
茨城県常総市出身。2003年女性ピン芸人としてデビュー。エンタの神様、爆笑レッドカーペットなどの番組で、茨城の自虐ネタで注目を集める。2011年先輩芸人、元 坂道コロコロの松丘慎吾と結婚。2014年「チャイム」という夫婦コンビを組み、浅草漫才協会に所属。茨城大使・常総市ふるさと大使。整理収納アドバイザー。防災士。著書「おめえら、いつまでも調子に乗ってんじゃねーかんな」。
2017/04/28
女芸人赤プル、防災士になる!

赤プル
茨城県常総市出身。2003年女性ピン芸人としてデビュー。エンタの神様、爆笑レッドカーペットなどの番組で、茨城の自虐ネタで注目を集める。2011年先輩芸人、元 坂道コロコロの松丘慎吾と結婚。2014年「チャイム」という夫婦コンビを組み、浅草漫才協会に所属。茨城大使・常総市ふるさと大使。整理収納アドバイザー。防災士。著書「おめえら、いつまでも調子に乗ってんじゃねーかんな」。

茨城出身の赤プルです!
先日驚いた事がありました!
私は現在、主人とのコンビ「チャイム」として、定期的にお笑いライブに出演しています!
ほとんどのお笑いライブには、出演芸人全組がネタを披露した後、全員が出揃い、それぞれが次回のライブであったり、テレビ出演の告知をする、エンディングコーナーがあります!
先日出演したライブのエンディングで、意気揚々と「防災士への道の連載がスタートしたのでみてください!」と告知すると、舞台上の出演者、そして、客席のお客様の頭の上に、「?」が浮かんで見えるのです。
やっぱりみんな、赤プルが防災士になろうとしてるのを、疑問に思うんだなと思っていると、MCの方に「ぼうさいしってどんな漢字を書くんですか?」と聞かれたのです。
どうも赤プルが「ボウサイシ」と発言すると、そのボウの響きが、防災士の防ぐの字ではなく、「暴走族」の暴れるという字の印象になるらしいんです。
※茨城=暴走族というのが、世間の偏った印象なんですね。(赤プルのキャラもあるのでしょうけれど)
これはまずったなぁと思いながら、一生懸命「防災士」について説明するんですが、私自身もよくわかってないんですね。
これは、一言で説明できるようにならないとなぁと教本を開いたんですけど、1ページ目の防災士とは、こんな風に乗ってるんですね。
防災士とは「〝自助〟〝共助〟〝協働〟を原則として、社会の様々な場で防災力を高める活動が期待され、そのための十分な意識と一定の知識・技能を修得したことを、日本防災士機構が認証した人です」と書いてあります。
が、正直よくわからなかったんです!
防災を学ぼうと申込んだは良かったのだけど、そもそも防災士ってなんなの?っていう振り出しに戻ってしまったわけです。本当にまずいですよね。
で、防災士の資格を取得しているリスク対策.comの編集部の方にちょっと聞いてみました!
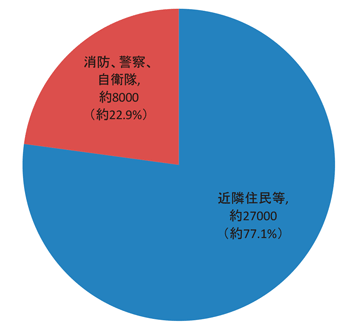
赤:近隣の住民っていうのは、一般の人ってことですか?!
確かに、消防や警察の人だけでは、とても手が足りなさそうです。
リ:さらに防災士教本によると、消防や警察・自衛隊に助けられた8000人のうち約半数の方はお亡くなりになったのに比べ、近隣住民の方に助けられた方で亡くなった方はおよそ2割程度だったそうです。災害発生から24時間以内の素早い救出がいかに大事なことが分かりますね。
赤: 助かった人は、すぐに人を助ける!これが大事なんですね!それって、私が持ってる防災士教本にも書いてあるんですね(汗)
リ:そうなんです。災害の時にはまず「自分が助かること」。そして「身近な人を周りの人が助けること」が重要なのです。これを「自助」、「共助」と言います。もうひとつ、「公助」というものもあります。これは文字通り政府や自治体による支援ですが、先にもお話ししたように限界があります。できるだけ頼らないようにすることが大事ですね。
赤:なるほど!よくわかりました!
自助というのは、まず自分が助かること。共助というのは、周りを助けること。
リ:私が防災士になったときに言われたことは、防災士の役割は「助けられる側から助ける側にまわること」でした。そのためにはまず自分が助かることが必要です。赤プルさんも勉強を通じて、災害に対して正しい知識を持ち、「助けられる側から助ける側」にまわれるようにしたいですね。
赤 : 防災士の役割!これを知ることがとても重要ですね。
まさに私が災害時、何かしたくても何をすればいいかわからなかった!
その答えが、「助けられる側から助ける側にまわること」だと実感が湧きます!
今回は防災士の役割と、「災害に対して正しい知識を身につけなければ、助ける側には回れない」ということが分かりました。
前回もお話ししましたが、私は現在整理収納アドバイザーの資格も取っており(実は調理師免許も持ってます!)、出身地の常総市で水害を経験したことから「防災」と「整理収納」をこれからもっと勉強したいと思っています。
防災士の勉強、引き続き頑張ります!

(了)
女芸人赤プル、防災士になる!の他の記事
おすすめ記事

能登半島地震からまもなく2年
能登半島地震からまもなく2年。災害対応の検証も終盤に入っています。浮上した課題を反映し、災害関連法も変わりました。来年はこれらの内容をふまえた防災・BCPの見直しが加速しそうです。発災直後から被災地を調査し、石川県の初動対応を振り返る検証委員会の委員も務めた金沢大学准教授の青木賢人氏に防災・BCP強化の方向を聞きました。
2025/12/25




中澤・木村が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2025/12/23





※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方