2012/11/25
リスクマネジメントの本質
5.品質管理導入の歴史と対比したリスクマネジメント・BCP等導入の問題点
QC(品質管理)の導入と定着の過程は、QCという言葉をリスクマネジメント、ERMや内部統制コーポレート・ガバナンス体制の導入と定着という言葉に置き換えて考えてみるときに我々に数多くの示唆を与えてくれます。
それでは、我が国の企業がコーポレート・ガバナンス体制の構築、内部統制に支えられたリスクマネジメント→ERMを導入するについて、品質管理の導入時と現在とはどのような相違点があるのでしょうか。
①危機意識の欠如
アメリカやイギリスにおいては、数多くの企業の不祥事の反省からコーポレート・ガバナンス体制構築についての議論と実務が積み重ねられ、一方、内部統制によって支えられるリスクマネジント、さらにはERMの実践が求められてきました。我が国においても最近、著名企業において色々な不祥事が続発し、また東京電力福島第一原子力発電所の事故などが発生して、我が国の企業経営の在り方が問われています。
その対策としてのコーポレート・ガバナンス体制の構築やERM、BCPが叫ばれています。しかし我が国の企業経営者のすべてが真に危機意識を持って取り組もうとしているのかは疑問だと思います。
品質管理と違って、全社的な問題であるという我が国の縦割りの企業組織についての技術的な問題も無視できませんが、経営者の危機意識の欠如が根本の問題だと思います。経営者に危機意識があればいかに多忙であっても外国の動向を理解し、経営者自らがリーダーシップを取って対処することになるはずですが、経営者を含め、真摯に取り組む姿勢が不十分な企業がまだまだ存在することは憂慮に耐えません。先にも述べましたようにQC(品質管理)導入時の危機意識や熱気を覚えている人達は企業から去っていると思いますが、改めて当時の精神に立ち帰ることが必要だと思います。
5年ほど前、私がある外資系の出版社の手伝いをしていた時に、デミング博士の自叙伝を翻訳出版しようと思って、日本科学技術連盟にご意見をお聞きしました。日本科学技術連盟は、「現在日本において生産部門の地位は当時に比し低下しています。デミング賞も国内で無く、東南アジアの会社の受賞が増えています。恐らくデミング博士の自叙伝は日本ではあまり売れないでしょう」ということでしたので出版を断念しました。私が若い頃の世の中のQCに対する熱気を思い出す時、隔世の感があります。
②導入にあたり、中心となって推進する団体、リーダーがいない
品質管理導入時には、日本科学技術連盟(会長は初代経済団体連合会会長石川一郎氏)が普及の主体となり、普及が進むにつれて、個別的なコンサルティングを行う民間のコンサルティング会社が発達しました。
今日コーポレート・ガバナンス体制の構築、内部統制とリスクマネジメント、さらにはERMを導入推進するについては、当時とは逆に個別的なマターを扱う民間のコンサルティング会社はおびただしくありますが、我が国全体として導入の推進を図る、かつての日本科学技術連盟のような団体は存在しません。監査法人系は従来のリスクマネジメントの経験が少なく、損害保険会社系や、リスクマネジメントの専門家は、コーポレート・ガバナンスや内部統制についての経験が少ないという問題点もあります。
学問の世界を見ても、コーポレート・ガバナンス論、監査論(外部、内部、監査役)、リスクマネジメント論など専門分野が多岐にわたるので、内部統制、リスクマネジメント、さらにはERMをコーポレート・ガバナンス体制構築の見地から企業に導入するについて指導的な役割を果す学者の存在もはっきりしません。
コーポレート・ガバナンス体制構築のため内部統制に支えられたリスクマネジメント、さらにはERMを導入するについては各部門にまたがる問題ですから、企業の担当部門としては経営企画部、総務部、経理部、監査部、法務部、リスク管理部等多くの部門が関係します。
また、関係者の間で現状とあるべき姿についての共通認識が醸成され難い状態にあると思います。従って企業において何れかの部門が中心となって推進するにしても、経営者の明確な指示が無ければ推進は到底不可能です。
経営者をはじめ関係者は、旗を振る外部の組織が無ければ、体系的に学ぶことは困難です。このような状態で経営者が自発的に問題の本質を理解し、重要性の認識を持つことは容易ではありません。
③経営者の理解
統計的品質管理の本質を経営者が理解するのは容易でした。なぜならば、品質管理は主として製造部門の問題であって、理論は単純であり、製造担当役員を頂点とする製造部門が推進すればよかったので、縦割りの日本企業においては、やり易いことであったと考えられます。
経営者が自発的に問題の本質を理解し、重要性の認識を持つことは容易ではありません。
しかし、部下が経営者を啓蒙し、リーダーシップを取らせるのは大変難しいことですから、経営者が自ら事の本質を理解してこの問題に取り組むことしか方策はありません。6.日本の実情に適した管理体制を 話は横道に逸れますが、私はバラの栽培が趣味です。西欧の園芸・バラの栽培と日本の園芸の異なる点ですが、盆栽や、サツキ(皐月)、菊などは、栽培法の本には書ききれない微妙な技術が要求されます。バラの栽培は、本当は微妙な技術が要求されているのかも知れませんが、本に書いてある通りのプロセスをキチンと守れば綺麗な花が咲いてくれます。
また、欧米のバラの花の写真は大体満開です。日本のバラの花の写真は7分咲きか8分咲きくらいです。これは欧米人と日本人の美的感覚の差異だと思われます。生け花とフラワー・アレンジメントの感覚の相違とも言えます。
言いたいことは、欧米から輸入されたものが、日本人の感覚の相違によって異なるものになるということがあるということです。園芸の微妙な技術・花の美しさに対する相違と同じようなことが、経営管理手法の導入にあたってもあるように思われます。 我が国では法制度と実務が乖離している場合が多々あります。欧米から輸入した株式会社法の建前と、我が国の株式会社の実務・実状との甚しい乖離も大きな問題です。ごく最近そのことを痛感しました。
繰り返しになりますが、経営管理手法の直輸入では無く、わが国の実情を考慮して根本精神を失うことなく、日本化することが大切だと思います。しかし、現状我が国にそのような人材がいるのか疑問です。
○参考文献:
*一橋大学 佐々木聡教授 『戦後日本のマネジメント手法の導入』 『一橋ビジネスレビュー』(東洋経済新報社)2002年秋号
*財団法人日本科学技術連盟 「創立50年史」
(了)
- keyword
- リスクマネジメントの本質
リスクマネジメントの本質の他の記事
- 最終回 戦後日本のアメリカ流マネジメント手法の導入
- 第5回 家庭電器大手の業績について
- 第4回 リスクマネジメントの実践における経営的視点の欠如
- 第3回 東日本大震災の関係報告書に見るわが国企業における危機管理の問題点
- 第2回 我が国における BCP (事業継続計画 ) の問題点
おすすめ記事
-

「防災といえば応用地質」。リスクを可視化し災害に強い社会に貢献
地盤調査最大手の応用地質は、創業以来のミッションに位置付けてきた自然災害の軽減に向けてビジネス領域を拡大。保有するデータと専門知見にデジタル技術を組み合わせ、災害リスクを可視化して防災・BCPのあらゆる領域・フェーズをサポートします。天野洋文社長に今後の事業戦略を聞きました。
2025/10/20
-

-
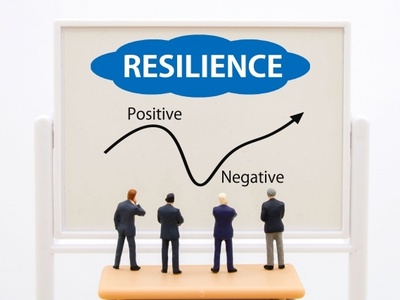
-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2025/10/14
-

走行データの活用で社用車をより安全に効率よく
スマートドライブは、自動車のセンサーやカメラのデータを収集・分析するオープンなプラットフォームを提供。移動の効率と安全の向上に資するサービスとして導入実績を伸ばしています。目指すのは移動の「負」がなくなる社会。代表取締役の北川烈氏に、事業概要と今後の展開を聞きました。
2025/10/14
-

-

-

-

トヨタ流「災害対応の要諦」いつ、どこに、どのくらいの量を届ける―原単位の考え方が災害時に求められる
被災地での初動支援や現場での調整、そして事業継続――。トヨタ自動車シニアフェローの朝倉正司氏は、1995年の阪神・淡路大震災から、2007年の新潟県中越沖地震、2011年のタイ洪水、2016年熊本地震、2024年能登半島地震など、国内外の数々の災害現場において、その復旧活動を牽引してきた。常に心掛けてきたのはどのようなことか、課題になったことは何か、来る大規模な災害にどう備えればいいのか、朝倉氏に聞いた。
2025/10/13
-















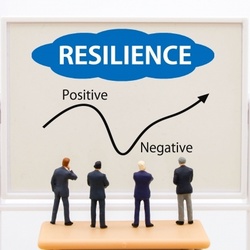

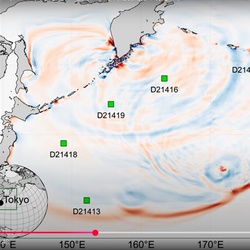

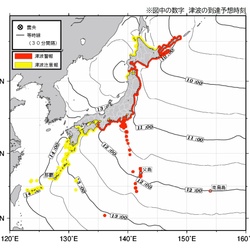
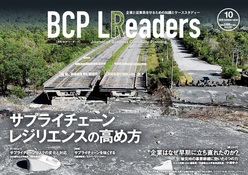



![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)






※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方