2019/02/13
インタビュー

賃貸住宅をDIY断熱化する
伊:「これからのリノベーション 断熱・気密編」は、地方の空き家リノベーションや古民家再生を想定してつくったのですが、読者からは「賃貸でも断熱できますか?」という問い合わせがかなり多かったんです。改めて、こんなに多くの人が賃貸暮らしに不満を持っていることが改めて分かりました。みんな寒さに悩んでます。
あ:私もいまは賃貸ですが、将来は新築もしくは、実家をリフォームして住む可能性もある。同じ事情で賃貸のまま暮らしている人もけっこう多いと思います。賃貸だと、原状回復義務があると建物を断熱化しようという発想に至らない。結局寒い家に住んでいても我慢してしまうんですよね。
イギリス保健省では「室温が18℃未満になる住空間は健康を害する」として、賃貸住宅には解体命令も出るそうです。これからは賃貸物件も余ってくる時代なので、世の中の大家さん全員に「内窓」(うちまど:窓の断熱性を高めるため、室内側から後付けする窓)を取り付けてほしいですね。
伊:賃貸物件で暮らすことは、ほとんどの場合がキャンプ状態です(笑)。こうした現状では、住まい手自身が必要なものを持ち運んで快適な環境を作る、というアウトドア的発想も必要だと思うんですよ。
何かいい方法はないか。最近すごく考えているんですけど。例えばいまDIY賃貸で、壁に傷をつけずに壁面装飾ができる「ディアウォール」(若井産業(株))というツールが人気です。こうした発想で、壁に傷をつけずに断熱材を固定したり、内窓を取り付けられたらよい。こうしたパーツをオンラインで簡単にオーダーできないか、と断熱材・窓のメーカーさんに提案しているところです。
あ:すごくいいですね。現状では災害が起きたあとの復旧・復興に大量の予算をつけていますが、それよりも圧倒的に少ない投資で事前予防をすることで、災害も日常の暮らしも快適になる。防災の観点でも「住まいの断熱」という手段をもっと知ってもらいたいですね。
思想よりも技術が社会を変える
伊:札幌市に築40年の北海道名誉教授・荒谷登さんの旧自邸があります。見学に行ったのですが、温熱や湿度、結露水など環境をコントロールするために、とても緻密な設計やおさまりがあり、試行錯誤をしている。現在のエコハウスと対比すると、40年という時間軸で住宅がここまで進歩している、とそのスピードを実感できます。それは住まい手にとって希望の持てることです。
あ:かつて「電気のない暮らし」というと、原始時代に戻るイメージがありました。でもいま最新のアウトドア道具を駆使すれば、電気が不要な道具があったり、山奥でもソーラー発電や蓄電バッテリーで電気を自給できたりと、かなり快適な生活ができます。技術はどんどん進歩していますね。
伊:先日、音楽プロデューサーの小林武さんとお会いする機会がありました。小林さんは15年前から環境やエネルギーの活動をされていますが、東日本大震災後は「社会は何にも変わらないや」という失望があったそうです。でもここ数年でエネルギーに関する技術がものすごく進歩して、選択肢が増えている。おそらく世の中は、思想が広まるよりもっと早く劇的に、技術の進歩によって変わっていく。そのことに希望を持たれていました。
あ:私達もその進歩をうまく使いこなして、暮らしを豊かにしていきたいですね。本日はどうもありがとうございました。
■関連記事「自宅を防災仕様にすれば、お肌ぷるぷる!?」
http://www.risktaisaku.com/articles/-/14528
インタビューの他の記事
おすすめ記事
-

リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ
リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。
2026/01/05
-
年末年始にサイバー攻撃は約2倍以上増加する
サイバー攻撃のリスクは、平日よりも休日に高まる傾向がある。デジタルデータソリューション株式会社(東京都港区)の調査によると、年末年始にはサイバー攻撃が約2倍以上に増加することが明らかになっているという。
2026/01/04
-

能登半島地震からまもなく2年
能登半島地震からまもなく2年。災害対応の検証も終盤に入っています。浮上した課題を反映し、災害関連法も変わりました。来年はこれらの内容をふまえた防災・BCPの見直しが加速しそうです。発災直後から被災地を調査し、石川県の初動対応を振り返る検証委員会の委員も務めた金沢大学准教授の青木賢人氏に防災・BCP強化の方向を聞きました。
2025/12/25
-

-

-

-

中澤・木村が斬る!今週のニュース解説
毎週火曜日(平日のみ)朝9時~、リスク対策.com編集長 中澤幸介と兵庫県立大学教授 木村玲欧氏(心理学・危機管理学)が今週注目のニュースを短く、わかりやすく解説します。
2025/12/23
-

-

-

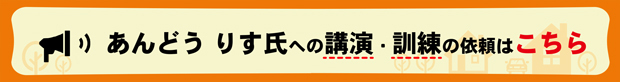
























![2022年下半期リスクマネジメント・BCP事例集[永久保存版]](https://risk.ismcdn.jp/mwimgs/8/2/160wm/img_8265ba4dd7d348cb1445778f13da5c6a149038.png)




※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方