第4回 旅館業の事業継続計画

小山 和博
外食業、会計事務所勤務を経て、(株)インターリスク総研にて 2007 ~ 2017年の間、事業継続、危機管理、労働安全衛生、事故防止、組織文化に関するコンサルティングに従事。2017 年よりPwC総合研究所に参画し、引き続き同分野の調査研究、研修、コンサルティングを行っている。
2016/06/03
業種別BCPのあり方

小山 和博
外食業、会計事務所勤務を経て、(株)インターリスク総研にて 2007 ~ 2017年の間、事業継続、危機管理、労働安全衛生、事故防止、組織文化に関するコンサルティングに従事。2017 年よりPwC総合研究所に参画し、引き続き同分野の調査研究、研修、コンサルティングを行っている。
編集部注:「リスク対策.com」本誌2013年7月25日号(Vol.38)掲載の連載を、Web記事として再掲したものです。(2016年6月3日)
日本旅行業協会の資料によれば、観光産業に従事する人口は直接雇用だけで229万人、波及効果による雇用も合わせると424万人であり、特に地方経済における観光産業の存在感は大きい。現在、各都道府県において、事業継続計画の策定を民間企業に勧める動きが活発であるが、その中でもホテル・旅館業への働きかけが大きな課題となっている。
ホテル・旅館業の特性として、小規模企業者が全体に占める比率が高く、従業者数も50人以下の規模に留まる事業者が多いことが挙げられる。しかも緊急時にホテル・旅館業が守らなければならない旅行客はその地域や施設を熟知していないことが圧倒的に多く、対応の困難さを更に増している。そこで、本稿では、ホテル・旅館業の事業継続を考える。
■お客さまを守る防災対策の徹底は事業継続の基礎
ホテル・旅館業では、過去幾度となく大規模火災による死傷事故例が発生しており、建築基準法や消防法に基づき、様々な対策が義務付けられている。特に重要な対応策としては主に以下の4点がある。
自社の事業継続を図ろうとするのであれば、まずこれら法令上の義務を確実にクリアすることが第一歩となる。ところが、ホテル・旅館業における事件・事故例を精査すると、まずこのレベルのクリアが大きな課題であることが分かる。
2012年に発生したホテル火災による死亡事件をうけ、国土交通省・総務省消防庁が連携して緊急調査が行われた。その結果は、表2のとおりである。
特に気になるのは、この消防法令違反を指摘された549施設のうち、スプリンクラー設備、屋内消火栓設備または自動火災報知設備のいずれかの設備が、その設備の設置義務部分の床面積の過半にわたり設置されていないという「重大な違反」47施設が(5.9%)あったことである。各種事情はあろうが、この段階の取り組みは計画的に早めに完了しておきたい。
また、法令上の規制はあくまで必要最小限である。専門家による耐震診断と補強、飛散防止フイルムの貼付によるガラスの飛散防止、出入口・通路の障害物除去や大型機器類の移動・転倒防止による避難通路の確保、施設内の避難誘導や安全確認のための図面等の準備などのハード面の対策も各施設の実情に合わせて実施を検討することを勧めたい。
■緊急時に備えて考えておくべき対応
いかなる自然災害、事件事故にも共通して考えておくべき緊急時の対応方針として、最低限の項目はルールを決めておく必要がある。その一覧は表3のとおりである。
業種別BCPのあり方の他の記事
おすすめ記事



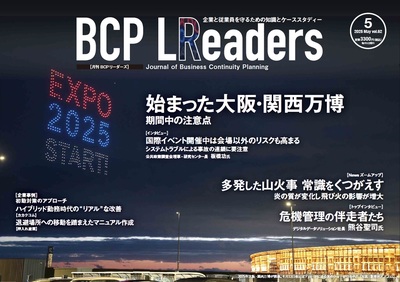
リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ
リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。
2025/05/05
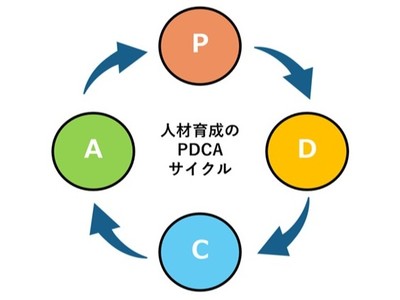
企業理念やビジョンと一致させ、意欲を高める人を成長させる教育「70:20:10の法則」
新入社員研修をはじめ、企業内で実施されている教育や研修は全社員向けや担当者向けなど多岐にわたる。企業内の人材育成の支援や階層別研修などを行う三菱UFJリサーチ&コンサルティングの有馬祥子氏が指摘するのは企業理念やビジョンと一致させる重要性だ。マネジメント能力の獲得や具体的なスキル習得、新たな社会ニーズ変化への適応がメインの社内教育で、その必要性はなかなかイメージできない。なぜ、教育や研修において企業理念やビジョンが重要なのか、有馬氏に聞いた。
2025/05/02


備蓄燃料のシェアリングサービスを本格化
飲料水や食料は備蓄が進み、災害時に比較的早く支援の手が入るようになりました。しかし電気はどうでしょうか。特に中堅・中小企業はコストや場所の制約から、非常用電源・燃料の備蓄が難しい状況にあります。防災・BCPトータル支援のレジリエンスラボは2025年度、非常用発電機の燃料を企業間で補い合う備蓄シェアリングサービスを本格化します。
2025/04/27

自社の危機管理の進捗管理表を公開
食品スーパーの西友では、危機管理の進捗を独自に制作したテンプレートで管理している。人事総務本部 リスク・コンプライアンス部リスクマネジメントダイレクターの村上邦彦氏らが中心となってつくったもので、現状の危機管理上の課題に対して、いつまでに誰が何をするのか、どこまで進んだのかが一目で確認できる。
2025/04/24


常識をくつがえす山火事世界各地で増える森林火災
2025年、日本各地で発生した大規模な山火事は、これまでの常識をくつがえした。山火事に詳しい日本大学の串田圭司教授は「かつてないほどの面積が燃え、被害が拡大した」と語る。なぜ、山火事は広がったのだろうか。
2025/04/23
※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方