第21回 緊急事態における企業の対応要員の行動
型を持って型を破る

小山 和博
外食業、会計事務所勤務を経て、(株)インターリスク総研にて 2007 ~ 2017年の間、事業継続、危機管理、労働安全衛生、事故防止、組織文化に関するコンサルティングに従事。2017 年よりPwC総合研究所に参画し、引き続き同分野の調査研究、研修、コンサルティングを行っている。
2016/10/06
業種別BCPのあり方

小山 和博
外食業、会計事務所勤務を経て、(株)インターリスク総研にて 2007 ~ 2017年の間、事業継続、危機管理、労働安全衛生、事故防止、組織文化に関するコンサルティングに従事。2017 年よりPwC総合研究所に参画し、引き続き同分野の調査研究、研修、コンサルティングを行っている。

平成28 年熊本地震の発生に伴い、多くの企業に被害が生じている。今回は、編集部からのご依頼により、「業種別BCPのあり方」シリーズの特別篇として、企業向けの研修で筆者がご案内している緊急事態発生直後における心得の一部をご紹介する。
編集部注:「リスク対策.com」本誌2016年5月25日号(Vol.55)掲載の連載を、Web記事として再掲したものです。(2016年10月6日)
地震、洪水、風水害、爆発、テロ、感染症。企業を取り巻くリスク事象は様々なものがあるが、自社の事業が展開されている地域において何らかの被害が生じた場合は、自社に被害が生じていないことを確認する。人間はつい「恐らく被害はないだろう」「連絡が来ないのだから、大丈夫なのだろう」と考えてしまう。一般従業員はそれでもよいが、緊急事態対応要員はそれでは務まらない。大きな被害が生じかねないリスク事象の発生時は、社内で事実確認の体制を取ることが危機管理の第一歩である。
この確認を確実に行うためには、被害確認を行うリスク事象を特定し、部署間の役割と責任を明確にした上で、これを規則としておくとよい。これは、緊急事態の初動対応時によく見られる事態として「被害があれば報告があるはず」として、事実確認のため情報収集に必要な体制を取ること自体が不要だという意見が社内から出てくるからである。事実確認の結果、被害がなかった場合には、このような意見の持ち主は「だから大騒ぎしなくてよかったのだ、大げさすぎる」と主張する。
確かに、被害の有無について事実確認の体制を取り、結果として被害がないことを確認して、その態勢を解除することにはコストがかかるが、組織の緊急事態対応力を高めるうえで必要な投資であると考える。
大規模な災害のあと報道でよく使われる「被害の報告は入っていません」という表現がある。社会を相手とする報道であればこれでもよいが、組織の中での報告では不適切であるし、当該組織のリスク情報に対する感性の低さを示すことにもなる。あるべき表現としては「現地の従業員に連絡をとって、状況を確認しています」もしくは「現地と連絡が取れないため、要員を派遣しています」といったものになる。
情報は自ら取りに行くものであって、報告を待つものではない。また、緊急事態においては、特定地域に関する情報がないこと自体が被害の大きさを示していることもある。連絡が取れない地域があるのであれば、状況確認のために、要員派遣を検討する。現地の危険情報を確認し、進入可能な経路を複数チェックする。そのうえで、水、食料、寝袋、現金といったものを持参した複数の人間で構成するチームをいくつか編成し、異なる方向からの進入を試みさせることが理想である。
大手ホームセンターのA社が被害確認のため現地に要員を派遣する際には、そのホームセンターの名前が明記されたジャンバーなどを着用させる。現地に向かう途中、警察や自治体職員に「何をしに来たのだ」と目的を確認された際には、ジャンバーを見せ、「被災状況の確認と支援のためにきている」と言うようにしているとのことである。
業種別BCPのあり方の他の記事
おすすめ記事



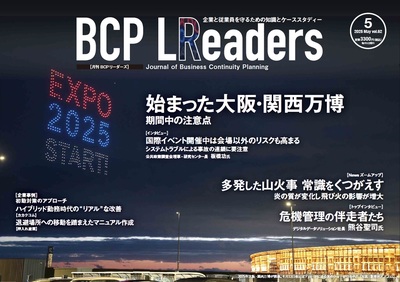
リスク対策.PROライト会員用ダウンロードページ
リスク対策.PROライト会員はこちらのページから最新号をダウンロードできます。
2025/05/05
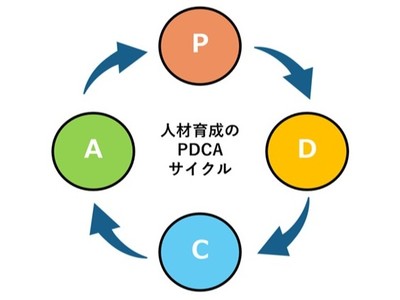
企業理念やビジョンと一致させ、意欲を高める人を成長させる教育「70:20:10の法則」
新入社員研修をはじめ、企業内で実施されている教育や研修は全社員向けや担当者向けなど多岐にわたる。企業内の人材育成の支援や階層別研修などを行う三菱UFJリサーチ&コンサルティングの有馬祥子氏が指摘するのは企業理念やビジョンと一致させる重要性だ。マネジメント能力の獲得や具体的なスキル習得、新たな社会ニーズ変化への適応がメインの社内教育で、その必要性はなかなかイメージできない。なぜ、教育や研修において企業理念やビジョンが重要なのか、有馬氏に聞いた。
2025/05/02


備蓄燃料のシェアリングサービスを本格化
飲料水や食料は備蓄が進み、災害時に比較的早く支援の手が入るようになりました。しかし電気はどうでしょうか。特に中堅・中小企業はコストや場所の制約から、非常用電源・燃料の備蓄が難しい状況にあります。防災・BCPトータル支援のレジリエンスラボは2025年度、非常用発電機の燃料を企業間で補い合う備蓄シェアリングサービスを本格化します。
2025/04/27

自社の危機管理の進捗管理表を公開
食品スーパーの西友では、危機管理の進捗を独自に制作したテンプレートで管理している。人事総務本部 リスク・コンプライアンス部リスクマネジメントダイレクターの村上邦彦氏らが中心となってつくったもので、現状の危機管理上の課題に対して、いつまでに誰が何をするのか、どこまで進んだのかが一目で確認できる。
2025/04/24


常識をくつがえす山火事世界各地で増える森林火災
2025年、日本各地で発生した大規模な山火事は、これまでの常識をくつがえした。山火事に詳しい日本大学の串田圭司教授は「かつてないほどの面積が燃え、被害が拡大した」と語る。なぜ、山火事は広がったのだろうか。
2025/04/23
※スパム投稿防止のためコメントは編集部の承認制となっておりますが、いただいたコメントは原則、すべて掲載いたします。
※個人情報は入力しないようご注意ください。
» パスワードをお忘れの方